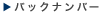月刊みんぱく 2006年5月号
2006年5月号
第30巻第5号通巻第344号
2006年5月1日発行
2006年5月1日発行
カンボジアで、今、光っている人材育成
大村 次郷
重なり合うように埋められた仏像群から「千体仏」が宙に浮いたときは、おもわず手をたたいた。約八〇〇年のねむりから覚めた遺物は優に四五〇キロはある。それをとり上げたのは日本人の学徒ではなく、上智大学が育ててきた現地の考古、建築、石工の人たちだった。
今、カンボジアでは日本人による人材育成が目にとまる。ひとつはこの上智大学のプロジェクトと、もうひとつは京都出身の染色家、森本喜久男氏が始めた伝統織物の再興である。どちらも腰をすえた仕事だ。それらは内乱で失われた技術、知識取得などに重きを置く。
考古学はややもすると資金を出す関係者への成果に期待をし、地元の人たちには益にならないことが多い。上智大学は発掘する現地の人たちを育て、彼らに掘らせて、それを調査、修復、そして保護することを学ばせてきた。日本に招いた人たちもかるく一〇人をこえている。
その過渡期に、神が配剤したとしか思えない二七四体の廃仏発見にぶつかったのだ。「千体仏」もアンコールの考古学の発掘史上画期的な出土物であったが、表面が浮いていて、綱のかけ方を間違うと壊れる状況であった。難しい出土物をいためずに彼ら自身の手でとり上げたのは、上智大学が意図したことが実を結んだ結果である。
また染色家の森本氏の工房をシュムレアップ川沿いにたずねると、糸をつむぐ人たち、織る人たちのまわりには乳飲み児がたくさんいた。女性たちの数はおよそ五〇〇人。この町で子どもを連れて働ける、唯一の職場である。その彼女たちが織っている絹は、内乱でほとんどなくなっていた。
この絹はマユ玉からわずか二〇〇メートルしか引き出せない生糸で織られるものだが、森本氏はこの再興に力を入れたのだ。その染料も、この国が古来よりやってきたとおりに草木をつかうことに徹した。日本などからは何ももち込まなかった。彼女たちが染料となる草木を庭に植え、それを買い上げるシステムまで作り上げている。赤い染料となるラックカイガラ虫は今、この国にはいない。それを放虫する森を作ろうと、彼はこころみている。
このプロジェクトにスイスの時計メーカー(ローレックス)が賞を出したのは、他ならぬ戦いで未亡人になった人たち、働きたい人たちに希望を与えたからだ。老婆の手のなかに残された織物の世界が、次の世代に受けつがれていく。
おおむら つぐさと/1941年、旧満州生まれ。写真家。アジアを中心に世界各地のフォト・ルポルタージュを手がける。NHKのドキュメンタリー番組「新シルクロード」ほかのスチールを担当。1999年、大同生命地域研究特別賞受賞。おもな著書に『遺跡が語るアジア』(中公新書)『アジアをゆく』全7巻(集英社)などがある。
今、カンボジアでは日本人による人材育成が目にとまる。ひとつはこの上智大学のプロジェクトと、もうひとつは京都出身の染色家、森本喜久男氏が始めた伝統織物の再興である。どちらも腰をすえた仕事だ。それらは内乱で失われた技術、知識取得などに重きを置く。
考古学はややもすると資金を出す関係者への成果に期待をし、地元の人たちには益にならないことが多い。上智大学は発掘する現地の人たちを育て、彼らに掘らせて、それを調査、修復、そして保護することを学ばせてきた。日本に招いた人たちもかるく一〇人をこえている。
その過渡期に、神が配剤したとしか思えない二七四体の廃仏発見にぶつかったのだ。「千体仏」もアンコールの考古学の発掘史上画期的な出土物であったが、表面が浮いていて、綱のかけ方を間違うと壊れる状況であった。難しい出土物をいためずに彼ら自身の手でとり上げたのは、上智大学が意図したことが実を結んだ結果である。
また染色家の森本氏の工房をシュムレアップ川沿いにたずねると、糸をつむぐ人たち、織る人たちのまわりには乳飲み児がたくさんいた。女性たちの数はおよそ五〇〇人。この町で子どもを連れて働ける、唯一の職場である。その彼女たちが織っている絹は、内乱でほとんどなくなっていた。
この絹はマユ玉からわずか二〇〇メートルしか引き出せない生糸で織られるものだが、森本氏はこの再興に力を入れたのだ。その染料も、この国が古来よりやってきたとおりに草木をつかうことに徹した。日本などからは何ももち込まなかった。彼女たちが染料となる草木を庭に植え、それを買い上げるシステムまで作り上げている。赤い染料となるラックカイガラ虫は今、この国にはいない。それを放虫する森を作ろうと、彼はこころみている。
このプロジェクトにスイスの時計メーカー(ローレックス)が賞を出したのは、他ならぬ戦いで未亡人になった人たち、働きたい人たちに希望を与えたからだ。老婆の手のなかに残された織物の世界が、次の世代に受けつがれていく。
おおむら つぐさと/1941年、旧満州生まれ。写真家。アジアを中心に世界各地のフォト・ルポルタージュを手がける。NHKのドキュメンタリー番組「新シルクロード」ほかのスチールを担当。1999年、大同生命地域研究特別賞受賞。おもな著書に『遺跡が語るアジア』(中公新書)『アジアをゆく』全7巻(集英社)などがある。
「遊び」はとても広範なとらえにくい行動である。
ゲームや賭け事、遊興、果ては
「いない・いない・ばあ」も遊びであれば、
仕事一般の対義語も遊びである。
しかも、それは人に固有の行動ではなく、
ネコやイヌ、イルカのような高等脊椎動物も
原初的な遊びをすることが知られている。
本特集ではこうした多様な遊びと、
それをとらえる視点の拡がりを、人以外の霊長類や
世界各地の事例から見ていきたい。
ゲームや賭け事、遊興、果ては
「いない・いない・ばあ」も遊びであれば、
仕事一般の対義語も遊びである。
しかも、それは人に固有の行動ではなく、
ネコやイヌ、イルカのような高等脊椎動物も
原初的な遊びをすることが知られている。
本特集ではこうした多様な遊びと、
それをとらえる視点の拡がりを、人以外の霊長類や
世界各地の事例から見ていきたい。
遊びと仕事の遠近
楽しく自由な行動
遊びの領域が曖昧なように、その評価も矛盾を含む。幼児期の遊びは社会関係を構築する訓練として推奨され、多くの人は大人になっても遊びが人間らしい豊かな生活を送るため、あるいはあらたなことを創造するために欠かせないものだと感じている。だが、他方でわたしたちは、学童期以降おそらく定年退職するその日まで「遊んでばかりいないで勉強(仕事)しろ」という強迫観念にさいなまれる。この場合の遊びは創造の源泉どころか、怠け者のレッテルだ。
確かに度が過ぎた遊びは身上をつぶしかねない。だが、幼少のころから将棋で遊び、それに打ち込んだ人が、棋士になれたのではなかったか。だとすると、将来の仕事に遊びが活かされることはありえないことではない。また、ある行動の形式、たとえば将棋、野球、楽器演奏などが、初めから遊びか仕事かという属性をもつのではない。ときに漫然と仕事をしたり一心不乱に遊んだりするわたしたち自身を思い起こせば、仕事と結びつけられがちな真剣さや真面目さが、遊びと仕事を分かつ要因でないことも明らかだ。このように考えると、遊びとは遊び手が楽しみでする自由な行動である、という単純な定義が適当に思える。楽しみでする自由な行動であれば、たとえそれが肉体的に過酷であっても労苦を感じないだろう。そこに、ある種の仕事のなかにも、遊びの様態が入り込む余地が残されている。
ネパールのカーム
遊びと仕事の峻別と、仕事により高い価値をおく勤勉の精神は、近代の合理的精神の産物である。近代以前や人以前の動物では両者は未分化であり、仕事あるいは生きることのなかに遊びが入り混じっていた。たとえばネパールでは、公私混同と思われるだろうが、仕事の最中におしゃべりをしたり、私的な友人と会ったり、軽い飲食を摂ることが広く受け入れられている。それらは仕事に付随することとされ、「遊び」とは認識されていないのだ。それゆえネパール語には、仕事(カーム)の対義語が未だにない。
ネパールではよく「開発が進んだ日本のような国では、人は誰一人働かなくてもよい」といわれる。分刻みで働く日本人には信じがたい言葉だが、彼または彼女らはデスクワークのような軽微な労働をカームとみなしていない。カームはあくまで、荷物をかつぐ作業や犂(すき)を用いた耕作などの農作業に代表される、額に汗する労働をさすのだ。だから、息子が公務員になると母親は「もう仕事をしなくてもよい。オフィスに座っていれば給料がもらえる」と、喜々として話すことになる。
日本人の目には遊んでいるように映るネパール人の仕事ぶりと、それとは異なる理由でネパール人の目には遊んでいるように見える日本人の仕事。そこには、遊びとは何か、遊び手が楽しみでする自由な行動を仕事のなかに取り戻すことができるか、といった問いのヒントが隠されているようだ。
遊びの領域が曖昧なように、その評価も矛盾を含む。幼児期の遊びは社会関係を構築する訓練として推奨され、多くの人は大人になっても遊びが人間らしい豊かな生活を送るため、あるいはあらたなことを創造するために欠かせないものだと感じている。だが、他方でわたしたちは、学童期以降おそらく定年退職するその日まで「遊んでばかりいないで勉強(仕事)しろ」という強迫観念にさいなまれる。この場合の遊びは創造の源泉どころか、怠け者のレッテルだ。
確かに度が過ぎた遊びは身上をつぶしかねない。だが、幼少のころから将棋で遊び、それに打ち込んだ人が、棋士になれたのではなかったか。だとすると、将来の仕事に遊びが活かされることはありえないことではない。また、ある行動の形式、たとえば将棋、野球、楽器演奏などが、初めから遊びか仕事かという属性をもつのではない。ときに漫然と仕事をしたり一心不乱に遊んだりするわたしたち自身を思い起こせば、仕事と結びつけられがちな真剣さや真面目さが、遊びと仕事を分かつ要因でないことも明らかだ。このように考えると、遊びとは遊び手が楽しみでする自由な行動である、という単純な定義が適当に思える。楽しみでする自由な行動であれば、たとえそれが肉体的に過酷であっても労苦を感じないだろう。そこに、ある種の仕事のなかにも、遊びの様態が入り込む余地が残されている。
ネパールのカーム
遊びと仕事の峻別と、仕事により高い価値をおく勤勉の精神は、近代の合理的精神の産物である。近代以前や人以前の動物では両者は未分化であり、仕事あるいは生きることのなかに遊びが入り混じっていた。たとえばネパールでは、公私混同と思われるだろうが、仕事の最中におしゃべりをしたり、私的な友人と会ったり、軽い飲食を摂ることが広く受け入れられている。それらは仕事に付随することとされ、「遊び」とは認識されていないのだ。それゆえネパール語には、仕事(カーム)の対義語が未だにない。
ネパールではよく「開発が進んだ日本のような国では、人は誰一人働かなくてもよい」といわれる。分刻みで働く日本人には信じがたい言葉だが、彼または彼女らはデスクワークのような軽微な労働をカームとみなしていない。カームはあくまで、荷物をかつぐ作業や犂(すき)を用いた耕作などの農作業に代表される、額に汗する労働をさすのだ。だから、息子が公務員になると母親は「もう仕事をしなくてもよい。オフィスに座っていれば給料がもらえる」と、喜々として話すことになる。
日本人の目には遊んでいるように映るネパール人の仕事ぶりと、それとは異なる理由でネパール人の目には遊んでいるように見える日本人の仕事。そこには、遊びとは何か、遊び手が楽しみでする自由な行動を仕事のなかに取り戻すことができるか、といった問いのヒントが隠されているようだ。
遊びを楽しむ霊長類
早木 仁成
人間の子どものように
野猿公園などでニホンザルの子どもをしばらく眺めていると、いつの間にか子ザルたちが集まり、枝にぶら下がって絡み合ったり、取っ組み合いのレスリングをしたり、広場を走り回って追いかけっこをしたりする光景に出会う。はじめてサルを見る人には喧嘩をしているように見えるかもしれないが、慣れてくれば喧嘩とはずいぶん様子が異なることに気がつくはずである。喧嘩なら聞こえる悲鳴や吠え声がない。年長の子ザルたちはかなり乱暴で激しく動き回るが、それでも遊びだと気づけば、彼らはいかにも楽しそうに見えてくる。
チンパンジーの遊びは、ニホンザルに比べると身体が大きいこともあって、動きが緩やかな印象を受ける。取っ組み合いをしているチンパンジーには、しばしば口を大きく開けた遊び顔とよばれる表情が見られ、組み伏せられた方からは特徴的なあえぎ声が聞こえることもある。その様子は、げらげらと笑いながらじゃれ合っている人間の子どもたちとほとんど変わらない。
強者の自制
彼らが本当に遊びを楽しんでいるのかどうかを確認することは困難だが、楽しんでいるのだと仮定すれば、彼らの遊びのなかには、楽しむためのさまざまな仕掛けが存在することに気づかされる。その仕掛けのなかでも代表的なものは、セルフハンディキャッピングとよばれる現象である。
セルフハンディキャッピングとは、体格差があるような者同士で遊ぶときに、強い方が自分の力を抑えて弱い方に合わせてやるという現象である。レスリングの遊びでは強者がわざと下になり、追いかけっこ遊びでは強者が逃げる側になる。こうして強者が弱者のようなふるまいをすると、普段強者の前で自己を抑制している弱者も遠慮せずに遊べるというわけである。
強者が弱者に対して遊びを強要することはむずかしい。強者が抑制することによって弱者のやる気を引き出し、遊びが維持されるのである。弱者がいったんその気になれば、遊びが少々荒っぽいものになっても平気である。ただし、遊びが弱者に統御不可能なほど激しくなると、弱者は急に動きを止める。すると、たいてい強者も弱者に合わせて動きを止め、遊びは中断する。中断と書いたのは、短い休止の後に遊びはリセットされて再び始まることが多いからである。この中断を伴いながら遊びが繰り返されるという連鎖的な構造も、遊びを楽しむためのうまい仕掛けになっている。
野猿公園などでニホンザルの子どもをしばらく眺めていると、いつの間にか子ザルたちが集まり、枝にぶら下がって絡み合ったり、取っ組み合いのレスリングをしたり、広場を走り回って追いかけっこをしたりする光景に出会う。はじめてサルを見る人には喧嘩をしているように見えるかもしれないが、慣れてくれば喧嘩とはずいぶん様子が異なることに気がつくはずである。喧嘩なら聞こえる悲鳴や吠え声がない。年長の子ザルたちはかなり乱暴で激しく動き回るが、それでも遊びだと気づけば、彼らはいかにも楽しそうに見えてくる。
チンパンジーの遊びは、ニホンザルに比べると身体が大きいこともあって、動きが緩やかな印象を受ける。取っ組み合いをしているチンパンジーには、しばしば口を大きく開けた遊び顔とよばれる表情が見られ、組み伏せられた方からは特徴的なあえぎ声が聞こえることもある。その様子は、げらげらと笑いながらじゃれ合っている人間の子どもたちとほとんど変わらない。
強者の自制
彼らが本当に遊びを楽しんでいるのかどうかを確認することは困難だが、楽しんでいるのだと仮定すれば、彼らの遊びのなかには、楽しむためのさまざまな仕掛けが存在することに気づかされる。その仕掛けのなかでも代表的なものは、セルフハンディキャッピングとよばれる現象である。
セルフハンディキャッピングとは、体格差があるような者同士で遊ぶときに、強い方が自分の力を抑えて弱い方に合わせてやるという現象である。レスリングの遊びでは強者がわざと下になり、追いかけっこ遊びでは強者が逃げる側になる。こうして強者が弱者のようなふるまいをすると、普段強者の前で自己を抑制している弱者も遠慮せずに遊べるというわけである。
強者が弱者に対して遊びを強要することはむずかしい。強者が抑制することによって弱者のやる気を引き出し、遊びが維持されるのである。弱者がいったんその気になれば、遊びが少々荒っぽいものになっても平気である。ただし、遊びが弱者に統御不可能なほど激しくなると、弱者は急に動きを止める。すると、たいてい強者も弱者に合わせて動きを止め、遊びは中断する。中断と書いたのは、短い休止の後に遊びはリセットされて再び始まることが多いからである。この中断を伴いながら遊びが繰り返されるという連鎖的な構造も、遊びを楽しむためのうまい仕掛けになっている。
遊びながら働く人びと
名本 光男
塩作りの合間に
「あとは誰かに任せて、さあ、遊びに行こうか」
海水が入った釜に薪をくべ、火力が安定してきたとき、塩作り名人・小渡(おど)幸信さんの口から飛び出した言葉に、わたしはいささか驚いてしまった。
職人といえば普通、仕事にどっぷりと浸って、ひたすら精進を続け、最後には道を究める人であって、「仕事」の対極にある「遊び」は、彼のなかにあってはならないものではないのか。ましてや、作業の途中で、遊びに行くなどありえないと、わたしは長らく思っていた。しかし、それがわたしの職人に対する先入観であったことに気づいたのは、塩作りを体験させてもらった後のことだった。
小渡さんは、一〇年ほど前に沖縄県粟国(あぐに)島に渡り、一人で「粟国の塩」を作りはじめた。その後、彼の作る塩は全国的にその名が知れ渡り、今では、二〇人ほどの従業員が彼の元で働いている。
塩作りの工程で、もっとも手間と時間がかかるのは、釜で海水を煮詰めていく作業だ。大きな平釜に海水をなみなみと注いで、薪をくべ、水分を蒸発させていく。一度火を入れると、二〇~二五時間は連続して薪を炊き続けなければならないと言う。だが、その作業はずっと根を詰めるというものでは決してなかった。
かつて、小渡さんは、作業の合間に自分の子どもたちを連れて、島中を遊び回ったものだと言う。南の海岸では島民も知らない奇岩を見つけ、よじ登ったりした。北の海岸近くには、洞寺(てら)とよばれる鍾乳洞があって、今でこそ観光客のために通路や照明が整備され、誰もが安全にその内部を探索することができるようになったが、当時は懐中電灯をもって、泥んこ覚悟でなかに入らなければならなかった。小渡さんは、そこで子どもと一緒にかくれんぼをしたのだという。塩工場の前に広がる珊瑚礁では、干潮時には魚の影を追いかけて、珊瑚が壊れることも気にせず走り回ったそうだ。
人家から隔たっていた塩工場は、夜になると真っ暗な闇と静けさに包まれる。すると、釜場の脇に自作のベンチを引っぱり出し、その上に身を横たえ、薪が静かに燃える音を聞きながら、満天の星のあいだを音もなく横切る人工衛星を数えたりしたと言う。
遊びながらゆっくり
現在、塩工場の規模は大きくなり、生産量も飛躍的に増加した。だが、小渡さんは次のように語る。これからも、今までと同じように釜に薪をくべて、何時間もかけてゆっくりと海水を煮詰めていかなければならない。それを、効率だけを考えて急いでやるようなことになれば、デリケートなミネラル分が抜け落ちてしまって、いい塩はできない。だから、根を詰めずに、ときには遊びながらゆっくりとやればいい。
今のわたしたちは、仕事にしても遊びにしても、あまりに一生懸命になりすぎているのではないか。そして、わたしたちのおこなうさまざまな活動のなかには、小渡さんにとっての塩作りのような、心が躍ることが残っているだろうか。生まれて初めて作った、ほんのりと赤みがかった塩をぼんやり眺めながら、わたしはふとそう思うのであった。
「あとは誰かに任せて、さあ、遊びに行こうか」
海水が入った釜に薪をくべ、火力が安定してきたとき、塩作り名人・小渡(おど)幸信さんの口から飛び出した言葉に、わたしはいささか驚いてしまった。
職人といえば普通、仕事にどっぷりと浸って、ひたすら精進を続け、最後には道を究める人であって、「仕事」の対極にある「遊び」は、彼のなかにあってはならないものではないのか。ましてや、作業の途中で、遊びに行くなどありえないと、わたしは長らく思っていた。しかし、それがわたしの職人に対する先入観であったことに気づいたのは、塩作りを体験させてもらった後のことだった。
小渡さんは、一〇年ほど前に沖縄県粟国(あぐに)島に渡り、一人で「粟国の塩」を作りはじめた。その後、彼の作る塩は全国的にその名が知れ渡り、今では、二〇人ほどの従業員が彼の元で働いている。
塩作りの工程で、もっとも手間と時間がかかるのは、釜で海水を煮詰めていく作業だ。大きな平釜に海水をなみなみと注いで、薪をくべ、水分を蒸発させていく。一度火を入れると、二〇~二五時間は連続して薪を炊き続けなければならないと言う。だが、その作業はずっと根を詰めるというものでは決してなかった。
かつて、小渡さんは、作業の合間に自分の子どもたちを連れて、島中を遊び回ったものだと言う。南の海岸では島民も知らない奇岩を見つけ、よじ登ったりした。北の海岸近くには、洞寺(てら)とよばれる鍾乳洞があって、今でこそ観光客のために通路や照明が整備され、誰もが安全にその内部を探索することができるようになったが、当時は懐中電灯をもって、泥んこ覚悟でなかに入らなければならなかった。小渡さんは、そこで子どもと一緒にかくれんぼをしたのだという。塩工場の前に広がる珊瑚礁では、干潮時には魚の影を追いかけて、珊瑚が壊れることも気にせず走り回ったそうだ。
人家から隔たっていた塩工場は、夜になると真っ暗な闇と静けさに包まれる。すると、釜場の脇に自作のベンチを引っぱり出し、その上に身を横たえ、薪が静かに燃える音を聞きながら、満天の星のあいだを音もなく横切る人工衛星を数えたりしたと言う。
遊びながらゆっくり
現在、塩工場の規模は大きくなり、生産量も飛躍的に増加した。だが、小渡さんは次のように語る。これからも、今までと同じように釜に薪をくべて、何時間もかけてゆっくりと海水を煮詰めていかなければならない。それを、効率だけを考えて急いでやるようなことになれば、デリケートなミネラル分が抜け落ちてしまって、いい塩はできない。だから、根を詰めずに、ときには遊びながらゆっくりとやればいい。
今のわたしたちは、仕事にしても遊びにしても、あまりに一生懸命になりすぎているのではないか。そして、わたしたちのおこなうさまざまな活動のなかには、小渡さんにとっての塩作りのような、心が躍ることが残っているだろうか。生まれて初めて作った、ほんのりと赤みがかった塩をぼんやり眺めながら、わたしはふとそう思うのであった。
伝承される彦根のカロム
杉原 正樹
カロムとは四隅にポケット(穴)がある正方形の盤上で、扁平な円筒形の玉を指で弾いて穴に入れる、ビリヤードに似たゲームである。日本では滋賀県彦根市周辺で古くから遊ばれてきたが、なぜここだけに見られるのか、その伝来の経緯を含めて定かでない。だが、カロムに類似するゲームが名称やルールを少しずつ変えながら、ネパールなど地球上のさまざまなところで今も遊ばれていることは確かだ。
かつて彦根では、一家に一台カロム盤があるといわれるほどポピュラーな遊びだった。正月、地蔵盆、雨の日などに、誰もが遊んだ経験をもつ。古いカロム盤の裏には、製作年や購入年などの墨書がある。発見されたもっとも古いもので大正二年とあるから、一〇〇年近く遊び継がれてきたことになる。所有者や製作者、一円一〇銭といった購入代金、遊び続けると盤面がすり減りラインが消えるので、それを塗り替えた年まで記された盤が現役で使われていたりする。
一九八八年八月二八日、「第一回カロム日本選手権大会」が開催された。子どもから老人までが同じ盤上で対等に競える大会は、デジタルゲームでは味わえない感動があった。各町内からは腕に覚えのある大人たち、自称「名人」が名乗りをあげ、間違いなく日本最高水準の大会だった。以来、大会は年に一度開かれ、今では老人会、小学校、自治会などでも、カロムが我がまちの遊びとして再び脚光をあびている。
近年、彦根カロムは全国に知れ渡るようになった。それによって彦根の人びとは、自分たちの日常の遊びが、じつはこの地域固有のものであることを知った。これに一番驚いたのは、彦根の人びとだったかもしれない。
かつて彦根では、一家に一台カロム盤があるといわれるほどポピュラーな遊びだった。正月、地蔵盆、雨の日などに、誰もが遊んだ経験をもつ。古いカロム盤の裏には、製作年や購入年などの墨書がある。発見されたもっとも古いもので大正二年とあるから、一〇〇年近く遊び継がれてきたことになる。所有者や製作者、一円一〇銭といった購入代金、遊び続けると盤面がすり減りラインが消えるので、それを塗り替えた年まで記された盤が現役で使われていたりする。
一九八八年八月二八日、「第一回カロム日本選手権大会」が開催された。子どもから老人までが同じ盤上で対等に競える大会は、デジタルゲームでは味わえない感動があった。各町内からは腕に覚えのある大人たち、自称「名人」が名乗りをあげ、間違いなく日本最高水準の大会だった。以来、大会は年に一度開かれ、今では老人会、小学校、自治会などでも、カロムが我がまちの遊びとして再び脚光をあびている。
近年、彦根カロムは全国に知れ渡るようになった。それによって彦根の人びとは、自分たちの日常の遊びが、じつはこの地域固有のものであることを知った。これに一番驚いたのは、彦根の人びとだったかもしれない。
中国の都市化と泥んこ遊び
高 茜
正月休み、雲南省昆明市に里帰りした。久しぶりに家族と過ごす時間が嬉しく、姪たちの遊びにもずっとつきあった。
ある日、兄の車で、家から一時間半ほどかかる公園へ出かけた。一人一〇元(約一三〇円)の入園料を払って公園に入ると、園内の一ヵ所に泥んこ遊び場があった。そこでは子どもの多くが親と一緒に泥んこ遊びを楽しんでいたが、遊び相手のいない子どもには公園の指導員たちが遊び方を教えていた。指導員は子どもの安全を守り、洋服を汚さない遊び方や手洗いの指導までしているのだ。
この泥んこ遊び場は半年前にできたばかりだが、とても人気があるという。わたしが子どものころ、泥んこ遊びは洋服が汚れるので親から禁じられていた。こっそり楽しんでいた泥んこ遊びが、今では子どもの遊びとして認められるようになったのかと微笑ましく思った。でも、かつての泥んこ遊びと、今のそれとでは多くの違いがある。まず、遊びが子どもたちだけで楽しむものから大人が一緒に加わるものに変わった。子どもが自発的に遊ぶ能力は育つのだろうかと少し心配だ。遊びをとおして形成される子どもたちの心もこれから大きく変わっていくのではないか。
中国には、経済発展と都市化が進む昆明市のような街が多く存在する。そのような大都会では子どもの遊びも変わりつつある。子どもの遊び場や遊び方の移り変わりに、中国社会の急速な変化を垣間見た気がした。
ある日、兄の車で、家から一時間半ほどかかる公園へ出かけた。一人一〇元(約一三〇円)の入園料を払って公園に入ると、園内の一ヵ所に泥んこ遊び場があった。そこでは子どもの多くが親と一緒に泥んこ遊びを楽しんでいたが、遊び相手のいない子どもには公園の指導員たちが遊び方を教えていた。指導員は子どもの安全を守り、洋服を汚さない遊び方や手洗いの指導までしているのだ。
この泥んこ遊び場は半年前にできたばかりだが、とても人気があるという。わたしが子どものころ、泥んこ遊びは洋服が汚れるので親から禁じられていた。こっそり楽しんでいた泥んこ遊びが、今では子どもの遊びとして認められるようになったのかと微笑ましく思った。でも、かつての泥んこ遊びと、今のそれとでは多くの違いがある。まず、遊びが子どもたちだけで楽しむものから大人が一緒に加わるものに変わった。子どもが自発的に遊ぶ能力は育つのだろうかと少し心配だ。遊びをとおして形成される子どもたちの心もこれから大きく変わっていくのではないか。
中国には、経済発展と都市化が進む昆明市のような街が多く存在する。そのような大都会では子どもの遊びも変わりつつある。子どもの遊び場や遊び方の移り変わりに、中国社会の急速な変化を垣間見た気がした。
トルコのカフヴェに集まって
キャーミル・トプラマオール
トルコ人男性の関心事といえば家族のことはもちろんだが、やはり政治とサッカーが一、二を競う。二人の男が会えば挨拶後、まず週末のサッカーの試合の結果や首相の会見などの話になる。そんな男たちがよく集まる店がカフヴェである。カフヴェとは元々コーヒーという意味だ。だが、ふつうカフヴェに行けばコーヒーではなく、煮出して作るトルコ紅茶、チャイを飲む。五、六杯飲むこともめずらしくはない。チャイを飲んだらお金を払うのは当たり前。そこでその支払いをかけてトランプやバックギャモン、そしてトルコ式の麻雀「オケイ(Okey)」が始まる。
オケイは、一から一三まで記された赤、黒、青、黄色のこま(牌)各二組と二枚のジョーカー的なこま、全一〇六枚のこまで遊ぶ麻雀に似たゲームだ。四人で遊び、向かい合った人同士がチームを組む。こまの並べ方の制限は少ない。同じ色で連番であれば何枚でもつなげてよく、色違いの同じ数を四枚すべて集めてもよい。ただし、捨てられたこまを取れるのは、次の順番の人だけになる。オケイとは、最初に開示するひとつのこま(ギョステルゲ)と同色で、それに一を足した数のこまのことを指し、ラッキーカードのような働きをする。
そのようなゲームも、週末にテレビでサッカー中継が始まるや否や中断される。みながテレビに釘づけとなり、応援もまるでスタジアムにいるかのように激しい。ライバルのサポーター同士で野次が飛び交うほどだ。場合によっては喧嘩も辞さないが、当然次回から入店禁止となる。だから必然的に同じチームのサポーターが同じカフヴェで観戦することが多い。誤ってライバルチーム・カラーのマフラーをまいたままでの入店にはご用心!
オケイは、一から一三まで記された赤、黒、青、黄色のこま(牌)各二組と二枚のジョーカー的なこま、全一〇六枚のこまで遊ぶ麻雀に似たゲームだ。四人で遊び、向かい合った人同士がチームを組む。こまの並べ方の制限は少ない。同じ色で連番であれば何枚でもつなげてよく、色違いの同じ数を四枚すべて集めてもよい。ただし、捨てられたこまを取れるのは、次の順番の人だけになる。オケイとは、最初に開示するひとつのこま(ギョステルゲ)と同色で、それに一を足した数のこまのことを指し、ラッキーカードのような働きをする。
そのようなゲームも、週末にテレビでサッカー中継が始まるや否や中断される。みながテレビに釘づけとなり、応援もまるでスタジアムにいるかのように激しい。ライバルのサポーター同士で野次が飛び交うほどだ。場合によっては喧嘩も辞さないが、当然次回から入店禁止となる。だから必然的に同じチームのサポーターが同じカフヴェで観戦することが多い。誤ってライバルチーム・カラーのマフラーをまいたままでの入店にはご用心!
展示室―情報の行き交う場
布谷 知夫
情報が世のなかに溢(あふ)れ、教育の場としての
存在意義が薄れつつある博物館の展示室。
では、これからの展示室の役割とはどういうものか。
どうすれば人が集まり、メッセージを
伝えることができるのか。
滋賀県にある琵琶湖博物館の取り組みのなかに、
その答えのひとつを探してみよう。
存在意義が薄れつつある博物館の展示室。
では、これからの展示室の役割とはどういうものか。
どうすれば人が集まり、メッセージを
伝えることができるのか。
滋賀県にある琵琶湖博物館の取り組みのなかに、
その答えのひとつを探してみよう。
琵琶湖博物館の展示室には展示交流員とよばれるスタッフがいる。彼らは来館者の話を聞きながら、必要な説明をおこない、その結果を日報に書き、また面白かった話もノートに記録している。こうして展示室で起こっているいろいろな交流についての情報が蓄積されてきた。
そうした情報のひとつに、もう経験者はいないだろうと情報収集をほとんどあきらめていた戦前の丸子船という琵琶湖の和船に関するものがあった。その船頭さんが展示室にあらわれて交流員さんに昔の航海の話をしてくれたのだ。また、昭和四〇年代の暮らしを再現した民家の展示では、多くの方から当時の暮らしの様子を具体的に教えてもらうなど、たくさんの情報が集まってきている。
博物館にとっては新しい情報が伝えられるだけではない。それらの記録のなかには、民家での暮らしの話に関連して子育ての話になり、相手の若いお母さんから子どもの食事と虫歯の相談を受け、その交流員の前職の知識から相談に乗ってあげたとか、その民家を見て、お姑さんからいじめられたのを思い出すのでとてもこの展示には近づけない、と昔の話をされた、というような余録のあるものもある。こんな話を聞いていると、博物館の展示について疑問に感じるだろう。人は何を目的にして博物館に来るのか、人はどういう展示を見て楽しいと感じるのだろうか。
教育の場でなくなった展示室
もともと博物館の展示は博物館からのメッセージを来館者に伝える場である。博物館では資料を収集し、研究をして、その成果のなかからストーリーを考え、メッセージを込めて展示を作り上げてきた。博物館がメッセージを強く意識する以前には、展示室でパネルと標本を見てもらって、その内容について教育をする場であったかもしれない。けれども博物館がもっている情報を使って、展示室で教育をするというスタイルは大きく変わらざるをえなくなっている。それはテレビやインターネット、出版物による情報の多さによる。例えば世界中の自然について、あるいは自然環境の変化について、大多数の人はテレビの映像で詳細に知っている。NHKの大河ドラマにかかわって、ある時代の歴史なども詳しく解説されている。
一般的にいうと、博物館の展示室で初めて知って感動を覚えるというような経験は今やほとんどないのではないだろうか。「ああ、これがテレビでいっていたあの話か」とか「テレビで見たのと同じだ」とかいうような見方がされている。
それでも多くの方が博物館の展示室を訪れる。博物館の魅力は展示だけではないが、ここでは展示に限って考えてみよう。人が展示を見に来るのは、そこが楽しくて、わくわくする場所だからである。博物館や美術館に行こうとする人が、「さあ、今日は勉強をしよう」と思ったりはしない。自分の楽しみで、あるいは友人や家族などとの楽しい時間を過ごすために博物館に来るのである。
人が楽しいと思う展示
「楽しい展示」という言葉に対してある方からの批判を受けたことがある。博物館には戦争や差別などのもっと深刻なテーマがあると。確かにそのとおりではあるが、博物館の楽しみをわたしはエンターテインメントだけとは考えていない。自分の知らなかったことに気づき、自分について見直すことができるような刺激的な経験が楽しさであると思う。例えば現代社会で一番楽しい場所のひとつはテーマパークだといわれる。そこは誰に対しても同じ楽しみを提供するが、その楽しみは一過性のものでしかない。博物館の楽しみは、その個人個人の興味や関心に合わせて、長く続く疑問と発見につながるような楽しみである。
博物館の展示室で人が本当に楽しいと感じるのは、展示を自分が日常的に考えていることと関連づけて見ることができ、それについて考えることができたときであると思う。わたしは、そのような状態を「展示と対話し、展示を自分化することができる」と表現している。そしてそのような状態になったとき、展示を見る人は展示から教えられるのではなく、逆に展示を契機として自分が主体となり、自分の考えをまとめていくようになる。
琵琶湖博物館の「民家のくらし再現展示」では、展示物を見たことで普段は忘れていた当時の暮らしや周りの自然、家族のことなどを思い出し、その具体的なイメージを伴って、今の自分の暮らしのことなどを考える。そしてもし同伴者がいれば、その人に対して、展示物やそれに関連した個人的な思い出などを話すだろう。そういうことを思い出し、口にすることによって、さらにイメージは膨らみ、かつ固定されていく。自分の考えたことや知っていることを人に伝えることは、とても楽しいことであろう。
琵琶湖博物館のこの展示コーナーでは、高齢者の団体と学校団体などが一緒になると、高齢者は近くにいる子どもたちに展示物について説明し、みんなが展示解説者になっているという状態ができてしまうのである。
展示室は情報交流の場
琵琶湖博物館では展示室に展示交流員というスタッフを配置しており、交流員は来館者の話を聞くことを主たる仕事にしている。そして文頭に書いたようにさまざまな来館者と話をし、ときには相談に応じることも含め、来館者にとって展示室では自分が主体であり、展示は楽しいものだと感じてもらうことができると考えている。
博物館から見ると、教えるのではない展示室とは、来館者がもっている地域の情報を博物館がいただくことができる場になるということでもある。丸子船や湖上交通についての情報は琵琶湖博物館の開館時には非常に少なかったが、展示交流員が展示室や、あるいは丸子船交流デスクというコーナーで来館者から情報を集めたのだ。
以前におこなった「湖の船」という企画展示の際には、来館者からの情報だけで構成された展示コーナーを作ったことがある。展示交流員が展示室で書き込んでくれている交流ノートには、そのような情報が数多く記録されている。そして琵琶湖博物館では毎週、その週の記録のなかから一部をコピーして館内の内部の掲示板二ヵ所に貼り出し、館員が読んでその経験を共有できるようにしている。
展示をもっと大切に
博物館の展示とは、まず学芸員があるメッセージを伝えることを目的としている。しかしそのメッセージはストレートに届くとは限らない。さまざまな受け取り方がされることを前提として、何段階かのメッセージ性を準備した展示を考えなければならないだろう。そしてメッセージをどのように準備したとしても、まず人が博物館に来てくれなければ、そもそもメッセージを伝える機会すら準備できないことになる。博物館が人を迎え入れる機関である以上、博物館は楽しい場所でありたい。そして人は熱中した状態で一番よく学ぶ。
博物館の展示は一度作ると更新が難しいという事情もあって、あまり議論がされることがないかもしれない。しかし展示が博物館の顔であることは間違いがない。博物館はまず展示で評価されるものであり、博物館と利用者とのつきあいが続くかどうかも、まず展示の印象で決まってしまう。展示をもっと大事なものと考えたいと思う。
そうした情報のひとつに、もう経験者はいないだろうと情報収集をほとんどあきらめていた戦前の丸子船という琵琶湖の和船に関するものがあった。その船頭さんが展示室にあらわれて交流員さんに昔の航海の話をしてくれたのだ。また、昭和四〇年代の暮らしを再現した民家の展示では、多くの方から当時の暮らしの様子を具体的に教えてもらうなど、たくさんの情報が集まってきている。
博物館にとっては新しい情報が伝えられるだけではない。それらの記録のなかには、民家での暮らしの話に関連して子育ての話になり、相手の若いお母さんから子どもの食事と虫歯の相談を受け、その交流員の前職の知識から相談に乗ってあげたとか、その民家を見て、お姑さんからいじめられたのを思い出すのでとてもこの展示には近づけない、と昔の話をされた、というような余録のあるものもある。こんな話を聞いていると、博物館の展示について疑問に感じるだろう。人は何を目的にして博物館に来るのか、人はどういう展示を見て楽しいと感じるのだろうか。
教育の場でなくなった展示室
もともと博物館の展示は博物館からのメッセージを来館者に伝える場である。博物館では資料を収集し、研究をして、その成果のなかからストーリーを考え、メッセージを込めて展示を作り上げてきた。博物館がメッセージを強く意識する以前には、展示室でパネルと標本を見てもらって、その内容について教育をする場であったかもしれない。けれども博物館がもっている情報を使って、展示室で教育をするというスタイルは大きく変わらざるをえなくなっている。それはテレビやインターネット、出版物による情報の多さによる。例えば世界中の自然について、あるいは自然環境の変化について、大多数の人はテレビの映像で詳細に知っている。NHKの大河ドラマにかかわって、ある時代の歴史なども詳しく解説されている。
一般的にいうと、博物館の展示室で初めて知って感動を覚えるというような経験は今やほとんどないのではないだろうか。「ああ、これがテレビでいっていたあの話か」とか「テレビで見たのと同じだ」とかいうような見方がされている。
それでも多くの方が博物館の展示室を訪れる。博物館の魅力は展示だけではないが、ここでは展示に限って考えてみよう。人が展示を見に来るのは、そこが楽しくて、わくわくする場所だからである。博物館や美術館に行こうとする人が、「さあ、今日は勉強をしよう」と思ったりはしない。自分の楽しみで、あるいは友人や家族などとの楽しい時間を過ごすために博物館に来るのである。
人が楽しいと思う展示
「楽しい展示」という言葉に対してある方からの批判を受けたことがある。博物館には戦争や差別などのもっと深刻なテーマがあると。確かにそのとおりではあるが、博物館の楽しみをわたしはエンターテインメントだけとは考えていない。自分の知らなかったことに気づき、自分について見直すことができるような刺激的な経験が楽しさであると思う。例えば現代社会で一番楽しい場所のひとつはテーマパークだといわれる。そこは誰に対しても同じ楽しみを提供するが、その楽しみは一過性のものでしかない。博物館の楽しみは、その個人個人の興味や関心に合わせて、長く続く疑問と発見につながるような楽しみである。
博物館の展示室で人が本当に楽しいと感じるのは、展示を自分が日常的に考えていることと関連づけて見ることができ、それについて考えることができたときであると思う。わたしは、そのような状態を「展示と対話し、展示を自分化することができる」と表現している。そしてそのような状態になったとき、展示を見る人は展示から教えられるのではなく、逆に展示を契機として自分が主体となり、自分の考えをまとめていくようになる。
琵琶湖博物館の「民家のくらし再現展示」では、展示物を見たことで普段は忘れていた当時の暮らしや周りの自然、家族のことなどを思い出し、その具体的なイメージを伴って、今の自分の暮らしのことなどを考える。そしてもし同伴者がいれば、その人に対して、展示物やそれに関連した個人的な思い出などを話すだろう。そういうことを思い出し、口にすることによって、さらにイメージは膨らみ、かつ固定されていく。自分の考えたことや知っていることを人に伝えることは、とても楽しいことであろう。
琵琶湖博物館のこの展示コーナーでは、高齢者の団体と学校団体などが一緒になると、高齢者は近くにいる子どもたちに展示物について説明し、みんなが展示解説者になっているという状態ができてしまうのである。
展示室は情報交流の場
琵琶湖博物館では展示室に展示交流員というスタッフを配置しており、交流員は来館者の話を聞くことを主たる仕事にしている。そして文頭に書いたようにさまざまな来館者と話をし、ときには相談に応じることも含め、来館者にとって展示室では自分が主体であり、展示は楽しいものだと感じてもらうことができると考えている。
博物館から見ると、教えるのではない展示室とは、来館者がもっている地域の情報を博物館がいただくことができる場になるということでもある。丸子船や湖上交通についての情報は琵琶湖博物館の開館時には非常に少なかったが、展示交流員が展示室や、あるいは丸子船交流デスクというコーナーで来館者から情報を集めたのだ。
以前におこなった「湖の船」という企画展示の際には、来館者からの情報だけで構成された展示コーナーを作ったことがある。展示交流員が展示室で書き込んでくれている交流ノートには、そのような情報が数多く記録されている。そして琵琶湖博物館では毎週、その週の記録のなかから一部をコピーして館内の内部の掲示板二ヵ所に貼り出し、館員が読んでその経験を共有できるようにしている。
展示をもっと大切に
博物館の展示とは、まず学芸員があるメッセージを伝えることを目的としている。しかしそのメッセージはストレートに届くとは限らない。さまざまな受け取り方がされることを前提として、何段階かのメッセージ性を準備した展示を考えなければならないだろう。そしてメッセージをどのように準備したとしても、まず人が博物館に来てくれなければ、そもそもメッセージを伝える機会すら準備できないことになる。博物館が人を迎え入れる機関である以上、博物館は楽しい場所でありたい。そして人は熱中した状態で一番よく学ぶ。
博物館の展示は一度作ると更新が難しいという事情もあって、あまり議論がされることがないかもしれない。しかし展示が博物館の顔であることは間違いがない。博物館はまず展示で評価されるものであり、博物館と利用者とのつきあいが続くかどうかも、まず展示の印象で決まってしまう。展示をもっと大事なものと考えたいと思う。
4000年をつらぬくインドのチェス 製作地/ラージャスターン州 標本番号H92921
小西正捷
零(ゼロ)の発見と並んで、チェスは世界に対するインドの貢献、という人もいる。紀元前二〇〇〇年以前にさかのぼるインダス文明期の遺物にはすでに、チェス用かと思われる格子目の付いた煉瓦製の厚い方形盤が、陶製あるいは貴石製の駒とともにモエンジョ=ダロやハラッパーなどの遺跡に出土している。ロータル出土のものには動物や山車の形をして底部が平らなものがあって興味深い。
のちのチェスの駒に王ラージャ(今日の西洋チェスのキング)・司令官マントリー(クイーン)、象ハスティン(ビショップ)・馬アシュヴァ(ナイト)・戦車ラタ(ルーク)・歩兵パダーティ(ポーン)の区別が生じる最古の例とも考えられるが、当時のルールの詳細はわからない。ただし文献上、その具体的な展開をたどることはできる。
すなわち古くは、カウティリヤ(前四―三世紀)の『実利論』をはじめ、仏典などにもチェスのことが、その遊び方を含め、やや詳細に出てくる。それによると当時のチェスは向き合った四人で遊ぶものであったらしい。各陣地が異なった色をもつ「四方陣」からこのゲームはチャトゥランガとよばれ、それがのちの六世紀ごろにペルシアに伝わってシャトランジとよばれるようになる。さらにはアラビアやビザンティン世界を経て、ヨーロッパへは九、一〇世紀に伝わった。
そのルールが現在のようにほぼ固まったのは一五世紀のことで、インドでは以降、ムスリムの王侯貴族のあいだでもっとも人気のあるゲームとなった。西洋でもチェスは、一八世紀には貴族層のみならず一般市民のあいだにも広がり、今では世界チャンピオンシップまであるが、残念ながらインドの成績は、昨今どうも振るわない。
のちのチェスの駒に王ラージャ(今日の西洋チェスのキング)・司令官マントリー(クイーン)、象ハスティン(ビショップ)・馬アシュヴァ(ナイト)・戦車ラタ(ルーク)・歩兵パダーティ(ポーン)の区別が生じる最古の例とも考えられるが、当時のルールの詳細はわからない。ただし文献上、その具体的な展開をたどることはできる。
すなわち古くは、カウティリヤ(前四―三世紀)の『実利論』をはじめ、仏典などにもチェスのことが、その遊び方を含め、やや詳細に出てくる。それによると当時のチェスは向き合った四人で遊ぶものであったらしい。各陣地が異なった色をもつ「四方陣」からこのゲームはチャトゥランガとよばれ、それがのちの六世紀ごろにペルシアに伝わってシャトランジとよばれるようになる。さらにはアラビアやビザンティン世界を経て、ヨーロッパへは九、一〇世紀に伝わった。
そのルールが現在のようにほぼ固まったのは一五世紀のことで、インドでは以降、ムスリムの王侯貴族のあいだでもっとも人気のあるゲームとなった。西洋でもチェスは、一八世紀には貴族層のみならず一般市民のあいだにも広がり、今では世界チャンピオンシップまであるが、残念ながらインドの成績は、昨今どうも振るわない。
友の会とミュージアム・ショップからのご案内
チェルノヴィッツのラビ
赤尾 光春
ヘブライ語の祝福
二〇〇一年の夏、イスラエルのイディッシュ文化公社が主催する、ウクライナの旧ユダヤ人史跡めぐりに同行した。目的地のひとつにルーマニア国境付近の町チェルノヴィッツ(現チェルニウツィ)があった。オスマントルコ帝国、オーストリア・ハンガリー帝国、ルーマニア、そしてソ連の支配下にあった典型的な多言語・多文化都市である。独ソ戦前夜には町の人口の半数近くをユダヤ人が占めていたが、最近の統計では、町全体の人口約二三万六〇〇〇人のうちユダヤ人はわずかに一三〇〇人(〇・六パーセント)を残すのみである。
われわれは、この町にただひとつ残る古色蒼然としたユダヤ教会堂を訪れた。ちょうど安息日で、祈祷に必要な男性一〇人をどうにかこうにかかき集めたといった様子だった。黒装束の立派なラビ(律法学者)が厳かに祈祷をとり仕切っていた。ところが一行のイスラエル人たちはといえば、祈る人びとには目もくれず、聖書のモチーフが描かれた天井画に感嘆の声を上げるなり、思い思いにシャッターを切り始めた。たまりかねたラビは祈祷を中断し、「あなたがたの国ではそういうことが許されるかもしれないが、わたしたちは今、安息日の祈りの最中なのです」とたしなめた。
建物から出ると、色とりどりのスカーフを被った女性が数人、正門のそばのベンチに所在なげに腰掛けているのが目にとまった。聞けば、彼女らはユダヤ人ではないが、祈祷が終わるのをただひたすら待っていると言う。その光景をどうしても忘れることができず、翌朝、わたしは一人で会堂を訪れることに決めた。
女性たちはやはり同じ場所にいて、人数も一〇人ほどに増えていた。扉から一人また一人と、スカーフ姿の女性たちがあらわれては去って行く。わたしは女性たちを呼びとめて、話を聞いてみた。それでわかったことには、彼女らはみな地元のキリスト教徒で、毎朝のように熱心にラビのもとを訪れ、お布施をする見返りに、ヘブライ語の祝福を受けていると言う。無病息災や家内安全などがおもな願い事だが、なかには合格祈願に来る学生までいるそうだ。キリスト教徒がなぜユダヤ人のところへ来るのか、神父の祝福は十分ではないのかなどと問うても、「神さまはただ一人。キリスト教もユダヤ教も区別はない」と一向にとり合わない。そうかと思えば、「キリスト教徒よりもユダヤ人の方が熱心にお祈りするから、効き目はずっと大きいの」と自信たっぷりに答える者もいた。
キリスト教徒のユダヤ人信仰
かつてウクライナでは農村部を中心に、レベとよばれるハシディズム(一八世紀半ば、東欧で誕生したユダヤ教敬虔主義運動)の精神的導師たちが、ユダヤ人のみならずキリスト教徒からの信仰も集めていたことが知られている。ユダヤ人といえば、中世から近世にかけてのキリスト教世界では、邪悪で不浄な存在として一方的に差別され、迫害されてきたものと理解されているが、ごく稀に、福をもたらす存在として重宝されていたという意外な側面も確認されている。とはいえ、ユダヤ人がめっきり少なくなった二一世紀初頭のウクライナで、まったく同じ現象をこの目で確かめようとは夢にも思っていなかった。
エルサレムに戻って、チェルノヴィッツ出身の教授にこの話をしたところ、教授は微笑を浮かべてこうつけ加えた。ソ連時代に無神論者の技師がいた。ユダヤ教の知識はとんともち合わせていなかったが、ペレストロイカで一念発起し、イスラエルでユダヤ教のいろはをにわかに仕込み、黒装束に身を包んで生まれ故郷に帰ってきた。
町でたった一人のラビはこうして誕生したというわけである。
二〇〇一年の夏、イスラエルのイディッシュ文化公社が主催する、ウクライナの旧ユダヤ人史跡めぐりに同行した。目的地のひとつにルーマニア国境付近の町チェルノヴィッツ(現チェルニウツィ)があった。オスマントルコ帝国、オーストリア・ハンガリー帝国、ルーマニア、そしてソ連の支配下にあった典型的な多言語・多文化都市である。独ソ戦前夜には町の人口の半数近くをユダヤ人が占めていたが、最近の統計では、町全体の人口約二三万六〇〇〇人のうちユダヤ人はわずかに一三〇〇人(〇・六パーセント)を残すのみである。
われわれは、この町にただひとつ残る古色蒼然としたユダヤ教会堂を訪れた。ちょうど安息日で、祈祷に必要な男性一〇人をどうにかこうにかかき集めたといった様子だった。黒装束の立派なラビ(律法学者)が厳かに祈祷をとり仕切っていた。ところが一行のイスラエル人たちはといえば、祈る人びとには目もくれず、聖書のモチーフが描かれた天井画に感嘆の声を上げるなり、思い思いにシャッターを切り始めた。たまりかねたラビは祈祷を中断し、「あなたがたの国ではそういうことが許されるかもしれないが、わたしたちは今、安息日の祈りの最中なのです」とたしなめた。
建物から出ると、色とりどりのスカーフを被った女性が数人、正門のそばのベンチに所在なげに腰掛けているのが目にとまった。聞けば、彼女らはユダヤ人ではないが、祈祷が終わるのをただひたすら待っていると言う。その光景をどうしても忘れることができず、翌朝、わたしは一人で会堂を訪れることに決めた。
女性たちはやはり同じ場所にいて、人数も一〇人ほどに増えていた。扉から一人また一人と、スカーフ姿の女性たちがあらわれては去って行く。わたしは女性たちを呼びとめて、話を聞いてみた。それでわかったことには、彼女らはみな地元のキリスト教徒で、毎朝のように熱心にラビのもとを訪れ、お布施をする見返りに、ヘブライ語の祝福を受けていると言う。無病息災や家内安全などがおもな願い事だが、なかには合格祈願に来る学生までいるそうだ。キリスト教徒がなぜユダヤ人のところへ来るのか、神父の祝福は十分ではないのかなどと問うても、「神さまはただ一人。キリスト教もユダヤ教も区別はない」と一向にとり合わない。そうかと思えば、「キリスト教徒よりもユダヤ人の方が熱心にお祈りするから、効き目はずっと大きいの」と自信たっぷりに答える者もいた。
キリスト教徒のユダヤ人信仰
かつてウクライナでは農村部を中心に、レベとよばれるハシディズム(一八世紀半ば、東欧で誕生したユダヤ教敬虔主義運動)の精神的導師たちが、ユダヤ人のみならずキリスト教徒からの信仰も集めていたことが知られている。ユダヤ人といえば、中世から近世にかけてのキリスト教世界では、邪悪で不浄な存在として一方的に差別され、迫害されてきたものと理解されているが、ごく稀に、福をもたらす存在として重宝されていたという意外な側面も確認されている。とはいえ、ユダヤ人がめっきり少なくなった二一世紀初頭のウクライナで、まったく同じ現象をこの目で確かめようとは夢にも思っていなかった。
エルサレムに戻って、チェルノヴィッツ出身の教授にこの話をしたところ、教授は微笑を浮かべてこうつけ加えた。ソ連時代に無神論者の技師がいた。ユダヤ教の知識はとんともち合わせていなかったが、ペレストロイカで一念発起し、イスラエルでユダヤ教のいろはをにわかに仕込み、黒装束に身を包んで生まれ故郷に帰ってきた。
町でたった一人のラビはこうして誕生したというわけである。
テレビ番組のなかのヴァヌアツ
知られざる国
わたしのフィールドは南太平洋の島国ヴァヌアツである。東隣にフィジー、南西隣にニューカレドニアがあるのだが、これら観光地として有名な国々に比べると、日本でヴァヌアツの知名度はかなり低い。ヴァヌアツをフィールドにしていると言うと、「アフリカにある国でしょ?」などと聞かれることもある。ボツワナと間違えられているらしい・・・。
そんなヴァヌアツだが、それでも最近テレビ番組などで少しずつとり上げられるようになってきている。わたしの知るかぎりでは、最初にまとまった形でヴァヌアツをとり上げた番組は一九七九年に放送されている。ペンテコストという島の人びとがおこなっているヤムイモの収穫儀礼を紹介したものである。バンジージャンプの原型と言えばすぐにイメージできるかもしれないが、この儀礼では高さ数十メートルの木製のやぐらから、足首に蔓性植物のロープを結びつけた男たちが次々に頭からダイブしてゆく。そんな勇壮な内容であることもあって、儀礼は早くから観光客の関心を引き、番組で紹介された一九七九年頃にはすでに観光客向けのツアーが組まれるようになっていた。
日本で広まったイメージ
さて、それから今までにヴァヌアツをとり上げたテレビ番組はどれくらい放送されているのだろうか。二〇〇〇年までを調べてみたところ、先の番組を含めて少なくとも一六件の番組があった。このうち一二件は一九九〇年代から二〇〇〇年にかけて放送されたものであり、ヴァヌアツをとり上げた番組が最近になって増えていることがわかる。ボツワナとヴァヌアツを混同してほしくないわたしにとって、こうした傾向は嬉しくもあるのだが、その一方で素直に喜べない部分もある。というのも、番組でとり上げられる地域がいつも決まって地方の村であり、登場する人びとはペニスサックや腰蓑という出で立ちであるからだ。実際そのような姿で生活している人びともいるのだが、ヴァヌアツの人びとの大半はTシャツやズボン、ワンピースなどで暮らしている。また、ペニスサックなどを身につけた人びとも、自分たちの伝統を守るという考え方に基づき、あえてそうした姿をしていることが多い。
ヴァヌアツ関連番組が増えてきたとはいえ、まだまだ少ない。それだけに前述のような説明がないまま、伝統的な衣装の村人たちをとり上げた番組だけが放送され続けると、視聴者のあいだに偏ったイメージができてしまうのではないかと心配である。そんなイメージを定着させないためには、たとえば都市で生活するヴァヌアツの人びとに目を向けたり(小さいながらもとても美しい街がヴァヌアツにはある)、ヴァヌアツの人びと自身が制作した自分たちの生活や文化に関する番組(もちろんヴァヌアツにもテレビ局はある)を紹介したりすることが、どこかで必要となってくるのではないだろうか。
わたしのフィールドは南太平洋の島国ヴァヌアツである。東隣にフィジー、南西隣にニューカレドニアがあるのだが、これら観光地として有名な国々に比べると、日本でヴァヌアツの知名度はかなり低い。ヴァヌアツをフィールドにしていると言うと、「アフリカにある国でしょ?」などと聞かれることもある。ボツワナと間違えられているらしい・・・。
そんなヴァヌアツだが、それでも最近テレビ番組などで少しずつとり上げられるようになってきている。わたしの知るかぎりでは、最初にまとまった形でヴァヌアツをとり上げた番組は一九七九年に放送されている。ペンテコストという島の人びとがおこなっているヤムイモの収穫儀礼を紹介したものである。バンジージャンプの原型と言えばすぐにイメージできるかもしれないが、この儀礼では高さ数十メートルの木製のやぐらから、足首に蔓性植物のロープを結びつけた男たちが次々に頭からダイブしてゆく。そんな勇壮な内容であることもあって、儀礼は早くから観光客の関心を引き、番組で紹介された一九七九年頃にはすでに観光客向けのツアーが組まれるようになっていた。
日本で広まったイメージ
さて、それから今までにヴァヌアツをとり上げたテレビ番組はどれくらい放送されているのだろうか。二〇〇〇年までを調べてみたところ、先の番組を含めて少なくとも一六件の番組があった。このうち一二件は一九九〇年代から二〇〇〇年にかけて放送されたものであり、ヴァヌアツをとり上げた番組が最近になって増えていることがわかる。ボツワナとヴァヌアツを混同してほしくないわたしにとって、こうした傾向は嬉しくもあるのだが、その一方で素直に喜べない部分もある。というのも、番組でとり上げられる地域がいつも決まって地方の村であり、登場する人びとはペニスサックや腰蓑という出で立ちであるからだ。実際そのような姿で生活している人びともいるのだが、ヴァヌアツの人びとの大半はTシャツやズボン、ワンピースなどで暮らしている。また、ペニスサックなどを身につけた人びとも、自分たちの伝統を守るという考え方に基づき、あえてそうした姿をしていることが多い。
ヴァヌアツ関連番組が増えてきたとはいえ、まだまだ少ない。それだけに前述のような説明がないまま、伝統的な衣装の村人たちをとり上げた番組だけが放送され続けると、視聴者のあいだに偏ったイメージができてしまうのではないかと心配である。そんなイメージを定着させないためには、たとえば都市で生活するヴァヌアツの人びとに目を向けたり(小さいながらもとても美しい街がヴァヌアツにはある)、ヴァヌアツの人びと自身が制作した自分たちの生活や文化に関する番組(もちろんヴァヌアツにもテレビ局はある)を紹介したりすることが、どこかで必要となってくるのではないだろうか。
国勢調査と二人の外国人
アンジェロ・イシ
国勢調査の広告
有名か無名かを問わず、日本のテレビCMや活字媒体の広告で「外国人」の姿を見かけることはもはや、めずらしいことではなくなった。しかし、昨年、日本政府が電車のなかや各種メディアで大々的に展開した国勢調査の広告は、この国における外国籍住民の位置付けを考えるうえで示唆に富んでいた。
この広告では、「10月1日は、国勢調査。」という文字に重なる形で、三人のタレントが「国民の代表者」として登場した。その三人の写真の下には、「日本に住む一人ひとりが、この国の明日を担ってる。」というフレーズが綴られていた。さらにその下には、より小さな文字で次のように書かれていた。「日本に住むすべての人が対象となる国勢調査。5年に一度行われる、いまの日本を知るうえで大切なこの調査にみなさんのご理解とご協力をよろしくお願いします。」
まず、この広告で目を引くのは、前述の宣伝文句がすべて英語でも書かれていることである。そこには、日本語が読めない人びとにもこの広告を理解してもらいたい、すなわち国勢調査について周知徹底したいという強い意志が垣間見られる。そしてその意図がより明確にあらわれているのが三人のタレントのキャスティングである。一人はドラマ出演など多方面から引っ張りだこの上戸彩、もう一人は映画「踊る大捜査線」などで知られる北村総一朗、そして三人目は米国出身のダニエル・カールである。テレビで放映されたため、おそらく覚えている方もいるだろう。
表面的な解釈を試みるならば、上戸は女性および若い世代の代表として、北村は男性および「上の世代」の代表として、そしてカールは在日外国人の代表として起用されていると思われる。しかし、すべての広告がそうであるように、この広告も多くの深読みを可能にしている。たとえば、なぜ日本人二人は洋服の普段着姿なのに、カールは帯を締めた和服姿なのか?なぜ外国人の代表として、(在日コリアンでも日系ブラジル人でもなく)よりによって白人系の米国人が選ばれたのか?在日外国人の数が全人口の二%にも満たないのに、なぜ広告の三分の一が外国人(あるいは外国人に接している日本人)をターゲットにしているのか?
ここでこれらの問題をひとつひとつ考察する余裕はないし、この広告の意義に疑問を投げかけるつもりもない。むしろ、政府が外国籍住民に関する情報収集に余念がないことを裏付ける重要な証拠として、この広告をとらえてよかろう。他国でもこれは同様である。同広告の一番下の部分には、英語で「外国籍住民のために、19の異なる言語のアンケートを用意しました」と書かれている。ではその多言語話者(外国籍住民)の情報はいかなる形で生かされるのだろうか?答えは同広告の文中に、日本語のみで明記されている。「人口の転換期を迎えつつある日本の21世紀最初の国勢調査です。」「小子高齢化への取組やみなさんの街づくりにいかされます。」
よくも悪くも、「外国人」としてくくられる人びとが、確実に日本社会の一員として認められ、無視できない存在になっていることを、この広告は物語っている-そう書きたいところだが、果たしてそうだろうか?
調査する側へ
じつは筆者は日本で発行されるポルトガル語のフリーペーパー Alternativaでコラムを書いているのだが、読者の一人から、国勢調査にまつわる苦い体験談を綴った長いメールが届いた。彼女は三重県のとある市役所で通訳として働いているバイリンガルの日系ブラジル人なのだが、国勢調査員に任命され、調査票の配布のため、ある団地を訪れた。自分は日本語がたどたどしいため、果たして日本人住民が快く応対してくれるかどうか、不安でいっぱいだったと言う。案の定、数名の住民は彼女の配布の手順に不備があったとして、罵声(ばせい)を浴びせた。彼女は反論もできず、ただ悔し涙を流したそうだ。彼女からのメールは次のような悲痛な言葉で締めくくられていた。「私は日本に永住する決心で家まで買ったのに、こんなにつらい思いをしてしまい、今は後悔しています。」
どう慰めればいいのか迷っていたところ、翌日、彼女から再びメールが届いた。「私は今日、調査員の任務を辞退する決心で市役所に出かけました。ところが、担当者に私の事情を説明したところ、彼は私に幾度も頭を下げお詫びを言って、私に調査の手順をきちんと説明しなかった職員を呼び出して叱りました。これで私もやる気を取り戻して、国勢調査で頑張ることにしました。」
日本語を母国語としない彼女にとって、調査員という任務は想像以上のプレッシャーを伴ったに違いない。しかし、外国人が調査を受けるだけでは、真の意味で「この国の明日を担う」ことにはならない。彼女の場合のように、調査をする側にも当たり前のように外国人がいてこそ、そして欲をいえばそのデータを分析し活用する過程でも外国籍住民を起用してこそ、誰にでも住みよい日本社会の実現に近づけるのかもしれない。
有名か無名かを問わず、日本のテレビCMや活字媒体の広告で「外国人」の姿を見かけることはもはや、めずらしいことではなくなった。しかし、昨年、日本政府が電車のなかや各種メディアで大々的に展開した国勢調査の広告は、この国における外国籍住民の位置付けを考えるうえで示唆に富んでいた。
この広告では、「10月1日は、国勢調査。」という文字に重なる形で、三人のタレントが「国民の代表者」として登場した。その三人の写真の下には、「日本に住む一人ひとりが、この国の明日を担ってる。」というフレーズが綴られていた。さらにその下には、より小さな文字で次のように書かれていた。「日本に住むすべての人が対象となる国勢調査。5年に一度行われる、いまの日本を知るうえで大切なこの調査にみなさんのご理解とご協力をよろしくお願いします。」
まず、この広告で目を引くのは、前述の宣伝文句がすべて英語でも書かれていることである。そこには、日本語が読めない人びとにもこの広告を理解してもらいたい、すなわち国勢調査について周知徹底したいという強い意志が垣間見られる。そしてその意図がより明確にあらわれているのが三人のタレントのキャスティングである。一人はドラマ出演など多方面から引っ張りだこの上戸彩、もう一人は映画「踊る大捜査線」などで知られる北村総一朗、そして三人目は米国出身のダニエル・カールである。テレビで放映されたため、おそらく覚えている方もいるだろう。
表面的な解釈を試みるならば、上戸は女性および若い世代の代表として、北村は男性および「上の世代」の代表として、そしてカールは在日外国人の代表として起用されていると思われる。しかし、すべての広告がそうであるように、この広告も多くの深読みを可能にしている。たとえば、なぜ日本人二人は洋服の普段着姿なのに、カールは帯を締めた和服姿なのか?なぜ外国人の代表として、(在日コリアンでも日系ブラジル人でもなく)よりによって白人系の米国人が選ばれたのか?在日外国人の数が全人口の二%にも満たないのに、なぜ広告の三分の一が外国人(あるいは外国人に接している日本人)をターゲットにしているのか?
ここでこれらの問題をひとつひとつ考察する余裕はないし、この広告の意義に疑問を投げかけるつもりもない。むしろ、政府が外国籍住民に関する情報収集に余念がないことを裏付ける重要な証拠として、この広告をとらえてよかろう。他国でもこれは同様である。同広告の一番下の部分には、英語で「外国籍住民のために、19の異なる言語のアンケートを用意しました」と書かれている。ではその多言語話者(外国籍住民)の情報はいかなる形で生かされるのだろうか?答えは同広告の文中に、日本語のみで明記されている。「人口の転換期を迎えつつある日本の21世紀最初の国勢調査です。」「小子高齢化への取組やみなさんの街づくりにいかされます。」
よくも悪くも、「外国人」としてくくられる人びとが、確実に日本社会の一員として認められ、無視できない存在になっていることを、この広告は物語っている-そう書きたいところだが、果たしてそうだろうか?
調査する側へ
じつは筆者は日本で発行されるポルトガル語のフリーペーパー Alternativaでコラムを書いているのだが、読者の一人から、国勢調査にまつわる苦い体験談を綴った長いメールが届いた。彼女は三重県のとある市役所で通訳として働いているバイリンガルの日系ブラジル人なのだが、国勢調査員に任命され、調査票の配布のため、ある団地を訪れた。自分は日本語がたどたどしいため、果たして日本人住民が快く応対してくれるかどうか、不安でいっぱいだったと言う。案の定、数名の住民は彼女の配布の手順に不備があったとして、罵声(ばせい)を浴びせた。彼女は反論もできず、ただ悔し涙を流したそうだ。彼女からのメールは次のような悲痛な言葉で締めくくられていた。「私は日本に永住する決心で家まで買ったのに、こんなにつらい思いをしてしまい、今は後悔しています。」
どう慰めればいいのか迷っていたところ、翌日、彼女から再びメールが届いた。「私は今日、調査員の任務を辞退する決心で市役所に出かけました。ところが、担当者に私の事情を説明したところ、彼は私に幾度も頭を下げお詫びを言って、私に調査の手順をきちんと説明しなかった職員を呼び出して叱りました。これで私もやる気を取り戻して、国勢調査で頑張ることにしました。」
日本語を母国語としない彼女にとって、調査員という任務は想像以上のプレッシャーを伴ったに違いない。しかし、外国人が調査を受けるだけでは、真の意味で「この国の明日を担う」ことにはならない。彼女の場合のように、調査をする側にも当たり前のように外国人がいてこそ、そして欲をいえばそのデータを分析し活用する過程でも外国籍住民を起用してこそ、誰にでも住みよい日本社会の実現に近づけるのかもしれない。
ジョージ・ブラウン・コレクションその価値が輝くとき
売り出された南太平洋の文化遺産
わたしは一九七五年に民博助手に採用され、その年に早くも資料収集のために南太平洋に派遣された。その際にミクロネシアのマーシャル諸島で収集をおこなったが、小船に乗って離島を目指していたときに嵐に遭遇し、危うく命をおとしかけた経験がある。
一〇年後の一九八五年に英国で南太平洋資料の収集をおこなうという得難い経験をした。南太平洋地域の民族資料について、民博は大きな問題を抱えていた。それはメラネシア地域の民族資料が極端に少ないことであった。そのような悩みを抱えるなかで、一九八五年に突然、得難い話が舞い込んできた。それは英国からの話で、ニューキャスル大学が所蔵するジョージ・ブラウン・コレクション(以下GBCと略す)約三〇〇〇点が売りに出されているというものだった。
ジョージ・ブラウンは、一八三五年に英国で生まれた宣教師で、一八六〇年から南太平洋の各地で布教活動をおこなうとともに、仮面や各種の生活用具など、多様な民族資料の収集をおこなった。とくに、メラネシア地域のニューブリテン島とニューアイルランド島で収集された約七〇〇点の資料は、ヨーロッパ人による民族資料収集としてはもっとも早い時期のものだ。
英国へ学術価値の調査
GBCを購入できれば、民博の南太平洋民族資料の空白部分を埋めることができるが、大きな問題があった。その価格が約二億円もしたことだ。当時の民博の標本資料収集委員会の判断は、学術資料として購入に値する貴重なコレクションであれば、購入してもよいというものだった。そこで、わたしが英国に派遣され、学術的価値を評価することになった。
英国ではニューキャスル大学の学長に会い、交渉をおこなった。学長はGBCを分散させたくないので一括購入してほしいと述べられ、資料チェックを快諾してくれた。早速、このコレクションを管理している大学附属博物館長に電話して、協力するように指示していただいた。
昼食後に博物館を訪れたところ、秘書だけしかおらず、「館長は不在なので、勝手に見てください」と言われ、収蔵庫の鍵の束を手渡された。収蔵庫の前で扉を開けようとして鍵を差し込んだが、いずれの鍵でも開かない。秘書のところに再度行き、「扉が開かない」と告げたが、「その鍵の束しかない」と言う。すぐに館長に連絡してほしいと頼んだが、連絡がつかないらしい。結局、ふたたび学長に会って、博物館の対応の悪さを抗議したところ、明朝にはかならず対応させると確約してくれた。翌日、ようやく館長に会え、GBCのチェックを周到におこなうことができた。
当時の英国ではサッチャー首相による行財政改革が強力に推進され、大学に対する政府の財政支援が大幅に削減されていた。ニューキャスル大学でも学長を中心に改革が進められており、その際に注目されたのがGBCであった。学長がサザビーズ社にその価値評価を依頼したところ、約二億四〇〇〇万円という結果になった。収蔵されているだけで、なんらの活用もなされていないために「宝の持ち腐れ」と判断されたらしい。大学理事会での売却が正式に決定され、サザビーズ社に売却の仲介が任された。
世界中で展示してこそ高まる価値
売却の決定を知った大英博物館のオセアニア地域部門の専門家が国内の研究者に呼びかけて、売却反対運動を展開した。大学附属博物館長も反対派の主要メンバーの一人であった。そのために、嫌がらせをされたわけだ。当時、日本企業が英国にかなり進出しており、経済的侵略だと批判されていた。そのうえに、英国の貴重な文化遺産の購入をもくろむのは文化的侵略だという新聞記事まで登場した。GBCをめぐって、かなりヒステリックな状況が生じていた。換言するならば、それだけ価値の高い文化遺産と評価されていたわけだ。
結論的にいうと、さまざまな経緯の後、一九八六年に民博が購入した。英国での反対運動などで手間取っているうちに、ポンド下落と円高によって、最終的な購入価格は約一億四〇〇〇万円になり、民博は約六〇〇〇万円ほど得をした。
民博は一九九九年に「南太平洋の文化遺産」と題する企画展を開催し、GBCの展示をおこなった。わたしは企画展の実行委員会委員長を務めた。その開会式典の際に、パプアニューギニア国立博物館長とフィジー国立博物館長をお招きした。このコレクションには、両国の貴重な文化遺産が数多く含まれているので、両館長に「貴国に資料を返還した方がよいですか?」と尋ねた。すると、二人とも即座に「その必要はない。一括して民博で所蔵されるべきだ」とおっしゃった。
民博所蔵のコレクションとして、各国の研究者に注目されており、他の博物館への貸し出しの機会も増えている。おおいに共同利用していただくことは民博の使命に合致するし、GBCにとっても幸せである。
わたしは一九七五年に民博助手に採用され、その年に早くも資料収集のために南太平洋に派遣された。その際にミクロネシアのマーシャル諸島で収集をおこなったが、小船に乗って離島を目指していたときに嵐に遭遇し、危うく命をおとしかけた経験がある。
一〇年後の一九八五年に英国で南太平洋資料の収集をおこなうという得難い経験をした。南太平洋地域の民族資料について、民博は大きな問題を抱えていた。それはメラネシア地域の民族資料が極端に少ないことであった。そのような悩みを抱えるなかで、一九八五年に突然、得難い話が舞い込んできた。それは英国からの話で、ニューキャスル大学が所蔵するジョージ・ブラウン・コレクション(以下GBCと略す)約三〇〇〇点が売りに出されているというものだった。
ジョージ・ブラウンは、一八三五年に英国で生まれた宣教師で、一八六〇年から南太平洋の各地で布教活動をおこなうとともに、仮面や各種の生活用具など、多様な民族資料の収集をおこなった。とくに、メラネシア地域のニューブリテン島とニューアイルランド島で収集された約七〇〇点の資料は、ヨーロッパ人による民族資料収集としてはもっとも早い時期のものだ。
英国へ学術価値の調査
GBCを購入できれば、民博の南太平洋民族資料の空白部分を埋めることができるが、大きな問題があった。その価格が約二億円もしたことだ。当時の民博の標本資料収集委員会の判断は、学術資料として購入に値する貴重なコレクションであれば、購入してもよいというものだった。そこで、わたしが英国に派遣され、学術的価値を評価することになった。
英国ではニューキャスル大学の学長に会い、交渉をおこなった。学長はGBCを分散させたくないので一括購入してほしいと述べられ、資料チェックを快諾してくれた。早速、このコレクションを管理している大学附属博物館長に電話して、協力するように指示していただいた。
昼食後に博物館を訪れたところ、秘書だけしかおらず、「館長は不在なので、勝手に見てください」と言われ、収蔵庫の鍵の束を手渡された。収蔵庫の前で扉を開けようとして鍵を差し込んだが、いずれの鍵でも開かない。秘書のところに再度行き、「扉が開かない」と告げたが、「その鍵の束しかない」と言う。すぐに館長に連絡してほしいと頼んだが、連絡がつかないらしい。結局、ふたたび学長に会って、博物館の対応の悪さを抗議したところ、明朝にはかならず対応させると確約してくれた。翌日、ようやく館長に会え、GBCのチェックを周到におこなうことができた。
当時の英国ではサッチャー首相による行財政改革が強力に推進され、大学に対する政府の財政支援が大幅に削減されていた。ニューキャスル大学でも学長を中心に改革が進められており、その際に注目されたのがGBCであった。学長がサザビーズ社にその価値評価を依頼したところ、約二億四〇〇〇万円という結果になった。収蔵されているだけで、なんらの活用もなされていないために「宝の持ち腐れ」と判断されたらしい。大学理事会での売却が正式に決定され、サザビーズ社に売却の仲介が任された。
世界中で展示してこそ高まる価値
売却の決定を知った大英博物館のオセアニア地域部門の専門家が国内の研究者に呼びかけて、売却反対運動を展開した。大学附属博物館長も反対派の主要メンバーの一人であった。そのために、嫌がらせをされたわけだ。当時、日本企業が英国にかなり進出しており、経済的侵略だと批判されていた。そのうえに、英国の貴重な文化遺産の購入をもくろむのは文化的侵略だという新聞記事まで登場した。GBCをめぐって、かなりヒステリックな状況が生じていた。換言するならば、それだけ価値の高い文化遺産と評価されていたわけだ。
結論的にいうと、さまざまな経緯の後、一九八六年に民博が購入した。英国での反対運動などで手間取っているうちに、ポンド下落と円高によって、最終的な購入価格は約一億四〇〇〇万円になり、民博は約六〇〇〇万円ほど得をした。
民博は一九九九年に「南太平洋の文化遺産」と題する企画展を開催し、GBCの展示をおこなった。わたしは企画展の実行委員会委員長を務めた。その開会式典の際に、パプアニューギニア国立博物館長とフィジー国立博物館長をお招きした。このコレクションには、両国の貴重な文化遺産が数多く含まれているので、両館長に「貴国に資料を返還した方がよいですか?」と尋ねた。すると、二人とも即座に「その必要はない。一括して民博で所蔵されるべきだ」とおっしゃった。
民博所蔵のコレクションとして、各国の研究者に注目されており、他の博物館への貸し出しの機会も増えている。おおいに共同利用していただくことは民博の使命に合致するし、GBCにとっても幸せである。
ふるさとの味は、毒の味?
阿良田 麻里子
「猛毒のイヌホオズキ」
イヌホオズキという植物をご存じだろうか。直径一センチメートルほどの球形の実をつけるが、名前に反してホオズキのような傘はない。
子どものころの愛読書『スカラブ号の夏休み』では、おてんば娘のナンシイが、招かれざる客である大叔母の寝室に猛毒のイヌホオズキの花を飾ろうと言っていた。それ以来、実物は知らずともイヌホオズキは猛毒と信じ込んでいた。植物図鑑をひもといても確かに有毒植物と書いてある。
だから、このイヌホオズキの実が、インドネシア・西ジャワのスンダ地方でルンチャとよばれ、地元のスンダ人に食べられているものの正体だと知ったときには驚いた。ルンチャはスンダではれっきとした野菜なのである。
ルンチャとよばれる常食
お手軽な食べ方にララブというのがある。これは、キュウリやキャベツなどと同様に生野菜として、そのままサンバルとよばれるチリソースをちょいとつけて食べるものだ。少し手をかけるなら、すりつぶした甘辛い調味料にルンチャを混ぜ、軽くたたきつぶしてカレドックにする。ピーナッツや大豆の発酵食品や唐辛子と煮込み、ウルクトゥックにしてもよい。こんなに食べてもなんともないのだから、少なくとも栽培種には毒はないようだ。
しかし、ルンチャの味は、苦いようなえぐいような、なんともいいようのない妙な味である。この味わいをスンダ人はプフールという言葉であらわす。プフールな味のするものは、そう多くはない。ルンチャによく似たスズメナスビという植物の実や、出来のよくない生食用のナスぐらいである。
インドネシアでは一般にニガウリなどの苦い野菜を食べる。渋くて日本人が顔をしかめるようなものが平気な人も多い。しかし、スンダ人のようにルンチャを好む民族は他にはいない。他の地域の大きな市場でルンチャを探し求めてもまず見かけないが、スンダでは村の行商人でさえ毎日売りに来るごく普通の野菜だ。栽培も簡単で値段も安い。ある山村の調査では、頻繁に使われる食材として、米・ヤシ油・トウガラシ・トゥラシ(小エビなどで作った調味料)・マニオクというメジャーどころと肩を並べて、堂々とルンチャが登場している。わたしの調査した村も同様で、近所の家々の食卓にはしばしばルンチャがのぼっていた。都会の高級スンダ料理レストランでも、豪勢な魚や肉の料理と並んで、渋い脇役としてルンチャ料理は欠かせない。
わたしも初めはつきあい程度に仕方なく食べていたが、そのうちにおいしく感じられるようになってきた。初めてのビールはまずくても、大人になるとおいしくなるのと似ている。生のララブは噛むとぷちゅっとつぶれる感じが楽しい。ウルクトゥックには、発酵ピーナッツの旨みや風味、唐辛子の辛みと相まってえもいわれぬ複雑な味わいがあり、好物のひとつになった。日本人のわたしがルンチャを好きだと言うと、スンダ人はたいてい、あんなものが好きなのかとあきれて嬉しそうに笑う。日本人が納豆好きの外国人に会ったときのような感じである。「猛毒のイヌホオズキ」は、スンダの人びとにとって、ふるさとの味なのだ。
イヌホオズキという植物をご存じだろうか。直径一センチメートルほどの球形の実をつけるが、名前に反してホオズキのような傘はない。
子どものころの愛読書『スカラブ号の夏休み』では、おてんば娘のナンシイが、招かれざる客である大叔母の寝室に猛毒のイヌホオズキの花を飾ろうと言っていた。それ以来、実物は知らずともイヌホオズキは猛毒と信じ込んでいた。植物図鑑をひもといても確かに有毒植物と書いてある。
だから、このイヌホオズキの実が、インドネシア・西ジャワのスンダ地方でルンチャとよばれ、地元のスンダ人に食べられているものの正体だと知ったときには驚いた。ルンチャはスンダではれっきとした野菜なのである。
ルンチャとよばれる常食
お手軽な食べ方にララブというのがある。これは、キュウリやキャベツなどと同様に生野菜として、そのままサンバルとよばれるチリソースをちょいとつけて食べるものだ。少し手をかけるなら、すりつぶした甘辛い調味料にルンチャを混ぜ、軽くたたきつぶしてカレドックにする。ピーナッツや大豆の発酵食品や唐辛子と煮込み、ウルクトゥックにしてもよい。こんなに食べてもなんともないのだから、少なくとも栽培種には毒はないようだ。
しかし、ルンチャの味は、苦いようなえぐいような、なんともいいようのない妙な味である。この味わいをスンダ人はプフールという言葉であらわす。プフールな味のするものは、そう多くはない。ルンチャによく似たスズメナスビという植物の実や、出来のよくない生食用のナスぐらいである。
インドネシアでは一般にニガウリなどの苦い野菜を食べる。渋くて日本人が顔をしかめるようなものが平気な人も多い。しかし、スンダ人のようにルンチャを好む民族は他にはいない。他の地域の大きな市場でルンチャを探し求めてもまず見かけないが、スンダでは村の行商人でさえ毎日売りに来るごく普通の野菜だ。栽培も簡単で値段も安い。ある山村の調査では、頻繁に使われる食材として、米・ヤシ油・トウガラシ・トゥラシ(小エビなどで作った調味料)・マニオクというメジャーどころと肩を並べて、堂々とルンチャが登場している。わたしの調査した村も同様で、近所の家々の食卓にはしばしばルンチャがのぼっていた。都会の高級スンダ料理レストランでも、豪勢な魚や肉の料理と並んで、渋い脇役としてルンチャ料理は欠かせない。
わたしも初めはつきあい程度に仕方なく食べていたが、そのうちにおいしく感じられるようになってきた。初めてのビールはまずくても、大人になるとおいしくなるのと似ている。生のララブは噛むとぷちゅっとつぶれる感じが楽しい。ウルクトゥックには、発酵ピーナッツの旨みや風味、唐辛子の辛みと相まってえもいわれぬ複雑な味わいがあり、好物のひとつになった。日本人のわたしがルンチャを好きだと言うと、スンダ人はたいてい、あんなものが好きなのかとあきれて嬉しそうに笑う。日本人が納豆好きの外国人に会ったときのような感じである。「猛毒のイヌホオズキ」は、スンダの人びとにとって、ふるさとの味なのだ。
イヌホオズキ (学名:Solanum nigrum L.)
ナス科。南北両半球の温帯から熱帯にかけて広く分布し、農地や道端に自生する。高さ20~90センチメートルの一年草で、茎は枝分かれして広がる。球形の液果は、5~6粒が房になっていて、未熟なうちは緑色、熟すと黒くなる。漢名は龍葵(リュウキ)といって漢方薬になる。本来は有毒だが、熱帯には栽培種があり、全草を食用にする。インドネシア語はアンティ(anti)またはランティ(ranti)、スンダ語はルンチャ(leunca)。
ナス科。南北両半球の温帯から熱帯にかけて広く分布し、農地や道端に自生する。高さ20~90センチメートルの一年草で、茎は枝分かれして広がる。球形の液果は、5~6粒が房になっていて、未熟なうちは緑色、熟すと黒くなる。漢名は龍葵(リュウキ)といって漢方薬になる。本来は有毒だが、熱帯には栽培種があり、全草を食用にする。インドネシア語はアンティ(anti)またはランティ(ranti)、スンダ語はルンチャ(leunca)。
タイのうたげと選挙
高城 玲
自らを賭けるアリーナ
夜のとばりが下りるころ、人影が三々五々に蠢(うごめ)き出した。まぎれる闇を待っていたのか、定かではない。ただ、皆どこか楽しげだ。
タイ中部のとある農村、ときはまさに選挙戦まっただなか、投票日まで残りあと一週間だった。彼らが集まる先は、村の小さな雑貨屋。そこで近隣の人びとを集めたうたげが開かれるのだ。それも、票をえるための選挙運動の一環としてだという。
うたげをタイ語では、ギン・リアンという。個人が催す簡単なパーティーから儀礼の後におこなわれるものまで、ギン・リアンは多種多様だ。結婚式後におこなわれるギン・リアンなど、小学校の校庭に八人掛けの円卓を一〇〇卓も並べるほどの規模になることがある。他方、毎月二回おこなわれる宝くじで、たった三〇バーツ(当時約一〇〇円弱)でも儲けが出た場合、当選の幸運をえた者は、わずかな儲けの半分程をジュース代に費やして周囲におごらなければならない。これも同様にギン・リアンと称される。ギン・リアンという言葉は、その指し示す対象と規模をこのように自在に変えていく。
ただし、変わらないこともある。それは、食べ物や飲み物をおごり、おごられる一連のやりとりが、農民の大きな楽しみであるだけでなく、彼らの生活に深くかかわっていることだ。
とりわけ選挙運動期間中のギン・リアンは重要だ。農民の生活を文字通り左右するからだ。自分に近い筋の候補者が当選すれば、家の前の赤土の道が数ヵ月後には舗装されるかもしれない。そういう現実的で切実な問題につながるのだ。だからこそ、この場のギン・リアンは自らをどの候補者に賭けるのかというアリーナとなる。
心躍る喧噪の場
もちろん、法律上、候補者が有権者である農民に飲食物を与えることは、タイでも御法度だ。しかし、候補者主催のギン・リアンは、わたしが調査していた一九九〇年代後半、あたりまえの光景として農村にしっくりなじんでいた。
灼熱の太陽の下での農作業を終え、夜の八時を過ぎたころ、わずかな涼風に身をゆだねながら、即席のうたげの会場となった雑貨屋に人びとが集まってくる。
彼らが楽しげなのは、自分の懐を痛めることなく食事や酒を囲んで、近隣の人たち大勢と居合わせることができるからだ。そして、わいわいがやがやとおしゃべりに興じることができるからだろう。
ここでは、即興の冗談や歌も満載だ。翌朝早くの農作業に備えて寝支度を整えていた農民も、ギン・リアンのざわめきをどこからともなく聞きつけると、いそいそと会場に足を向ける。そうやって寝巻姿でやってきた若い女性に、オジサン連中は「(ここに来るのに)着飾ってきたのか」と冗談を投げかけ、周りは笑いにつつまれたりもする。また、太鼓やコップを鳴り物として歌や踊りや合いの手で、その場が一気に盛り上がることも稀ではない。そんな心躍る喧噪の場ともなる。
しかし、このような祝祭的な雰囲気の一方で、やはりこのうたげは選挙運動のまっただなかにもある。どんちゃん騒ぎのどさくさに紛れ秩序が薄められる完全な無礼講という訳にはいかず、逆に、日頃あまり意識していなかった社会のかたちが目に見えて浮かび上がってくる。
「共」と「競」
ギン・リアンに集まって手を合わせ歌い合う様子は、うたげという日本語の「(手を)拍ち上げ」、「歌合(うたあわせ)」、「円居(まとい)」とも通じ合う。そうした行為によって、人びとはひとつになり、渾然一体と交感し、境界が判然としなくなる。しかし選挙のギン・リアンでは、逆説的に、同じ行為が差異を露呈させもする。
あるとき、選挙中のギン・リアンで即興の歌が飛び出した。主催者である候補者が、皆にのせられて、大声で歌い出したのだ。すると集まった有権者はこぞって、それに合わせ、太鼓をたたいて手を拍ち上げる。身体でもリズムを合わせながら、なかには合いの手で奇声を発して盛り上げようとする者まで出てくる。ここで候補者は共に居合わせる者たちを結びつける要として、中心に位置付く。が、ある農民がすぐ後を引きとって我先にと歌い出しても、周囲の対応は対照的だ。歌に手を拍ち合わせる者はごく少数で、多くが勝手に飲み物を手にし、なかには隣同士で雑談を始める者まで出てくる始末。
場がひとつにまとまるうたげの要となった候補者の歌と、誰も関心を寄せないある農民の歌。同じ場で、ジャンルも技量も似かよったふたつの歌だが、人びとの対応には歴然たる差が見られるのだ。このように日頃は十分に意識されない社会のかたちが、両者のあいだの差異として、皆の目の前に示されていく。
この夜、ふたつのベクトルがうたげのなかで交錯した。ふたつのベクトルとは、共に居合わせ寄り添いながら、同時に差異をめぐってせめぎ合う、「共」と「競」だ。それは、誰かに別の誰かが居合わせることで、初めて目に見えてくる差異の「共/競/饗」・「演/宴」と言い換えてもいい。
夜のとばりのその蔭で、選挙のうたげが、共し競する社会を紡ぎ出していったのだ。
夜のとばりが下りるころ、人影が三々五々に蠢(うごめ)き出した。まぎれる闇を待っていたのか、定かではない。ただ、皆どこか楽しげだ。
タイ中部のとある農村、ときはまさに選挙戦まっただなか、投票日まで残りあと一週間だった。彼らが集まる先は、村の小さな雑貨屋。そこで近隣の人びとを集めたうたげが開かれるのだ。それも、票をえるための選挙運動の一環としてだという。
うたげをタイ語では、ギン・リアンという。個人が催す簡単なパーティーから儀礼の後におこなわれるものまで、ギン・リアンは多種多様だ。結婚式後におこなわれるギン・リアンなど、小学校の校庭に八人掛けの円卓を一〇〇卓も並べるほどの規模になることがある。他方、毎月二回おこなわれる宝くじで、たった三〇バーツ(当時約一〇〇円弱)でも儲けが出た場合、当選の幸運をえた者は、わずかな儲けの半分程をジュース代に費やして周囲におごらなければならない。これも同様にギン・リアンと称される。ギン・リアンという言葉は、その指し示す対象と規模をこのように自在に変えていく。
ただし、変わらないこともある。それは、食べ物や飲み物をおごり、おごられる一連のやりとりが、農民の大きな楽しみであるだけでなく、彼らの生活に深くかかわっていることだ。
とりわけ選挙運動期間中のギン・リアンは重要だ。農民の生活を文字通り左右するからだ。自分に近い筋の候補者が当選すれば、家の前の赤土の道が数ヵ月後には舗装されるかもしれない。そういう現実的で切実な問題につながるのだ。だからこそ、この場のギン・リアンは自らをどの候補者に賭けるのかというアリーナとなる。
心躍る喧噪の場
もちろん、法律上、候補者が有権者である農民に飲食物を与えることは、タイでも御法度だ。しかし、候補者主催のギン・リアンは、わたしが調査していた一九九〇年代後半、あたりまえの光景として農村にしっくりなじんでいた。
灼熱の太陽の下での農作業を終え、夜の八時を過ぎたころ、わずかな涼風に身をゆだねながら、即席のうたげの会場となった雑貨屋に人びとが集まってくる。
彼らが楽しげなのは、自分の懐を痛めることなく食事や酒を囲んで、近隣の人たち大勢と居合わせることができるからだ。そして、わいわいがやがやとおしゃべりに興じることができるからだろう。
ここでは、即興の冗談や歌も満載だ。翌朝早くの農作業に備えて寝支度を整えていた農民も、ギン・リアンのざわめきをどこからともなく聞きつけると、いそいそと会場に足を向ける。そうやって寝巻姿でやってきた若い女性に、オジサン連中は「(ここに来るのに)着飾ってきたのか」と冗談を投げかけ、周りは笑いにつつまれたりもする。また、太鼓やコップを鳴り物として歌や踊りや合いの手で、その場が一気に盛り上がることも稀ではない。そんな心躍る喧噪の場ともなる。
しかし、このような祝祭的な雰囲気の一方で、やはりこのうたげは選挙運動のまっただなかにもある。どんちゃん騒ぎのどさくさに紛れ秩序が薄められる完全な無礼講という訳にはいかず、逆に、日頃あまり意識していなかった社会のかたちが目に見えて浮かび上がってくる。
「共」と「競」
ギン・リアンに集まって手を合わせ歌い合う様子は、うたげという日本語の「(手を)拍ち上げ」、「歌合(うたあわせ)」、「円居(まとい)」とも通じ合う。そうした行為によって、人びとはひとつになり、渾然一体と交感し、境界が判然としなくなる。しかし選挙のギン・リアンでは、逆説的に、同じ行為が差異を露呈させもする。
あるとき、選挙中のギン・リアンで即興の歌が飛び出した。主催者である候補者が、皆にのせられて、大声で歌い出したのだ。すると集まった有権者はこぞって、それに合わせ、太鼓をたたいて手を拍ち上げる。身体でもリズムを合わせながら、なかには合いの手で奇声を発して盛り上げようとする者まで出てくる。ここで候補者は共に居合わせる者たちを結びつける要として、中心に位置付く。が、ある農民がすぐ後を引きとって我先にと歌い出しても、周囲の対応は対照的だ。歌に手を拍ち合わせる者はごく少数で、多くが勝手に飲み物を手にし、なかには隣同士で雑談を始める者まで出てくる始末。
場がひとつにまとまるうたげの要となった候補者の歌と、誰も関心を寄せないある農民の歌。同じ場で、ジャンルも技量も似かよったふたつの歌だが、人びとの対応には歴然たる差が見られるのだ。このように日頃は十分に意識されない社会のかたちが、両者のあいだの差異として、皆の目の前に示されていく。
この夜、ふたつのベクトルがうたげのなかで交錯した。ふたつのベクトルとは、共に居合わせ寄り添いながら、同時に差異をめぐってせめぎ合う、「共」と「競」だ。それは、誰かに別の誰かが居合わせることで、初めて目に見えてくる差異の「共/競/饗」・「演/宴」と言い換えてもいい。
夜のとばりのその蔭で、選挙のうたげが、共し競する社会を紡ぎ出していったのだ。
定期購読についてのお問い合わせは、ミュージアムショップまで。 本誌の内容についてのお問い合わせは、国立民族学博物館広報企画室企画連携係【TEL:06-6878-8210(平日9時~17時)】まで。