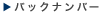月刊みんぱく 2007年3月号
2007年3月号
第31巻第3号通巻第354号
2007年3月1日発行
2007年3月1日発行
ナショナリズムに思う
川田 順造
最近ナショナリズムということを、さまざまな時と場で考えさせられる。
前首相の参拝もあった昨年八月一五日の靖国神社は、過去最高の人出といわれた。地下鉄の出口から大鳥居まで、ビラを配ったり大声に訴える人たちで混み合うのは例年通りだったが、昨年は東条英機自殺未遂をめぐって「立て看」脇で激論していた男の一人が「お前は非国民だ」と相手を罵っていた。「非国民」という言葉が人前で叫ばれるのを、戦後初めて私は聞いた。
戦争を知らない若者たちは、参道の一画で行われていた集会で「咲いた花なら散るのは覚悟、みごと散りましょ国のため」と大声で合唱していた。彼らは、私などの幼時の記憶に焼き付いている、忌まわしい神がかり軍国主義に、自分をどう重ね合わせていたのだろう。神社付属の遊就館の売店には、やはり戦争を知らない世代の、首相になりたい人が大急ぎで出した『美しい国へ』という、意味不明の題の本が山積みされていた。
西アフリカ・ダホメ王国最後の王で、植民地化のため侵入したフランス軍と戦って死んだ王が遺した王宮を復元する、ユネスコの世界遺産事業に、私は七年来参加してきた。復元完成の昨年がその王の死後一〇〇周年に当たるので、この王を「国家英雄」としたベナン共和国の国家行事に招待された。一七、八世紀に、軍事王国ダホメは近隣の民を捕らえて火器や火薬と引き替えにフランスの奴隷商人に売り、勢力を拡張した。一九世紀末、ダホメ王国もその一部だったこの地方を征服したフランスは、この王国構成者以外の住民の方が多かったにもかかわらず、ダホメのフランス語読み「ダオメ」を、この新植民地の名とした。独立後も新政府は植民地の領土と名称を受け継いだので、この王国の犠牲になった多数の人々の子孫も、同じ国家の国民とされた。一九七五年国民の融合を図るため、時の軍人大統領がダオメという国名を、現在のナイジェリアにやはり奴隷貿易で栄えた旧ベニン王国の名をとって、フランス語読みにした「ベナン」に変えた。
植民地として区切られた日本の三分の一にもみたない国土で、経済自立の見通しの立たないこの国が、国家英雄崇拝を通じて、国民の意気を高めようとするのは理解できる。だがそれは、かつてフランスが他の西欧列強との力関係で勝手に引いた境界を、今度はアフリカの住民が自らの意志で国境として追認することに他ならない。
昨年一〇月には民博の公開講演会で、オーストラリアという国民国家のあり方と、先住民の「国民」への統合、移民の制限をめぐる問題について考えさせられた。いわゆる先進諸国に比べて、格段に増加率が高いインドとサハラ以南アフリカの人口が今後急増し、「国家」間での移民の送り出しと受け入れの問題は、地球規模でさらに深刻化すると思われる。もちろん、日本においても。
新自由主義経済と情報・流通・移動のグローバル化、貧富の格差増大のなかで、国家、国民はどうあるべきなのか、その趨勢(すうせい)への情動的反応でもあるナショナリズムの過熱化にどう対処すべきなのか、人類学者の見識が問われている。
かわだ じゅんぞう/人類学者。1934年東京生まれ。日本のほか、西アフリカ、フランスでそれぞれのべ九年滞在調査。東西南の参照点による「文化の三角測量」を提唱。東京外国語大学名誉教授。著書、『口頭伝承論』(平凡社)、『人類学的認識論のために』(岩波書店)、『母の声、川の匂い』(筑摩書房)などがある。
前首相の参拝もあった昨年八月一五日の靖国神社は、過去最高の人出といわれた。地下鉄の出口から大鳥居まで、ビラを配ったり大声に訴える人たちで混み合うのは例年通りだったが、昨年は東条英機自殺未遂をめぐって「立て看」脇で激論していた男の一人が「お前は非国民だ」と相手を罵っていた。「非国民」という言葉が人前で叫ばれるのを、戦後初めて私は聞いた。
戦争を知らない若者たちは、参道の一画で行われていた集会で「咲いた花なら散るのは覚悟、みごと散りましょ国のため」と大声で合唱していた。彼らは、私などの幼時の記憶に焼き付いている、忌まわしい神がかり軍国主義に、自分をどう重ね合わせていたのだろう。神社付属の遊就館の売店には、やはり戦争を知らない世代の、首相になりたい人が大急ぎで出した『美しい国へ』という、意味不明の題の本が山積みされていた。
西アフリカ・ダホメ王国最後の王で、植民地化のため侵入したフランス軍と戦って死んだ王が遺した王宮を復元する、ユネスコの世界遺産事業に、私は七年来参加してきた。復元完成の昨年がその王の死後一〇〇周年に当たるので、この王を「国家英雄」としたベナン共和国の国家行事に招待された。一七、八世紀に、軍事王国ダホメは近隣の民を捕らえて火器や火薬と引き替えにフランスの奴隷商人に売り、勢力を拡張した。一九世紀末、ダホメ王国もその一部だったこの地方を征服したフランスは、この王国構成者以外の住民の方が多かったにもかかわらず、ダホメのフランス語読み「ダオメ」を、この新植民地の名とした。独立後も新政府は植民地の領土と名称を受け継いだので、この王国の犠牲になった多数の人々の子孫も、同じ国家の国民とされた。一九七五年国民の融合を図るため、時の軍人大統領がダオメという国名を、現在のナイジェリアにやはり奴隷貿易で栄えた旧ベニン王国の名をとって、フランス語読みにした「ベナン」に変えた。
植民地として区切られた日本の三分の一にもみたない国土で、経済自立の見通しの立たないこの国が、国家英雄崇拝を通じて、国民の意気を高めようとするのは理解できる。だがそれは、かつてフランスが他の西欧列強との力関係で勝手に引いた境界を、今度はアフリカの住民が自らの意志で国境として追認することに他ならない。
昨年一〇月には民博の公開講演会で、オーストラリアという国民国家のあり方と、先住民の「国民」への統合、移民の制限をめぐる問題について考えさせられた。いわゆる先進諸国に比べて、格段に増加率が高いインドとサハラ以南アフリカの人口が今後急増し、「国家」間での移民の送り出しと受け入れの問題は、地球規模でさらに深刻化すると思われる。もちろん、日本においても。
新自由主義経済と情報・流通・移動のグローバル化、貧富の格差増大のなかで、国家、国民はどうあるべきなのか、その趨勢(すうせい)への情動的反応でもあるナショナリズムの過熱化にどう対処すべきなのか、人類学者の見識が問われている。
かわだ じゅんぞう/人類学者。1934年東京生まれ。日本のほか、西アフリカ、フランスでそれぞれのべ九年滞在調査。東西南の参照点による「文化の三角測量」を提唱。東京外国語大学名誉教授。著書、『口頭伝承論』(平凡社)、『人類学的認識論のために』(岩波書店)、『母の声、川の匂い』(筑摩書房)などがある。
メディアの発達で入手できる情報量も増え続け、世界各地ではあらたな観光時代をむかえている。それは観光の実質とは違う「幻想」を求める旅であったりする。
人はなぜ旅をするのか。特集では今の観光の特色、さらに地域住民のかかわり方の変化にも注目したい。
人はなぜ旅をするのか。特集では今の観光の特色、さらに地域住民のかかわり方の変化にも注目したい。
「観光」という名の幻想
山村 高淑(やまむら たかよし) 京都嵯峨芸術大学助教授
マンガの国、日本へ
昨年の六月末、一六歳のフランス人少女二人がパリから列車の旅を続け、ポーランドからベラルーシに出国しようとしたところを、ビザ不所持の理由で国境警察に拘束された。仏紙リベラシオンが伝えた小さな記事である。良くあるニュースと思いきや、旅の動機を知って驚愕(きょうがく)した。じつは、彼女たち、陸路日本を目指していたのである!日本の漫画やビジュアル系バンドの大ファンで、その発信元の日本に行こうと思い立ったという。朝鮮半島までの陸路は鉄道を乗り継ぎ、海は船で渡ろうと計画していたそうだ。
一方、昨年のゴールデンウィークに中国は杭州で開催された「中国国際動漫節(アニメ・漫画祭)」は、六日間の会期中に約二八万人の来場者を数えた。なんとこの数は同年の「東京国際アニメフェア2006」(会期四日間)の約三倍である。さらにこの「動漫節」ではコスプレ(コスチュームプレイ)イベントがおこなわれ、全中国から多くの若者が集まり大盛況を博した。中国の若者たちが、日本のマンガ・アニメの登場人物になりきっているのである!
さて、人はなぜ、旅に出るのだろう?フランス人少女に、あえてユーラシア大陸横断の旅を決心させたものは何なのか。あの広大な中国で、若者を杭州に集わせたものは何なのか。
それは「漫画」であり「J‐Pop」であり「コスプレ」なのである。一体全体、我々はこういう旅をどう理解すれば良いのだろう?
「幻想」という物語
通常我々は観光という行為を、「本物」を見たり、「現実」を体験したりすることであると考える。しかし、じつはそうではなく、観光とは「幻想」に浸りに行くことなのである、ということをこのふたつの出来事は教えてくれる。我々はローマのコロッセオの前で、案外、建築としてのコロッセオを真剣に見ているわけではない。オードリー・ヘップバーンやグレゴリー・ペックに自らを重ね合わせたりしているのである。
この世界は、いうなれば元素が配列されただけの物質世界であり、それ自体に意味は無い。我々がそこに物語をもたせるからこそ、世界が意味をなすのであり、我々の存在も位置付けられる。我々は旅をとおして「幻想」という物語に浸り、無意味な世界に意味をもたせる作業をおこなっているのである。
これは、実体の無い「神」というものを感じに行く「巡礼」と本質的に同じ行為である。一部のアニメファンが秋葉原に行くことを「アキバ詣」とか「聖地巡礼」とよぶのも、そうした旅の本質に無意識のうちに気付いているからなのか。
我々はあらたな観光時代に突入した。インターネットなどメディアの発達により、人類がアクセスできる情報量は爆発的に増大し、観光において消費されるべき幻想はますます肥大化する。この傾向は、今後、観光資源の考え方や観光産業の形態を大きく変えていくことだろう。上述したような若者の旅の例はそのごく一例に過ぎない。
しかし、どんなに資源の考え方や産業の形態が変わろうとも、世界に意味をもたせ、自己を認識するという、精神的欲求としての旅の本質は、我々が人類である以上、これからも不変である。なぜなら、それは人類が自己という意識をもったときに同時に背負った業だからである。
昨年の六月末、一六歳のフランス人少女二人がパリから列車の旅を続け、ポーランドからベラルーシに出国しようとしたところを、ビザ不所持の理由で国境警察に拘束された。仏紙リベラシオンが伝えた小さな記事である。良くあるニュースと思いきや、旅の動機を知って驚愕(きょうがく)した。じつは、彼女たち、陸路日本を目指していたのである!日本の漫画やビジュアル系バンドの大ファンで、その発信元の日本に行こうと思い立ったという。朝鮮半島までの陸路は鉄道を乗り継ぎ、海は船で渡ろうと計画していたそうだ。
一方、昨年のゴールデンウィークに中国は杭州で開催された「中国国際動漫節(アニメ・漫画祭)」は、六日間の会期中に約二八万人の来場者を数えた。なんとこの数は同年の「東京国際アニメフェア2006」(会期四日間)の約三倍である。さらにこの「動漫節」ではコスプレ(コスチュームプレイ)イベントがおこなわれ、全中国から多くの若者が集まり大盛況を博した。中国の若者たちが、日本のマンガ・アニメの登場人物になりきっているのである!
さて、人はなぜ、旅に出るのだろう?フランス人少女に、あえてユーラシア大陸横断の旅を決心させたものは何なのか。あの広大な中国で、若者を杭州に集わせたものは何なのか。
それは「漫画」であり「J‐Pop」であり「コスプレ」なのである。一体全体、我々はこういう旅をどう理解すれば良いのだろう?
「幻想」という物語
通常我々は観光という行為を、「本物」を見たり、「現実」を体験したりすることであると考える。しかし、じつはそうではなく、観光とは「幻想」に浸りに行くことなのである、ということをこのふたつの出来事は教えてくれる。我々はローマのコロッセオの前で、案外、建築としてのコロッセオを真剣に見ているわけではない。オードリー・ヘップバーンやグレゴリー・ペックに自らを重ね合わせたりしているのである。
この世界は、いうなれば元素が配列されただけの物質世界であり、それ自体に意味は無い。我々がそこに物語をもたせるからこそ、世界が意味をなすのであり、我々の存在も位置付けられる。我々は旅をとおして「幻想」という物語に浸り、無意味な世界に意味をもたせる作業をおこなっているのである。
これは、実体の無い「神」というものを感じに行く「巡礼」と本質的に同じ行為である。一部のアニメファンが秋葉原に行くことを「アキバ詣」とか「聖地巡礼」とよぶのも、そうした旅の本質に無意識のうちに気付いているからなのか。
我々はあらたな観光時代に突入した。インターネットなどメディアの発達により、人類がアクセスできる情報量は爆発的に増大し、観光において消費されるべき幻想はますます肥大化する。この傾向は、今後、観光資源の考え方や観光産業の形態を大きく変えていくことだろう。上述したような若者の旅の例はそのごく一例に過ぎない。
しかし、どんなに資源の考え方や産業の形態が変わろうとも、世界に意味をもたせ、自己を認識するという、精神的欲求としての旅の本質は、我々が人類である以上、これからも不変である。なぜなら、それは人類が自己という意識をもったときに同時に背負った業だからである。
日本人の旅の心根をめぐって
目崎 茂和(めざき しげかず) 南山大学教授
神仏との出会いを求める
日本人の旅、とくに庶民の旅のはじまりは、世界に類例のない「伊勢参り」や「おかげ参り」にそのルーツが求められよう。日本人ばかりか、現代のマスツーリズムの起源でもある。中世末期にはじまる伊勢参宮の旅は、とくに江戸時代に入り、街道・海路の整備もあり、御師(おんし)(エージェント)に世話され、全国規模のネットワークの「講」グループによる旅のシステムである。
さらに歴史をさかのぼれば、中世の法皇や上皇らの「熊野詣」、京から熊野三山や浄土世界への参詣が、日本人の旅の原風景でもあろうか。旅と寺社参詣・聖地めぐりは、日本人の旅立ちの原点である。
二〇〇五年に、熊野三山を含め「紀伊山地の霊場と参詣道」として、世界遺産に登録された。いわゆる「熊野古道」自体が指定されたのは、スペインのサンチャゴへの巡礼路についで、世界で二例目である。伝統的な旅のプロセスとしての、ルートである困難・試練をともなうような「道中」「道行」が、とりわけ認識された意義は大きい。
ところで「おかげ参り」の伝統は、毎年の正月の寺社への初詣・初日の出などで、その片鱗や残照がうかがえる。なお、感謝の気持ちをあらわす「お蔭さま」「お陰さまで」とは、「御蔭祭」「みあれ祭」での神の出現、神仏との出会いで、その「陰(影)」を見たことから、このことばの由来といわれ、日本人の旅の心性や精神性を考える、キーワードかもしれない。
神話の中の旅
『古事記』など神話に描かれた旅を分析してみると、日本人の旅の心性、精神性がより理解できるのではなかろうか。大国主命(おおくにぬしのみこと)の若い時(オホナムチ)の初旅といえる「因幡(いなば)(稲羽)の白兎」を事例に考えてみたい。
この神話は、オホナムチの旅(東行)ばかりか、兎の旅(南行と西行)のふたつの旅が交差・重層する構造をもつ物語となっている。オホナムチの旅は、因幡の八上比売(やがみひめ)を競い合って娶(めと)るため、多くの兄弟の八十神(やそがみ)たちにしたがって大きな袋をもち、出雲から東の因幡への旅の道中での挿話である。
この「因幡の白兎」の旅は、図に示すように、十二支の卯(兎・東・青)が、陰陽五行(木↓火↓土↓金)の順にめぐり、兎神(月神)になるもので、時空間の変遷が、日・月のように東(陽・木・卯)↓西(陰・金・酉)に移動する再生循環を、象徴する神話でもある。
日本人の旅の根底には、この神話が物語るように、「熊野詣」や「伊勢参り」と同様に、若き旅で、その苦労を乗り越え、神の加護で再生した後、この託宣(たくせん)を授けられるような神にもなれるという、陰陽五行の循環論的「黄泉(よみ)がえり」「生きる道」精神が脈打っているのではなかろうか。
日本人の旅、とくに庶民の旅のはじまりは、世界に類例のない「伊勢参り」や「おかげ参り」にそのルーツが求められよう。日本人ばかりか、現代のマスツーリズムの起源でもある。中世末期にはじまる伊勢参宮の旅は、とくに江戸時代に入り、街道・海路の整備もあり、御師(おんし)(エージェント)に世話され、全国規模のネットワークの「講」グループによる旅のシステムである。
さらに歴史をさかのぼれば、中世の法皇や上皇らの「熊野詣」、京から熊野三山や浄土世界への参詣が、日本人の旅の原風景でもあろうか。旅と寺社参詣・聖地めぐりは、日本人の旅立ちの原点である。
二〇〇五年に、熊野三山を含め「紀伊山地の霊場と参詣道」として、世界遺産に登録された。いわゆる「熊野古道」自体が指定されたのは、スペインのサンチャゴへの巡礼路についで、世界で二例目である。伝統的な旅のプロセスとしての、ルートである困難・試練をともなうような「道中」「道行」が、とりわけ認識された意義は大きい。
ところで「おかげ参り」の伝統は、毎年の正月の寺社への初詣・初日の出などで、その片鱗や残照がうかがえる。なお、感謝の気持ちをあらわす「お蔭さま」「お陰さまで」とは、「御蔭祭」「みあれ祭」での神の出現、神仏との出会いで、その「陰(影)」を見たことから、このことばの由来といわれ、日本人の旅の心性や精神性を考える、キーワードかもしれない。
神話の中の旅
『古事記』など神話に描かれた旅を分析してみると、日本人の旅の心性、精神性がより理解できるのではなかろうか。大国主命(おおくにぬしのみこと)の若い時(オホナムチ)の初旅といえる「因幡(いなば)(稲羽)の白兎」を事例に考えてみたい。
この神話は、オホナムチの旅(東行)ばかりか、兎の旅(南行と西行)のふたつの旅が交差・重層する構造をもつ物語となっている。オホナムチの旅は、因幡の八上比売(やがみひめ)を競い合って娶(めと)るため、多くの兄弟の八十神(やそがみ)たちにしたがって大きな袋をもち、出雲から東の因幡への旅の道中での挿話である。
この「因幡の白兎」の旅は、図に示すように、十二支の卯(兎・東・青)が、陰陽五行(木↓火↓土↓金)の順にめぐり、兎神(月神)になるもので、時空間の変遷が、日・月のように東(陽・木・卯)↓西(陰・金・酉)に移動する再生循環を、象徴する神話でもある。
日本人の旅の根底には、この神話が物語るように、「熊野詣」や「伊勢参り」と同様に、若き旅で、その苦労を乗り越え、神の加護で再生した後、この託宣(たくせん)を授けられるような神にもなれるという、陰陽五行の循環論的「黄泉(よみ)がえり」「生きる道」精神が脈打っているのではなかろうか。
韓流ツアーから見る旅の類型
林 史樹(はやし ふみき) 神田外語大学専任講師
韓流の集客力
近年、「韓流」をテーマにした旅行がブームとなっている。ドラマ「冬のソナタ」(以下、冬ソナ)の舞台となった春川(チュンチョン)・南怡島(ナミソム)はもちろん、ロケで用いられた高校まで観光客が訪れる。各地では、ドラマを記念したモニュメントが作られ、付近にはにわかに俳優の写真やカレンダーを販売する店ができた。冬ソナのロケ地を中心におこなう韓国旅行を、一般に「冬ソナ観光」とよんだりもする。冬ソナ観光は、ロケ地を追うばかりでなく、一般の韓国観光もセットになっているところが通常のロケ地ツアーと異なる点と考えられる。
これらの観光がもたらす経済効果は大きく、二〇〇六年一一月二九日から済州島(チェジュド)の西帰浦(ソギボ)市済州コンベンションセンターで開催された「韓流エキスポinASIA」には、四〇〇〇人を超える日本からのファンが開幕式に訪れたといわれる。今回の韓流エキスポだけでも、七五〇億ウォン(約九三億九八〇〇万円)が見込まれている。
実際に、韓流の集客力は絶大であった。二〇〇五年の春先にロケ地であるソウルの中央(チュンアン)高校に行くと、正門横の駄菓子屋が韓流グッズを販売し、正門向かいでも仮設店舗でグッズを並べていた。わずか二〇分ほどのあいだに小型マイクロバスが二台もきた。ツアー客である。
東京から釜山(プサン)行きの飛行機を予約したときも、オフシーズンにもかかわらず、空席待ちといわれたことがある。春川に行くにはソウルに近い仁川(インチョン)国際空港が便利にもかかわらずである。少し日程をずらして釜山に行ったが、改装した釜山の金海(キメ)国際空港の待合いには書店があり、ポスターやカレンダーなどの韓流グッズを販売していた。後方で搭乗時間を待っていた女性グループが買い足りないといって、それらをあさる光景を目にした。
疑似イベントの旅
それでは、韓流ツアーはどのような旅といえるのだろうか。旅の目的には、(1)自分探しにつながる「オーセンティシティ(本物のもの)の追求」と、(2)既知の場所を再確認する「疑似イベント」の旅があるといわれる。韓流ツアーに、憧れの人物に同化したい、憧れの人物がいた場所に身を置きたいというのがあるとすれば、前もって写真などで素敵と思った場所に自分を置くことで満足する、一種の疑似イベントといえるかもしれない。しかし、疑似的体験をえるための対象は「動く」のである。つまり、人物を求めて動くため、訪問先は必ずしも特定されていない。これは、名所巡りを想定しがちな「観光」に含まれるのか、疑似イベントの派生型なのか。韓流ツアーから旅の類型をふと考えてしまった。
近年、「韓流」をテーマにした旅行がブームとなっている。ドラマ「冬のソナタ」(以下、冬ソナ)の舞台となった春川(チュンチョン)・南怡島(ナミソム)はもちろん、ロケで用いられた高校まで観光客が訪れる。各地では、ドラマを記念したモニュメントが作られ、付近にはにわかに俳優の写真やカレンダーを販売する店ができた。冬ソナのロケ地を中心におこなう韓国旅行を、一般に「冬ソナ観光」とよんだりもする。冬ソナ観光は、ロケ地を追うばかりでなく、一般の韓国観光もセットになっているところが通常のロケ地ツアーと異なる点と考えられる。
これらの観光がもたらす経済効果は大きく、二〇〇六年一一月二九日から済州島(チェジュド)の西帰浦(ソギボ)市済州コンベンションセンターで開催された「韓流エキスポinASIA」には、四〇〇〇人を超える日本からのファンが開幕式に訪れたといわれる。今回の韓流エキスポだけでも、七五〇億ウォン(約九三億九八〇〇万円)が見込まれている。
実際に、韓流の集客力は絶大であった。二〇〇五年の春先にロケ地であるソウルの中央(チュンアン)高校に行くと、正門横の駄菓子屋が韓流グッズを販売し、正門向かいでも仮設店舗でグッズを並べていた。わずか二〇分ほどのあいだに小型マイクロバスが二台もきた。ツアー客である。
東京から釜山(プサン)行きの飛行機を予約したときも、オフシーズンにもかかわらず、空席待ちといわれたことがある。春川に行くにはソウルに近い仁川(インチョン)国際空港が便利にもかかわらずである。少し日程をずらして釜山に行ったが、改装した釜山の金海(キメ)国際空港の待合いには書店があり、ポスターやカレンダーなどの韓流グッズを販売していた。後方で搭乗時間を待っていた女性グループが買い足りないといって、それらをあさる光景を目にした。
疑似イベントの旅
それでは、韓流ツアーはどのような旅といえるのだろうか。旅の目的には、(1)自分探しにつながる「オーセンティシティ(本物のもの)の追求」と、(2)既知の場所を再確認する「疑似イベント」の旅があるといわれる。韓流ツアーに、憧れの人物に同化したい、憧れの人物がいた場所に身を置きたいというのがあるとすれば、前もって写真などで素敵と思った場所に自分を置くことで満足する、一種の疑似イベントといえるかもしれない。しかし、疑似的体験をえるための対象は「動く」のである。つまり、人物を求めて動くため、訪問先は必ずしも特定されていない。これは、名所巡りを想定しがちな「観光」に含まれるのか、疑似イベントの派生型なのか。韓流ツアーから旅の類型をふと考えてしまった。
もう一つの観光?―イタリアのアグリツーリズモ―
イタリアといえば、政府観光局も自負するように「文化と歴史の国」として世界各地から多くの観光客を集める観光国だが、そんななか、近年注目されつつあるのが、アグリツーリズモである。
アグリツーリズモとは、農業(アグリコルトゥーラ)と観光(ツーリズモ)が合体したことばで、その名のとおり、農家がおこなう観光サービスのことである。たいていは、使わなくなった土地や家畜小屋などを利用して宿泊施設を作り、自分の農園で作った野菜やワイン、乳製品などを用いた食事を提供している。さらには農業体験、料理教室、乗馬やトレッキングなどのスポーツや娯楽を企画するところもある。
このため、ゆったりとした時間と自然のなかで、農家の人たちと直接ふれ合いながら地元の料理や生活を楽しむという趣向が話題を呼び、最近ではロハスやスローフードなどのブームに乗って客が増え、日本からも観光客が訪れるようになった。
とはいえ実態は、こうしたイメージとずれることも少なくない。というのも、アグリツーリズモとは、法的にはあくまでも農家の副業として規定されたものだからである。観光サービスからえる収入が農業の収入を超えないという条件もある。
そもそもアグリツーリズモは、一九八〇年代半ば、衰退が進む農業への支援策として始まった。そして、農業の維持は農地の劣化を防ぎ、環境保護や地域の活性化にもつながると考えられ、奨励はさらに進んだ。もちろんアグリツーリズモ農家のなかには、もともと環境問題や有機栽培などに関心をもっていたり、町おこしの中心人物として活動してきた者もいる。しかしその一方で、ビジネスチャンスのひとつとしてとびついたものの、うまくいかず撤退する農家も多い。
観光をとおして農業の維持・発展、環境保護、地域活性という一石三鳥を狙おうとするアグリツーリズモに、総合的な評価を下すのはまだ早い。ただしこの観光形態が、たんなる消費主義的なムードの田舎生活の提供ではなく、地域に根ざし、むしろ生産者側が主体となった試みであるということは、そこを訪れる我々も(彼らの生活を知りたいならなおさら)もっと評価すべきだろう。
アグリツーリズモとは、農業(アグリコルトゥーラ)と観光(ツーリズモ)が合体したことばで、その名のとおり、農家がおこなう観光サービスのことである。たいていは、使わなくなった土地や家畜小屋などを利用して宿泊施設を作り、自分の農園で作った野菜やワイン、乳製品などを用いた食事を提供している。さらには農業体験、料理教室、乗馬やトレッキングなどのスポーツや娯楽を企画するところもある。
このため、ゆったりとした時間と自然のなかで、農家の人たちと直接ふれ合いながら地元の料理や生活を楽しむという趣向が話題を呼び、最近ではロハスやスローフードなどのブームに乗って客が増え、日本からも観光客が訪れるようになった。
とはいえ実態は、こうしたイメージとずれることも少なくない。というのも、アグリツーリズモとは、法的にはあくまでも農家の副業として規定されたものだからである。観光サービスからえる収入が農業の収入を超えないという条件もある。
そもそもアグリツーリズモは、一九八〇年代半ば、衰退が進む農業への支援策として始まった。そして、農業の維持は農地の劣化を防ぎ、環境保護や地域の活性化にもつながると考えられ、奨励はさらに進んだ。もちろんアグリツーリズモ農家のなかには、もともと環境問題や有機栽培などに関心をもっていたり、町おこしの中心人物として活動してきた者もいる。しかしその一方で、ビジネスチャンスのひとつとしてとびついたものの、うまくいかず撤退する農家も多い。
観光をとおして農業の維持・発展、環境保護、地域活性という一石三鳥を狙おうとするアグリツーリズモに、総合的な評価を下すのはまだ早い。ただしこの観光形態が、たんなる消費主義的なムードの田舎生活の提供ではなく、地域に根ざし、むしろ生産者側が主体となった試みであるということは、そこを訪れる我々も(彼らの生活を知りたいならなおさら)もっと評価すべきだろう。
マサイ村のエンターテインメント
岩井 雪乃(いわい ゆきの) 早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター客員講師
赤い布をまとった長身の戦士が、槍を片手に空高くジャンプする。そんなマサイの姿は、数あるアフリカの民族のなかでもっとも有名だろう。マサイの人びとは、このイメージを観光資源として有効に活用して「観光マサイ村」を作っている。そこでは、実際に生活している集落を観光客に開放しているのだ。お金を払ってなかに入ると、牛糞で塗り固めた家のなかを見学したり、戦士や少女の歌や踊りに参加することができる。最近ではホームステイプログラムを実施しているところもある。
とはいえ、決して観光客に媚びないのがマサイらしいところだ。わたしがタンザニアのンゴロンゴロ自然保護区のマサイ村を訪れたときのこと、観光客のためのダンスのはずが、戦士同士の真剣勝負になってしまったことがある。マサイの戦士にとって、より高く跳べることは強さの象徴だ。大地のエネルギーがはじけ出るように、次々と宙に舞う彼らのダンスは圧巻だった。しかし、跳んでいるうちに彼らは本気になってきて、真剣なジャンプ競争が始まってしまった。やがてわたしたちの存在は忘れられてしまい、ジャンプに陶酔する戦士たちを後に、わたしたちはすごすごと退散するしかなかった。
伝統生活を観光に提供しているマサイだが、近代的な生活と隔絶して生きているわけではない。マサイ村から少し離れた観光客の行かない集落では、ビリヤードに興じるマサイたちの姿がある。二年ほど前に入ってきたこのゲームは、すぐに大流行した。携帯の普及も目ざましい。サバンナでも電波が入る地域が年々拡大しており、牛を放牧しながらの通話が可能になりつつある。
急増しているタンザニアの観光客と発達する情報網を背景に、彼らの観光へのかかわりは変わっていくのだろう。エンターテインメントとして、洗練される方へ向かうのだろうか。しかし一方で、あの内輪で楽しむ気持ちを失わないでほしいものだ。
とはいえ、決して観光客に媚びないのがマサイらしいところだ。わたしがタンザニアのンゴロンゴロ自然保護区のマサイ村を訪れたときのこと、観光客のためのダンスのはずが、戦士同士の真剣勝負になってしまったことがある。マサイの戦士にとって、より高く跳べることは強さの象徴だ。大地のエネルギーがはじけ出るように、次々と宙に舞う彼らのダンスは圧巻だった。しかし、跳んでいるうちに彼らは本気になってきて、真剣なジャンプ競争が始まってしまった。やがてわたしたちの存在は忘れられてしまい、ジャンプに陶酔する戦士たちを後に、わたしたちはすごすごと退散するしかなかった。
伝統生活を観光に提供しているマサイだが、近代的な生活と隔絶して生きているわけではない。マサイ村から少し離れた観光客の行かない集落では、ビリヤードに興じるマサイたちの姿がある。二年ほど前に入ってきたこのゲームは、すぐに大流行した。携帯の普及も目ざましい。サバンナでも電波が入る地域が年々拡大しており、牛を放牧しながらの通話が可能になりつつある。
急増しているタンザニアの観光客と発達する情報網を背景に、彼らの観光へのかかわりは変わっていくのだろう。エンターテインメントとして、洗練される方へ向かうのだろうか。しかし一方で、あの内輪で楽しむ気持ちを失わないでほしいものだ。
住民参加型のペルー遺跡観光
ラテンアメリカ各国では、近年、住民参加型の持続的観光をとおして貧困解消を図ろうという動きが出てきている。古代アンデス文明の中核地であるペルーでも、遺跡などを核に、これを推進しようとしている。その先鞭(せんべん)をつけたのは、我々日本調査団である。
わたしが所属する調査団は、日本各地の大学や研究所の文化人類学者が寄り集まって、毎年、ペルーで発掘調査を実施している。ここ十数年携わってきた、北高地のクントゥル・ワシという大規模な神殿の調査では、偶然にも、大量の金製品を副葬した墓に遭遇し、出土品の帰属をめぐる騒動に巻き込まれた。国か、県か、はたまた地元の村に置くべきか、さまざまな議論が渦巻くなかで、我々と村人が選択したのは、博物館を遺跡の麓に建設し、そこに出土品を納めることであった。資金は、日本で開催した展覧会で集めた協賛金や寄付金を充て、完成後の運営は、地元の村に作られたNPO組織に委ねたのである。
遺跡周辺で暮らす住民が盗掘に手を染めることの多いアンデスで、住民自らが遺跡を守り、出土品を管理することは、稀なケースである。彼らの努力は、その後、上下水道や電気などのインフラ整備に結び付き、国連開発計画からも注目されることになる。また、この活動を聞きつけた各地の自治体からの講演要請は村人の自尊心を高め、これが遺跡保存への意識へとフィードバックされた。一方で、我々もユネスコや日本から援助を導き、遺跡保存や博物館改修を実現し、観光資源として整備することに努めてきた。
遺跡を掘れば、必ず何かが出てくるし、また出てきたものは、場合によっては、研究者の手を離れて、観光など別の脈絡の中で意味付けがなされる。情報のグローバル化と途上国に強要される新自由主義経済の波のなかで、出土品の利用や活用は、もはや文化遺産関係者だけに限定されるものではなくなっているのである。観光開発にまで巻き込まれる文化遺産関係者という姿は常態化しつつあるといえよう。
わたしが所属する調査団は、日本各地の大学や研究所の文化人類学者が寄り集まって、毎年、ペルーで発掘調査を実施している。ここ十数年携わってきた、北高地のクントゥル・ワシという大規模な神殿の調査では、偶然にも、大量の金製品を副葬した墓に遭遇し、出土品の帰属をめぐる騒動に巻き込まれた。国か、県か、はたまた地元の村に置くべきか、さまざまな議論が渦巻くなかで、我々と村人が選択したのは、博物館を遺跡の麓に建設し、そこに出土品を納めることであった。資金は、日本で開催した展覧会で集めた協賛金や寄付金を充て、完成後の運営は、地元の村に作られたNPO組織に委ねたのである。
遺跡周辺で暮らす住民が盗掘に手を染めることの多いアンデスで、住民自らが遺跡を守り、出土品を管理することは、稀なケースである。彼らの努力は、その後、上下水道や電気などのインフラ整備に結び付き、国連開発計画からも注目されることになる。また、この活動を聞きつけた各地の自治体からの講演要請は村人の自尊心を高め、これが遺跡保存への意識へとフィードバックされた。一方で、我々もユネスコや日本から援助を導き、遺跡保存や博物館改修を実現し、観光資源として整備することに努めてきた。
遺跡を掘れば、必ず何かが出てくるし、また出てきたものは、場合によっては、研究者の手を離れて、観光など別の脈絡の中で意味付けがなされる。情報のグローバル化と途上国に強要される新自由主義経済の波のなかで、出土品の利用や活用は、もはや文化遺産関係者だけに限定されるものではなくなっているのである。観光開発にまで巻き込まれる文化遺産関係者という姿は常態化しつつあるといえよう。
戦争を語る、オンリーワンの博物館を
齋藤 義朗(さいとう よしろう) 呉市海事歴史科学館(大和ミュージアム)学芸員
戦艦「大和」の復元物を媒介に、
歴史の証人ともよばれるべき
戦争体験者の証言が、今、
呉市海事歴史科学館に集まりつつあるという。
同館の戦争の悲惨さ、平和の尊さを
伝えてゆこうとする活動を紹介したい。
二〇〇五年四月二三日、広島県呉市に新しい博物館が誕生した。その名は呉市海事歴史科学館。愛称「大和ミュージアム」といえばわかっていただけるだろうか。日本海海戦から一〇〇年、太平洋戦争終戦から六〇年目、映画でもとりあげられ、戦争の時代を再検証する動きが活発化するなかでオープンし、初年度は一六一万人の来館者を記録した。二年目となる二〇〇六年一二月末には累計二六〇万人を達成した。
瀬戸内海沿岸に延びるJR呉線の呉駅から専用歩道で徒歩五分、ミュージアムは戦艦「大和」建造の舞台となった呉海軍工廠(こうしょう)造船ドック跡を見渡す位置に建っている。
館のコンセプトは、明治以来、海軍工廠とともに歩んできた軍港・呉の歴史と、そこで培われた造船ほか各種技術を紹介し、「大和」の最期などを通じて戦争の悲惨さ、平和の尊さを伝えようというもの。その展示の中核に位置するのが一階展示フロア中央にそびえる一〇分の一スケールの戦艦「大和」である。
歴史の証人ともよばれるべき
戦争体験者の証言が、今、
呉市海事歴史科学館に集まりつつあるという。
同館の戦争の悲惨さ、平和の尊さを
伝えてゆこうとする活動を紹介したい。
二〇〇五年四月二三日、広島県呉市に新しい博物館が誕生した。その名は呉市海事歴史科学館。愛称「大和ミュージアム」といえばわかっていただけるだろうか。日本海海戦から一〇〇年、太平洋戦争終戦から六〇年目、映画でもとりあげられ、戦争の時代を再検証する動きが活発化するなかでオープンし、初年度は一六一万人の来館者を記録した。二年目となる二〇〇六年一二月末には累計二六〇万人を達成した。
瀬戸内海沿岸に延びるJR呉線の呉駅から専用歩道で徒歩五分、ミュージアムは戦艦「大和」建造の舞台となった呉海軍工廠(こうしょう)造船ドック跡を見渡す位置に建っている。
館のコンセプトは、明治以来、海軍工廠とともに歩んできた軍港・呉の歴史と、そこで培われた造船ほか各種技術を紹介し、「大和」の最期などを通じて戦争の悲惨さ、平和の尊さを伝えようというもの。その展示の中核に位置するのが一階展示フロア中央にそびえる一〇分の一スケールの戦艦「大和」である。
一〇分の一「大和」を造る
模型といいながら、その圧倒的な迫力に訪れた人はみな息をのみ、一瞬足を止めたのちに周囲を歩き始める。全長二六・三メートルの超巨大模型は、図体が大きいだけでなく、可能な限り細部にわたって”復元“したものである。製作した側としては、単なる大型プラモデルの展示と思っていただきたくはない。
ミュージアム建設にあたっては、「どこにもない、呉でしかできないオンリーワンの博物館」を作るため、呉の造船技術の歴史を展示するシンボルが必要だった。そこで出たのが一〇分の一「大和」建造計画。潜水調査などを経て図面の製作に六年。一九九七年の立案から完成までには八年の歳月を要した。紆余曲折を経て二〇〇三年に呉市で一〇分の一「大和」建造が決定。初めてづくしの巨大プロジェクトは困難続きであった。ミュージアムの開館期日は決定済み。残された製作期間はわずかに二年(実質一年半)。資料分析やコスト面とともに、時間という大きな壁が立ちはだかる建造となったのである。
戦艦「大和」は、昭和一〇年代の日本の技術レベルの高さを示すと同時に、時代の矛盾と戦争のむなしさを映す鏡でもある。真珠湾攻撃から八日後の一九四一年一二月一六日、世界最大・最強の戦艦として登場しながらも航空戦力が主役となった太平洋戦争を象徴するように、新造時の優雅な佇まいは増設された対空機銃でハリネズミのように変貌し、一九四五年四月七日、沖縄海上特攻の途上、米軍機の猛攻により三〇五六名の人命とともに悲劇的な最期を遂げた。今も三〇〇名近くの乗組員が氏名不詳のままとなっている。
「大和」に関しては情報が極めて厳重に統制され、国民の目から隠されたまま建造され、沈没した。国民の大多数が存在を知ったのは戦後になってから。終戦と同時にほとんどの記録類が灰となった幻の戦艦である。その「大和」を一〇分の一スケールで実際に立体化するためには、全長二六三メートルの巨艦を一センチメートル単位で分析する必要があった。模型の世界では、一ミリメートル単位の精度が要求されるからである。従来の研究蓄積に加え、あらたに収集した「大和」の原図面約二〇〇枚(部分図ばかり)と写真約一〇〇点、海底の「大和」を撮影した六〇時間におよぶ潜水調査映像などをもとにした戦艦「大和」復元は、気の遠くなるような作業となった。
それでも不明箇所は数限りなかった。そこは当事者への聞きとり調査で補うことになった。例えば「大和」の代名詞ともいえる四六センチ三連装主砲塔は、概略図がある程度で、出入口のある背面部の考証は憶測の域を出ないものだった。そこで元「大和」二番主砲砲員だった戸田文男さん(当時、上等水兵)にうかがったところ、「大和が沈没直前、左に大きく傾斜した際に、扉を開けられず砲塔内に取り残された者がいた」という辛い体験を語っていただいた。この証言から背面部出入口のとり付け状態などが明らかになったのである。
実際の製作段階でも、あらたな資料が発見されるたびに、作っては直しを繰り返し、試行錯誤の連続であった。結局最後は損得勘定を度外視した「現代の匠」たちが熱意と気迫で納期に間に合わせたのである。一〇分の一「大和」が形になってくるにしたがい、製作担当者一同は、「大和」が鋼鉄の箱ではなく、三〇〇〇人が生活を営み、生命を託した、生きた建造物であったことを実感するようになっていった。そして二〇〇五年二月一日、一〇分の一「大和」は完成した。戦艦「大和」にかかわった人たちが無数にいたように、一〇分の一スケールで復元した「大和」もまた元乗組員や遺族の方々、建造スタッフほか多くの関係者の想いが込められた艦(ふね)となったのである。
集まる記憶、よみがえる記憶
困難極まる道のりのなかで建造した一〇分の一「大和」は、ミュージアムの来館者に科学技術の発展と戦争の悲劇という「科学技術の光と影」両面のメッセージを送っている。ところが開館後同時に一〇分の一「大和」があらたな資料や情報をもつ歴史の証人ともいうべき人たちとミュージアムとをつなぐ役割も果たしていることを筆者は実感するようになった。ミュージアムの開館と一〇分の一「大和」の展示を契機にあらたに連絡をとることができた元乗組員や遺族の方々ほか関係者はのべ三〇人以上にのぼる。学芸員がいる研究室へ直接連絡をいただくこともあるが、ほとんどの場合、最初に接するのは展示室内各所で解説・案内をしてもらっているボランティアガイドさんたちだ。彼らを経由して学芸員へ情報が集められるのである。
元乗組員の方の場合、最初から「大和」乗艦者であったことを口にする人はまれだ。大半がガイドさんとのやりとりのなかで明らかになる。多くがシルバー世代で構成されるガイドさんたちは、戦争の時代を生き抜いた世代とも年齢的に近く、孫のような学芸員と比べて身構える必要もない。加えてガイドさんたちは話術も巧みで古い話には事欠かない。そうするうちに「じつは自分は『大和』のあの部分におったんですよ」と一〇分の一「大和」のある部分を示されるのである。
このような話は「大和」に限らず、大型資料展示室内にある「零式艦上戦闘機(零戦)」などでも同じである。戦争中、海軍の基地や航空母艦などでパイロット、あるいは航空機整備員をしていた方々の情報をえたのもガイドさん経由だった。そこから連絡をいただいて学芸員が展示室へ駆けつける。ミュージアムへ訪れる歴史の証人の発掘においても、ボランティアガイドさんは多大な貢献をしているのだ。
ミュージアムでは、週末ともなるとおじいちゃん・おばあちゃんから子・孫までの三世代にわたる家族連れが増える。そして歴史展示室内では高齢者が先生となって、戦争中の話を、関連する展示資料をもとに家族に説明している場面に遭遇することが多い。ガイドさんやほかの来館者も含めて、若い世代が生徒になって説明を聞く即席ミニ講座が開かれていることもしばしばである。後でうかがうと、家庭では戦争中の話をしたことはなかったが、ミュージアムの展示を見て話す気になったという方ばかりだった。
「記憶」を「記録」に
終戦から六一年。二七六人いた沖縄海上特攻時の「大和」乗組員生還者も二〇人を割り込んだ。戦争の時代を経験した世代は高齢となり、ここ数年で加速度的に減り続けている。来館者に”生の証言“を聞いていただこうにも、体力的に不安を抱える方がほとんどだ。しかし当事者の話ほど説得力のあるものはない。そこでミュージアムの歴史展示室やライブラリー内には証言者映像コーナーを設け、一九人の方々の話を聞いていただけるようにしている。また、ミュージアム開館後に出会うことができた歴史の証人たちには、後日、ビデオカメラの前でお話をいただくようお願いしている。住所が遠方で、ミュージアムへご足労願うのが難しい場合、カメラと三脚を抱えてこちらから訪問している。お話をうかがうにあたり、筆者に歴史の証人の記憶を引き出す能力が不足していると感じた場合には、館長の戸高一成や統括学芸員の相原謙次をインタビュアーとして巻き込んでの作業となる。企画展で募集、依頼した証言も含めると、こうして撮りためた六〇分ビデオテープは四〇本近くになった。これらは多くの方に見ていただけるよう準備を進めている。
「大和ミュージアム」では、科学技術と歴史の双方を展示することで歴史科学館の名称をとっている。その技術はよく「両刃の剣」と表現される。暮らしを豊かにできるはずのすばらしい技術であっても、人間の使い方次第で悲惨な結果を生む危険性をあわせもつ。一〇分の一「大和」はその象徴であり、戦争の悲惨さ、平和の尊さを我々に語りかける。それゆえミュージアムでは、戦争の時代の「記録」と「記憶」を証言者映像として多くの人たちのために残し、伝えていこうとしている。これは当館に課せられた義務だと筆者は思っている。
模型といいながら、その圧倒的な迫力に訪れた人はみな息をのみ、一瞬足を止めたのちに周囲を歩き始める。全長二六・三メートルの超巨大模型は、図体が大きいだけでなく、可能な限り細部にわたって”復元“したものである。製作した側としては、単なる大型プラモデルの展示と思っていただきたくはない。
ミュージアム建設にあたっては、「どこにもない、呉でしかできないオンリーワンの博物館」を作るため、呉の造船技術の歴史を展示するシンボルが必要だった。そこで出たのが一〇分の一「大和」建造計画。潜水調査などを経て図面の製作に六年。一九九七年の立案から完成までには八年の歳月を要した。紆余曲折を経て二〇〇三年に呉市で一〇分の一「大和」建造が決定。初めてづくしの巨大プロジェクトは困難続きであった。ミュージアムの開館期日は決定済み。残された製作期間はわずかに二年(実質一年半)。資料分析やコスト面とともに、時間という大きな壁が立ちはだかる建造となったのである。
戦艦「大和」は、昭和一〇年代の日本の技術レベルの高さを示すと同時に、時代の矛盾と戦争のむなしさを映す鏡でもある。真珠湾攻撃から八日後の一九四一年一二月一六日、世界最大・最強の戦艦として登場しながらも航空戦力が主役となった太平洋戦争を象徴するように、新造時の優雅な佇まいは増設された対空機銃でハリネズミのように変貌し、一九四五年四月七日、沖縄海上特攻の途上、米軍機の猛攻により三〇五六名の人命とともに悲劇的な最期を遂げた。今も三〇〇名近くの乗組員が氏名不詳のままとなっている。
「大和」に関しては情報が極めて厳重に統制され、国民の目から隠されたまま建造され、沈没した。国民の大多数が存在を知ったのは戦後になってから。終戦と同時にほとんどの記録類が灰となった幻の戦艦である。その「大和」を一〇分の一スケールで実際に立体化するためには、全長二六三メートルの巨艦を一センチメートル単位で分析する必要があった。模型の世界では、一ミリメートル単位の精度が要求されるからである。従来の研究蓄積に加え、あらたに収集した「大和」の原図面約二〇〇枚(部分図ばかり)と写真約一〇〇点、海底の「大和」を撮影した六〇時間におよぶ潜水調査映像などをもとにした戦艦「大和」復元は、気の遠くなるような作業となった。
それでも不明箇所は数限りなかった。そこは当事者への聞きとり調査で補うことになった。例えば「大和」の代名詞ともいえる四六センチ三連装主砲塔は、概略図がある程度で、出入口のある背面部の考証は憶測の域を出ないものだった。そこで元「大和」二番主砲砲員だった戸田文男さん(当時、上等水兵)にうかがったところ、「大和が沈没直前、左に大きく傾斜した際に、扉を開けられず砲塔内に取り残された者がいた」という辛い体験を語っていただいた。この証言から背面部出入口のとり付け状態などが明らかになったのである。
実際の製作段階でも、あらたな資料が発見されるたびに、作っては直しを繰り返し、試行錯誤の連続であった。結局最後は損得勘定を度外視した「現代の匠」たちが熱意と気迫で納期に間に合わせたのである。一〇分の一「大和」が形になってくるにしたがい、製作担当者一同は、「大和」が鋼鉄の箱ではなく、三〇〇〇人が生活を営み、生命を託した、生きた建造物であったことを実感するようになっていった。そして二〇〇五年二月一日、一〇分の一「大和」は完成した。戦艦「大和」にかかわった人たちが無数にいたように、一〇分の一スケールで復元した「大和」もまた元乗組員や遺族の方々、建造スタッフほか多くの関係者の想いが込められた艦(ふね)となったのである。
集まる記憶、よみがえる記憶
困難極まる道のりのなかで建造した一〇分の一「大和」は、ミュージアムの来館者に科学技術の発展と戦争の悲劇という「科学技術の光と影」両面のメッセージを送っている。ところが開館後同時に一〇分の一「大和」があらたな資料や情報をもつ歴史の証人ともいうべき人たちとミュージアムとをつなぐ役割も果たしていることを筆者は実感するようになった。ミュージアムの開館と一〇分の一「大和」の展示を契機にあらたに連絡をとることができた元乗組員や遺族の方々ほか関係者はのべ三〇人以上にのぼる。学芸員がいる研究室へ直接連絡をいただくこともあるが、ほとんどの場合、最初に接するのは展示室内各所で解説・案内をしてもらっているボランティアガイドさんたちだ。彼らを経由して学芸員へ情報が集められるのである。
元乗組員の方の場合、最初から「大和」乗艦者であったことを口にする人はまれだ。大半がガイドさんとのやりとりのなかで明らかになる。多くがシルバー世代で構成されるガイドさんたちは、戦争の時代を生き抜いた世代とも年齢的に近く、孫のような学芸員と比べて身構える必要もない。加えてガイドさんたちは話術も巧みで古い話には事欠かない。そうするうちに「じつは自分は『大和』のあの部分におったんですよ」と一〇分の一「大和」のある部分を示されるのである。
このような話は「大和」に限らず、大型資料展示室内にある「零式艦上戦闘機(零戦)」などでも同じである。戦争中、海軍の基地や航空母艦などでパイロット、あるいは航空機整備員をしていた方々の情報をえたのもガイドさん経由だった。そこから連絡をいただいて学芸員が展示室へ駆けつける。ミュージアムへ訪れる歴史の証人の発掘においても、ボランティアガイドさんは多大な貢献をしているのだ。
ミュージアムでは、週末ともなるとおじいちゃん・おばあちゃんから子・孫までの三世代にわたる家族連れが増える。そして歴史展示室内では高齢者が先生となって、戦争中の話を、関連する展示資料をもとに家族に説明している場面に遭遇することが多い。ガイドさんやほかの来館者も含めて、若い世代が生徒になって説明を聞く即席ミニ講座が開かれていることもしばしばである。後でうかがうと、家庭では戦争中の話をしたことはなかったが、ミュージアムの展示を見て話す気になったという方ばかりだった。
「記憶」を「記録」に
終戦から六一年。二七六人いた沖縄海上特攻時の「大和」乗組員生還者も二〇人を割り込んだ。戦争の時代を経験した世代は高齢となり、ここ数年で加速度的に減り続けている。来館者に”生の証言“を聞いていただこうにも、体力的に不安を抱える方がほとんどだ。しかし当事者の話ほど説得力のあるものはない。そこでミュージアムの歴史展示室やライブラリー内には証言者映像コーナーを設け、一九人の方々の話を聞いていただけるようにしている。また、ミュージアム開館後に出会うことができた歴史の証人たちには、後日、ビデオカメラの前でお話をいただくようお願いしている。住所が遠方で、ミュージアムへご足労願うのが難しい場合、カメラと三脚を抱えてこちらから訪問している。お話をうかがうにあたり、筆者に歴史の証人の記憶を引き出す能力が不足していると感じた場合には、館長の戸高一成や統括学芸員の相原謙次をインタビュアーとして巻き込んでの作業となる。企画展で募集、依頼した証言も含めると、こうして撮りためた六〇分ビデオテープは四〇本近くになった。これらは多くの方に見ていただけるよう準備を進めている。
「大和ミュージアム」では、科学技術と歴史の双方を展示することで歴史科学館の名称をとっている。その技術はよく「両刃の剣」と表現される。暮らしを豊かにできるはずのすばらしい技術であっても、人間の使い方次第で悲惨な結果を生む危険性をあわせもつ。一〇分の一「大和」はその象徴であり、戦争の悲惨さ、平和の尊さを我々に語りかける。それゆえミュージアムでは、戦争の時代の「記録」と「記憶」を証言者映像として多くの人たちのために残し、伝えていこうとしている。これは当館に課せられた義務だと筆者は思っている。
ぺー(白)族の民族衣装
女性用(白族)(頭飾り、ベスト、上衣、前掛け、ズボン標本番号H226747~226751)
男性用(白族)(頭飾り、ベスト、上衣、ズボン標本番号H226739~226742)中国
女性用(白族)(頭飾り、ベスト、上衣、前掛け、ズボン標本番号H226747~226751)
男性用(白族)(頭飾り、ベスト、上衣、ズボン標本番号H226739~226742)中国
中国雲南省大理市では一九八〇年代前半以降、観光化が進んだ。服飾はどこの地域にあっても時代を反映して変化を遂げるが、近年、当地のぺー族の青年男女の民族衣装としてこのような衣服が登場した背景には、観光化が大きな要因のひとつとしてある。
以前とは素材がまず違う。かつての生地は木綿が多く、刺繍には絹が用いられたが、現在は化学繊維全盛で、できあいの刺繍テープもよく使われる。扱いやすく、舞台衣装のような鮮やかさのある素材が選ばれる。
それまで女性の大半が民族衣装を毎日着ていた村でも、若い娘が次第に着なくなったのと歩調を合わせて、このような民族衣装が出現した。観光客の接待や歌や踊りを披露する時、あるいは祝祭時の晴れ着として、娘たちがこれを着る。既婚女性でも、この未婚用の衣装を着てみやげものを売っていたりすることがある。若い男性用は踊りを踊る時以外、ほとんど着用されない。
形態も変化を遂げた。頭飾りは男女とも着脱が簡単な帽子式になっている。以前は男性は布をターバン状に巻き、女性は布を何枚も重ね、その上に三つ編みにした髪に赤い毛糸を結んだのをぐるぐると頭に回して留めていた。今や三つ編み部分も黒い毛糸でつくりつけるので、短髪でも、これをかぶればぺー族の娘らしく見える。
上衣、ズボン、ベスト、前掛けからなる女性用の服は、ベストの左肩の飾りボタンがただの飾りになり、前身ごろは開かない。代わりに後ろと脇のファスナーで脱ぎ着する。前掛けは後ろの鍵ホックで留め、その上に蝶形のリボンと二枚の垂れが下がり、ひもで結んでいるように見せている。これだと短時間で誰が着てもさまになる。
このような衣装は観光みやげとしても売られてきた。最近では現地観光ガイドの女性が、ぺー族ではなくても、これを着て団体旅行客を案内するようになった。
以前とは素材がまず違う。かつての生地は木綿が多く、刺繍には絹が用いられたが、現在は化学繊維全盛で、できあいの刺繍テープもよく使われる。扱いやすく、舞台衣装のような鮮やかさのある素材が選ばれる。
それまで女性の大半が民族衣装を毎日着ていた村でも、若い娘が次第に着なくなったのと歩調を合わせて、このような民族衣装が出現した。観光客の接待や歌や踊りを披露する時、あるいは祝祭時の晴れ着として、娘たちがこれを着る。既婚女性でも、この未婚用の衣装を着てみやげものを売っていたりすることがある。若い男性用は踊りを踊る時以外、ほとんど着用されない。
形態も変化を遂げた。頭飾りは男女とも着脱が簡単な帽子式になっている。以前は男性は布をターバン状に巻き、女性は布を何枚も重ね、その上に三つ編みにした髪に赤い毛糸を結んだのをぐるぐると頭に回して留めていた。今や三つ編み部分も黒い毛糸でつくりつけるので、短髪でも、これをかぶればぺー族の娘らしく見える。
上衣、ズボン、ベスト、前掛けからなる女性用の服は、ベストの左肩の飾りボタンがただの飾りになり、前身ごろは開かない。代わりに後ろと脇のファスナーで脱ぎ着する。前掛けは後ろの鍵ホックで留め、その上に蝶形のリボンと二枚の垂れが下がり、ひもで結んでいるように見せている。これだと短時間で誰が着てもさまになる。
このような衣装は観光みやげとしても売られてきた。最近では現地観光ガイドの女性が、ぺー族ではなくても、これを着て団体旅行客を案内するようになった。
さよなら民博
京都大学大学院農学研究科博士課程修了。1976年に民博に着任。助手、助教授を経て教授。総合研究大学院大学文化科学研究科併任教授。アンデスやヒマラヤ、チベットなどの山岳地域で主として先住民による環境利用の方法の調査、研究に従事。著書に『インカの末裔(まつえい)たち』(日本放送出版協会)、『ジャガイモとインカ帝国』(東京大学出版会)、『ラテンアメリカ楽器紀行』(山川出版社)、『雲の上で暮らすーアンデス・ヒマラヤ高地民族の世界』(ナカニシヤ出版)など。
「大阪の万博跡地に博物館ができるらしい」という噂を聞いたのは、たしか一九七四年のことであった。アマゾン川源流域を歩き回っていたとき、そのニュースがどこかから入ってきたのだった。しかし、そのときはまさか自分がその博物館に勤務することになろうとは思ってもみなかった。
その二年後、経緯は省略するが、わたしは民博の館員になった。当時の民族学はまさに上げ潮といった感じで、民博も熱気にあふれていた。梅棹忠夫館長も館員にさかんに檄(げき)をとばしていた。いわく、早く学位をとれ、一年間に一〇〇〇枚の原稿(四〇〇字詰で!)を書け、などなど。しかし、館員はみんな若く、元気にあふれていたせいか、激しい檄も苦にならず、それを励みに開館に向けて全力を投入していた。
わたしも無茶苦茶な忙しさのなかで、自分の力を試しているような気分を味わっていた。それというのも、わたしはもともと京大の大学院で植物学を専攻する大学院生であったが、博士論文に向けての実験の途中で民博に就職したため、二重生活を余儀なくされたからである。すなわち、日中は民博で開館に向けての展示作業や図録作りをしながら、夕方の五時以降は京大に行って夜遅くまで植物の観察を続けていたのである。
そんな生活は結局、民博が開館してから一年後の九月まで続いた。そして、学位論文を提出したあと、すぐにわたしはペルー・アンデスに向かった。学生時代からの夢であった「インカの末裔(まつえい)」たちと暮らしをともにし、彼らの社会や文化を明らかにするためである。じつは、この夢を実現したかったからこそわたしは植物学から民族学に転向したのである。
当時、民博では他分野から民族学に転向したスタッフはめずらしくなかった。そもそも館長自身も動物学から民族学に転じた研究者であった。これは、当時の民族学が他分野の研究者をも引き込むだけの大きな魅力をそなえていたことを物語るのであろう。それから三〇年が経ち、民族学も民博も大きく変わった。とりわけ、民博は同じ研究組織と思えないほどに変わった。そんな民博の今後をこれからは遠くから見守ることにしよう。
では、さよなら民博。
「大阪の万博跡地に博物館ができるらしい」という噂を聞いたのは、たしか一九七四年のことであった。アマゾン川源流域を歩き回っていたとき、そのニュースがどこかから入ってきたのだった。しかし、そのときはまさか自分がその博物館に勤務することになろうとは思ってもみなかった。
その二年後、経緯は省略するが、わたしは民博の館員になった。当時の民族学はまさに上げ潮といった感じで、民博も熱気にあふれていた。梅棹忠夫館長も館員にさかんに檄(げき)をとばしていた。いわく、早く学位をとれ、一年間に一〇〇〇枚の原稿(四〇〇字詰で!)を書け、などなど。しかし、館員はみんな若く、元気にあふれていたせいか、激しい檄も苦にならず、それを励みに開館に向けて全力を投入していた。
わたしも無茶苦茶な忙しさのなかで、自分の力を試しているような気分を味わっていた。それというのも、わたしはもともと京大の大学院で植物学を専攻する大学院生であったが、博士論文に向けての実験の途中で民博に就職したため、二重生活を余儀なくされたからである。すなわち、日中は民博で開館に向けての展示作業や図録作りをしながら、夕方の五時以降は京大に行って夜遅くまで植物の観察を続けていたのである。
そんな生活は結局、民博が開館してから一年後の九月まで続いた。そして、学位論文を提出したあと、すぐにわたしはペルー・アンデスに向かった。学生時代からの夢であった「インカの末裔(まつえい)」たちと暮らしをともにし、彼らの社会や文化を明らかにするためである。じつは、この夢を実現したかったからこそわたしは植物学から民族学に転向したのである。
当時、民博では他分野から民族学に転向したスタッフはめずらしくなかった。そもそも館長自身も動物学から民族学に転じた研究者であった。これは、当時の民族学が他分野の研究者をも引き込むだけの大きな魅力をそなえていたことを物語るのであろう。それから三〇年が経ち、民族学も民博も大きく変わった。とりわけ、民博は同じ研究組織と思えないほどに変わった。そんな民博の今後をこれからは遠くから見守ることにしよう。
では、さよなら民博。
ことは人事より始まる
フランス、パリ第5大学修士課程修了、パリ第10大学にて民族学博士号取得。1976年に民博に着任。総合研究大学院大学文化科学研究科併任教授。専門は映像人類学(民族誌映画)。ヨーロッパの移動民マヌーシュの生活やその信仰、また聖地や巡礼に焦点を当てた映像記録を含め作品数は長編50本余り。著書に『映像人類学の冒険』(せりか書房)、『進化する映像』CD-ROM付(千里文化財団)など。撮影・制作監督を務めた「津軽のカミサマ」が1995年フランス、パリ第14回民族誌映画大会ナヌーク賞(グランプリ)受賞。3月15日から特別展「聖地・巡礼―自分探しの旅へ―」公開。
民博に在籍することになったきっかけ、そして今日のわたしがあるのは、フランスの民族学者で映画制作者のジャン・ルーシュとの出会いがあったからである。
一九七〇年にフランスのトゥール大学大学院に入学し、一年ほどして民族学研究の必要性から動く映像による調査ノートそして映像作品に関心をもつようになった。
毎日のように移動生活を続けるマヌーシュたちの姿をノートに書くだけでは、出来事を思い起こすことは可能であっても、詳細な事実はボンヤリとしたものであった。それをひとつひとつ映像のコマに記録し、再生できるもの、それは映画しかなかった。
当時トゥール大学に芸術社会学の教授として活躍していたジャン・ドヴィニヨーの生徒となったわたしは早速映画と社会科学についてたずねてみると、即座にジャン・ルーシュなる研究者の存在を教えてくれた。しかし彼にコンタクトし、門下生となる方法は教えてくれなかった。
一九七二年春になって、パリへ出るたびにジャン・ルーシュに面会しようと人類博物館の事務所、国際民族誌映画委員会を訪ねた。しかし留守がちなうえに編集作業に入るとまったく人と会わないと聞かされた。数回廊下で会えたのだがいつも、「次回に」と言われ、話ができなかった。
翌年の一九七三年、第九回国際人類学・民族学シカゴ会議での「Urgent Anthropology」のもとで、民族誌映画が重要視され、日本の「映像記録センター」の活動が注目されると、ルーシュからわたしに接触してきた。当時ルーシュはアフリカの人びととしか接しないとうわさされていた。この後にルーシュとしては初めてわたしという東洋人の生徒を指導する教官となった。
ルーシュからマルセル・モースの生徒で多彩な才能を発揮した岡本太郎を紹介され、彼から古きもののなかにこそ新しい芸術表現が見えてくることを教えられた。
さらに、シネマテークフランセーズのアンリ・ラングロワの生徒となって、シネマの歴史と人間の関係から人間の感性の深さを教えられた。当時、博物館のモノの展示と映像展示の組み合わせをどうするかが二〇世紀後半の問題としてクローズアップされてきた。
こうしたなかで、岡本太郎の「太陽の塔」のある万博公園内に、民博が開館することとなり、一九七五年、初代館長であった梅棹忠夫先生が民族学研究をしていてかつ映像制作をしている研究者を求めてわたしにコンタクトしてこられた。結果的に開館の前年、一九七六年秋から赴任することになった。
ジャン・ルーシュは生涯にわたって自分の直弟子とよべる人間を個人的に育てなかった。自分の撮影地や編集室にも他人を入れたがらなかった。しかしわたしはアフリカの撮影地を除いて、パリ市内の撮影や編集にはしばしば立ち会うことを許可された。東洋人として初めてルーシュの助手づとめをすることができたのは、一生の糧となった。
民博に在籍することになったきっかけ、そして今日のわたしがあるのは、フランスの民族学者で映画制作者のジャン・ルーシュとの出会いがあったからである。
一九七〇年にフランスのトゥール大学大学院に入学し、一年ほどして民族学研究の必要性から動く映像による調査ノートそして映像作品に関心をもつようになった。
毎日のように移動生活を続けるマヌーシュたちの姿をノートに書くだけでは、出来事を思い起こすことは可能であっても、詳細な事実はボンヤリとしたものであった。それをひとつひとつ映像のコマに記録し、再生できるもの、それは映画しかなかった。
当時トゥール大学に芸術社会学の教授として活躍していたジャン・ドヴィニヨーの生徒となったわたしは早速映画と社会科学についてたずねてみると、即座にジャン・ルーシュなる研究者の存在を教えてくれた。しかし彼にコンタクトし、門下生となる方法は教えてくれなかった。
一九七二年春になって、パリへ出るたびにジャン・ルーシュに面会しようと人類博物館の事務所、国際民族誌映画委員会を訪ねた。しかし留守がちなうえに編集作業に入るとまったく人と会わないと聞かされた。数回廊下で会えたのだがいつも、「次回に」と言われ、話ができなかった。
翌年の一九七三年、第九回国際人類学・民族学シカゴ会議での「Urgent Anthropology」のもとで、民族誌映画が重要視され、日本の「映像記録センター」の活動が注目されると、ルーシュからわたしに接触してきた。当時ルーシュはアフリカの人びととしか接しないとうわさされていた。この後にルーシュとしては初めてわたしという東洋人の生徒を指導する教官となった。
ルーシュからマルセル・モースの生徒で多彩な才能を発揮した岡本太郎を紹介され、彼から古きもののなかにこそ新しい芸術表現が見えてくることを教えられた。
さらに、シネマテークフランセーズのアンリ・ラングロワの生徒となって、シネマの歴史と人間の関係から人間の感性の深さを教えられた。当時、博物館のモノの展示と映像展示の組み合わせをどうするかが二〇世紀後半の問題としてクローズアップされてきた。
こうしたなかで、岡本太郎の「太陽の塔」のある万博公園内に、民博が開館することとなり、一九七五年、初代館長であった梅棹忠夫先生が民族学研究をしていてかつ映像制作をしている研究者を求めてわたしにコンタクトしてこられた。結果的に開館の前年、一九七六年秋から赴任することになった。
ジャン・ルーシュは生涯にわたって自分の直弟子とよべる人間を個人的に育てなかった。自分の撮影地や編集室にも他人を入れたがらなかった。しかしわたしはアフリカの撮影地を除いて、パリ市内の撮影や編集にはしばしば立ち会うことを許可された。東洋人として初めてルーシュの助手づとめをすることができたのは、一生の糧となった。
日本のいろいろな学び方
流行と関係なく学ぶ日本
カタリナさん(仮名)は東京のある大学で学ぶドイツ人留学生である。日本の大学院で修士号を取得することを目指し、現在、猛勉強中である。日本に来る前からドイツで日本語や日本文化を学んでいた。ドイツでは「日本学」(Japanologie)を専攻していた。だが彼女が日本学を学ぶようになったきっかけは少々変わっている。
彼女はドイツで大学に進学する以前、昼間は保育園で働きながら、夜間高校に通っていた。高校を卒業し、大学に進学しようと考えたときに、インターネットでいろいろな大学の授業内容を調べたそうである。そしてなぜか、日本学を専攻することに決め、ハイデルベルク大学に進学した。日本学を専攻しようと思った理由は「日本について何も知らなかったけれど、面白そうだと思ったから」。
ドイツでも日本学や日本語を勉強する学生は少なくない。ハイデルベルク大学にも何人かの学生が進学してきた。そんな学生の多くは、大学進学以前から日本文化に興味をもち、日本学を専攻する。なかでも日本のアニメやマンガはドイツでも人気がある。そうしたアニメ好きやマンガ好きの若者が日本学の専攻を希望するのである。またドイツの大学では、学生は主専攻と副専攻を決め、専門分野をふたつ勉強することが求められている。そのため経済学を主専攻とする学生のなかにも、日本や東アジアの経済発展を勉強するために、副専攻を日本学にする者が多い。だが彼女は日本のアニメもマンガについても全然知らず、日本経済にも特別な興味をもっていない。サブ・カルチャーと経済発展は海外における現代日本のイメージを代表するものであるが、彼女はそうした「流行の」日本イメージに流されずに日本研究を志したのである。
関西弁についての論文執筆
カタリナさんは大学では日本語、日本文学、日本の歴史等を学んだ。勉強は楽しかったが、特に日本学に一生打ち込もうとしていたわけではない。それでも、大学三年生になると、彼女に日本に留学するチャンスが訪れた。ドイツではハイデルベルク大学以外に、チュービンゲン大学にも日本学の専攻がある。このチュービンゲン大学は毎年、自校の学生を日本に留学させるが、このとき、たまたま定員が満たされなかったため、ハイデルベルク大学の学生の彼女がその留学生枠に入ることが可能になったのである。
彼女はチュービンゲン大学の学生たちとともに、京都のある大学でおもに日本語を勉強することになった。彼女が日本に来たのはこれが初めてであった。しかもドイツでは日本食を食べたことすらなかった。じつは彼女が初めて食べた日本料理は、日本に来る際に乗った飛行機の機内食で出されたソバだった。
京都で彼女はいろいろな日本の文化に接することができた。そのなかのひとつは、以前から興味をもっていた弓道である。弓道を習うのは楽しかったが、困難なこともあった。弓道の技術や弓道用語などが、難しい。だが、特に大変だったのは、弓道の練習中に先生が話す関西弁がなかなか理解できなかったことである。先生が話すことは、弓道教室の先輩が「普通の」日本語に訳してくれた。彼女がハイデルベルク大学で習った日本語は、いわゆる標準語であった。だが京都での暮らしは、同時に関西弁の世界で暮らすことを意味していたのである。
こうして彼女は少しずつ関西弁を覚えていった。例えば、「高(たこ)うなる」という関西弁を初めて聞いたときには、「たこう」という名詞と「なる」という動詞のふたつからできた表現だと思い、「たこう」という語を辞書で引いて調べてみたが、それらしい項目は載っていなかった。それで知り合いの先生に聞いて、初めてこれは関西特有の表現だということがわかった。
京都に五ヵ月住んだ後、彼女はドイツに帰国し、日本学を勉強し続けることを決意した。大学もハイデルベルクからチュービンゲンに変更した。帰国後、彼女はチュービンゲン大学の日本学の授業で、京都で覚えた関西弁について発表する機会をえた。発表は好評で、指導教授は京都に留学する他の学生のために、彼女に何度も同じ発表をすることを求めた。さらに関西弁について卒業論文を書くことをアドバイスした。こうして日本の方言についていろいろと調べ、京都弁や大阪弁の違いの比較研究をおこない、論文としてまとめた。
再び、日本へ留学
これを機にチュービンゲン大学の修士課程に進学し、さらに日本の大学で国費留学生として勉強することになった。彼女が現在留学している日本の大学では、留学生は世界各地からきており、中国、インドネシア、フィリピン、韓国、フランスなど、さまざまな国の学生とともに勉強している。ドイツで日本学を勉強していたときには、そのように世界各地の学生と一緒に勉強することはなかった。だが彼女にとっては、世界各地の学生とともに日本語を勉強する状態は別に特別なものではないようだ。むしろ、それぞれ出身国は異なるが、日本語や日本文化を勉強したいという目的は皆同じであり、自分の出身国が懐かしいといったことや、日本語を学ぶうえでの難しさ、外国人として日本で暮らすうえでの困難など、日本人に相談してもなかなか理解してもらえない問題を共有している。例えば、日本の大学の授業は、当たり前ではあるが、日本人学生のためのものである。だが外国人留学生は、日本語に不慣れで日本文化の背景を知らないために、完全に授業を理解できないこともある。こんな時、他の留学生と話し合うことで、皆同じような問題を抱えていて、別に自分の能力に問題があるわけではないことを確認することができる。このような問題は、なかなか日本人には理解してもらえないようである。
彼女は現在、日本とドイツの戦前の教育を比較研究している。日本の大学で教育学のゼミに所属し、勉強しながら気づいたことがいくつかある。そのうちのひとつは、日本の大学では学生の研究テーマが必ずしも所属する専攻と一致するわけではなく、むしろそれが普通だということである。彼女のように日本とドイツの教育史の比較研究、というオーソドックスなテーマだけではなく、教育以外の日本の社会問題や流行文化等をテーマとしてとり上げる学生もいる。このような研究テーマの多様性は、ドイツと日本の大学の違いのひとつであると彼女はいう。また、日本とドイツの第二次世界大戦に対する認識の違いにも驚かされている。ドイツでは第二次世界大戦に対する学生の意識は現在でも高いが、日本の学生は第二次世界大戦のことについてあまり知らず、問題意識も高くない。
カタリナさんに限らず、日本で暮らし学ぶ外国人は、皆、それぞれ異なった背景と、共通した問題を抱えている。日本に留学し生活する外国人は、今後も増え続けるだろう。そして留学生たちはそれぞれの立場や興味にしたがって、さまざまな方法で日本語や日本文化を学んでゆくことになるだろう。日本をどのように学ぶのか、そして日本でどのように暮らすのか、その方法もこれからどんどん多様化してゆくのだろう。
カタリナさん(仮名)は東京のある大学で学ぶドイツ人留学生である。日本の大学院で修士号を取得することを目指し、現在、猛勉強中である。日本に来る前からドイツで日本語や日本文化を学んでいた。ドイツでは「日本学」(Japanologie)を専攻していた。だが彼女が日本学を学ぶようになったきっかけは少々変わっている。
彼女はドイツで大学に進学する以前、昼間は保育園で働きながら、夜間高校に通っていた。高校を卒業し、大学に進学しようと考えたときに、インターネットでいろいろな大学の授業内容を調べたそうである。そしてなぜか、日本学を専攻することに決め、ハイデルベルク大学に進学した。日本学を専攻しようと思った理由は「日本について何も知らなかったけれど、面白そうだと思ったから」。
ドイツでも日本学や日本語を勉強する学生は少なくない。ハイデルベルク大学にも何人かの学生が進学してきた。そんな学生の多くは、大学進学以前から日本文化に興味をもち、日本学を専攻する。なかでも日本のアニメやマンガはドイツでも人気がある。そうしたアニメ好きやマンガ好きの若者が日本学の専攻を希望するのである。またドイツの大学では、学生は主専攻と副専攻を決め、専門分野をふたつ勉強することが求められている。そのため経済学を主専攻とする学生のなかにも、日本や東アジアの経済発展を勉強するために、副専攻を日本学にする者が多い。だが彼女は日本のアニメもマンガについても全然知らず、日本経済にも特別な興味をもっていない。サブ・カルチャーと経済発展は海外における現代日本のイメージを代表するものであるが、彼女はそうした「流行の」日本イメージに流されずに日本研究を志したのである。
関西弁についての論文執筆
カタリナさんは大学では日本語、日本文学、日本の歴史等を学んだ。勉強は楽しかったが、特に日本学に一生打ち込もうとしていたわけではない。それでも、大学三年生になると、彼女に日本に留学するチャンスが訪れた。ドイツではハイデルベルク大学以外に、チュービンゲン大学にも日本学の専攻がある。このチュービンゲン大学は毎年、自校の学生を日本に留学させるが、このとき、たまたま定員が満たされなかったため、ハイデルベルク大学の学生の彼女がその留学生枠に入ることが可能になったのである。
彼女はチュービンゲン大学の学生たちとともに、京都のある大学でおもに日本語を勉強することになった。彼女が日本に来たのはこれが初めてであった。しかもドイツでは日本食を食べたことすらなかった。じつは彼女が初めて食べた日本料理は、日本に来る際に乗った飛行機の機内食で出されたソバだった。
京都で彼女はいろいろな日本の文化に接することができた。そのなかのひとつは、以前から興味をもっていた弓道である。弓道を習うのは楽しかったが、困難なこともあった。弓道の技術や弓道用語などが、難しい。だが、特に大変だったのは、弓道の練習中に先生が話す関西弁がなかなか理解できなかったことである。先生が話すことは、弓道教室の先輩が「普通の」日本語に訳してくれた。彼女がハイデルベルク大学で習った日本語は、いわゆる標準語であった。だが京都での暮らしは、同時に関西弁の世界で暮らすことを意味していたのである。
こうして彼女は少しずつ関西弁を覚えていった。例えば、「高(たこ)うなる」という関西弁を初めて聞いたときには、「たこう」という名詞と「なる」という動詞のふたつからできた表現だと思い、「たこう」という語を辞書で引いて調べてみたが、それらしい項目は載っていなかった。それで知り合いの先生に聞いて、初めてこれは関西特有の表現だということがわかった。
京都に五ヵ月住んだ後、彼女はドイツに帰国し、日本学を勉強し続けることを決意した。大学もハイデルベルクからチュービンゲンに変更した。帰国後、彼女はチュービンゲン大学の日本学の授業で、京都で覚えた関西弁について発表する機会をえた。発表は好評で、指導教授は京都に留学する他の学生のために、彼女に何度も同じ発表をすることを求めた。さらに関西弁について卒業論文を書くことをアドバイスした。こうして日本の方言についていろいろと調べ、京都弁や大阪弁の違いの比較研究をおこない、論文としてまとめた。
再び、日本へ留学
これを機にチュービンゲン大学の修士課程に進学し、さらに日本の大学で国費留学生として勉強することになった。彼女が現在留学している日本の大学では、留学生は世界各地からきており、中国、インドネシア、フィリピン、韓国、フランスなど、さまざまな国の学生とともに勉強している。ドイツで日本学を勉強していたときには、そのように世界各地の学生と一緒に勉強することはなかった。だが彼女にとっては、世界各地の学生とともに日本語を勉強する状態は別に特別なものではないようだ。むしろ、それぞれ出身国は異なるが、日本語や日本文化を勉強したいという目的は皆同じであり、自分の出身国が懐かしいといったことや、日本語を学ぶうえでの難しさ、外国人として日本で暮らすうえでの困難など、日本人に相談してもなかなか理解してもらえない問題を共有している。例えば、日本の大学の授業は、当たり前ではあるが、日本人学生のためのものである。だが外国人留学生は、日本語に不慣れで日本文化の背景を知らないために、完全に授業を理解できないこともある。こんな時、他の留学生と話し合うことで、皆同じような問題を抱えていて、別に自分の能力に問題があるわけではないことを確認することができる。このような問題は、なかなか日本人には理解してもらえないようである。
彼女は現在、日本とドイツの戦前の教育を比較研究している。日本の大学で教育学のゼミに所属し、勉強しながら気づいたことがいくつかある。そのうちのひとつは、日本の大学では学生の研究テーマが必ずしも所属する専攻と一致するわけではなく、むしろそれが普通だということである。彼女のように日本とドイツの教育史の比較研究、というオーソドックスなテーマだけではなく、教育以外の日本の社会問題や流行文化等をテーマとしてとり上げる学生もいる。このような研究テーマの多様性は、ドイツと日本の大学の違いのひとつであると彼女はいう。また、日本とドイツの第二次世界大戦に対する認識の違いにも驚かされている。ドイツでは第二次世界大戦に対する学生の意識は現在でも高いが、日本の学生は第二次世界大戦のことについてあまり知らず、問題意識も高くない。
カタリナさんに限らず、日本で暮らし学ぶ外国人は、皆、それぞれ異なった背景と、共通した問題を抱えている。日本に留学し生活する外国人は、今後も増え続けるだろう。そして留学生たちはそれぞれの立場や興味にしたがって、さまざまな方法で日本語や日本文化を学んでゆくことになるだろう。日本をどのように学ぶのか、そして日本でどのように暮らすのか、その方法もこれからどんどん多様化してゆくのだろう。
バタックのタイコ
バラエティに富んだ楽器
タイコは、世界でもっとも広く見られる楽器のひとつである。しかし、その形や奏法、そしてそこから生み出されるリズムは非常に多様であり、世界の音楽の共通性と多様性を体現する楽器だと言ってもよいだろう。タイコは、数年後のリニューアルを目指すみんぱくの音楽展示におけるテーマの候補のひとつともなっている。わたしは、リニューアルの準備のため、二〇〇五年七月、インドネシアのスマトラ島を訪れた。
北スマトラ州に住むバタック人は、トバ、カロ、パクパク、シマルングン、アンコラ、マンダイリンなど、いくつかの集団にわかれており、それぞれがタイコを中心とする合奏音楽をもっている。わたしは北スマトラ大学のリタオニ・フタジュルさんの協力をえて、これらさまざまな合奏音楽に使われる楽器を収集しながら映像取材もおこなった。
バタックの人びとのタイコは、集団により大きいものから小さなものまでバラエティに富んでいる。もっとも大きなタイコを使うのは、マンダイリンの人びとだろう。ゴルダン・サンビランとよばれる彼らの合奏は、九つの円筒形の胴をもったタイコがメインになっている(写真1)。いちばん大きいものは、一・五メートルほどの長さがあり、小さいものでも一メートル以上になる。それにサルネとよばれるオーボエ系の楽器一、小型のゴングが三か四、中型ゴングが二、シンバル一で演奏される(写真2)。
それに対して、もっとも小さなタイコを使うのはカロの人びとだろう。グンダン・リマ・サダラネン、あるいはグンダン・サルネとよばれる合奏には、グンダンとよばれる四〇センチメートル程度の長さの細長いタイコ一対と、サルネ、小ゴング一、大ゴング一が用いられる。一対のグンダンは、それぞれ母(インドゥン)と子(アナック)とよばれ、子のグンダンには、グラントゥンとよばれるさらに小さいタイコが結び付けられている(写真3)。ゴルダン・サンビランの音は、腹に響いてくるが、グンダン・リマ・サダラネンの音は、かわいらしいと形容したくなるような音だ。しかし、演奏が始まるとかなり激しいリズムを打ち出し、迫力があるのに驚く。
文化に根ざす存在感
これらのタイコ合奏は、バタック人の古くからの信仰にささえられている。たとえば、ゴルダン・サンビランは、結婚式や葬式でも演奏されるが、古くは、祖先の霊を呼び、霊媒を通じてそのことばを聞くために演奏されたという。今でも、演奏時に憑依(ひょうい)がおこることはまれではないそうだ。そのため、ゴルダン・サンビランを演奏する場合には、必ずスイギュウを犠牲にして、霊に対してそなえなければならない。
現在、バタック人の多くはキリスト教徒であり、少数派ではあるが、イスラム教徒もいる。そんななか、トバの古来からの信仰を守ることを信条とするパルマリンとよばれる組織がある。彼らは、ムラ・ジャディ・ナ・ボロンをはじめとするバタックの神々に対して祈りをささげる。その祈りには音楽が欠かせない。というよりは、音楽自体も神にささげる祈りとみなされている。そのときに用いられる合奏がゴンダン・サバングナンである。タガニンとよばれる五つのタイコとオダックとよばれるタイコのセット、ゴルダンとよばれる少し大きめのタイコ、大型のサルネであるサルネ・ボロン、オグンとよばれる四つのゴング、そしてヘセック・ヘセックとよばれるガラスのビンからなる(写真4)。
パルマリンの儀礼においては、このゴンダン・サバングナンに合わせて、手を自分の前であわせ、身体を上下させながら手を前後に軽くふるトルトルとよばれる一種の踊りをおこなう(写真5)。祈りをささげる相手により、それぞれ祈りのことばがあるように、演奏する曲も祈りをささげる対象によって決まっている。リーダーが、それぞれの神にささげる祈りのことばを唱えると、それに合わせて音楽家は適切な曲を選んで演奏をはじめる。すると人びとはこのトルトルを一緒におこなうのである。
タイコがきざむリズム、それに合わせて身体を動かす人びと。モノの収集と並行して、撮影したビデオによって、バタックの人びとの文化におけるタイコの存在感を、展示をとおして少しでも伝えるために、これからアイディアをしぼっていきたいと考えている。
タイコは、世界でもっとも広く見られる楽器のひとつである。しかし、その形や奏法、そしてそこから生み出されるリズムは非常に多様であり、世界の音楽の共通性と多様性を体現する楽器だと言ってもよいだろう。タイコは、数年後のリニューアルを目指すみんぱくの音楽展示におけるテーマの候補のひとつともなっている。わたしは、リニューアルの準備のため、二〇〇五年七月、インドネシアのスマトラ島を訪れた。
北スマトラ州に住むバタック人は、トバ、カロ、パクパク、シマルングン、アンコラ、マンダイリンなど、いくつかの集団にわかれており、それぞれがタイコを中心とする合奏音楽をもっている。わたしは北スマトラ大学のリタオニ・フタジュルさんの協力をえて、これらさまざまな合奏音楽に使われる楽器を収集しながら映像取材もおこなった。
バタックの人びとのタイコは、集団により大きいものから小さなものまでバラエティに富んでいる。もっとも大きなタイコを使うのは、マンダイリンの人びとだろう。ゴルダン・サンビランとよばれる彼らの合奏は、九つの円筒形の胴をもったタイコがメインになっている(写真1)。いちばん大きいものは、一・五メートルほどの長さがあり、小さいものでも一メートル以上になる。それにサルネとよばれるオーボエ系の楽器一、小型のゴングが三か四、中型ゴングが二、シンバル一で演奏される(写真2)。
それに対して、もっとも小さなタイコを使うのはカロの人びとだろう。グンダン・リマ・サダラネン、あるいはグンダン・サルネとよばれる合奏には、グンダンとよばれる四〇センチメートル程度の長さの細長いタイコ一対と、サルネ、小ゴング一、大ゴング一が用いられる。一対のグンダンは、それぞれ母(インドゥン)と子(アナック)とよばれ、子のグンダンには、グラントゥンとよばれるさらに小さいタイコが結び付けられている(写真3)。ゴルダン・サンビランの音は、腹に響いてくるが、グンダン・リマ・サダラネンの音は、かわいらしいと形容したくなるような音だ。しかし、演奏が始まるとかなり激しいリズムを打ち出し、迫力があるのに驚く。
文化に根ざす存在感
これらのタイコ合奏は、バタック人の古くからの信仰にささえられている。たとえば、ゴルダン・サンビランは、結婚式や葬式でも演奏されるが、古くは、祖先の霊を呼び、霊媒を通じてそのことばを聞くために演奏されたという。今でも、演奏時に憑依(ひょうい)がおこることはまれではないそうだ。そのため、ゴルダン・サンビランを演奏する場合には、必ずスイギュウを犠牲にして、霊に対してそなえなければならない。
現在、バタック人の多くはキリスト教徒であり、少数派ではあるが、イスラム教徒もいる。そんななか、トバの古来からの信仰を守ることを信条とするパルマリンとよばれる組織がある。彼らは、ムラ・ジャディ・ナ・ボロンをはじめとするバタックの神々に対して祈りをささげる。その祈りには音楽が欠かせない。というよりは、音楽自体も神にささげる祈りとみなされている。そのときに用いられる合奏がゴンダン・サバングナンである。タガニンとよばれる五つのタイコとオダックとよばれるタイコのセット、ゴルダンとよばれる少し大きめのタイコ、大型のサルネであるサルネ・ボロン、オグンとよばれる四つのゴング、そしてヘセック・ヘセックとよばれるガラスのビンからなる(写真4)。
パルマリンの儀礼においては、このゴンダン・サバングナンに合わせて、手を自分の前であわせ、身体を上下させながら手を前後に軽くふるトルトルとよばれる一種の踊りをおこなう(写真5)。祈りをささげる相手により、それぞれ祈りのことばがあるように、演奏する曲も祈りをささげる対象によって決まっている。リーダーが、それぞれの神にささげる祈りのことばを唱えると、それに合わせて音楽家は適切な曲を選んで演奏をはじめる。すると人びとはこのトルトルを一緒におこなうのである。
タイコがきざむリズム、それに合わせて身体を動かす人びと。モノの収集と並行して、撮影したビデオによって、バタックの人びとの文化におけるタイコの存在感を、展示をとおして少しでも伝えるために、これからアイディアをしぼっていきたいと考えている。
トナカイと生きる
稲村 哲也(いなむら てつや) 愛知県立大学教授
トナカイ飼養発祥の地
モンゴル最北端フブスグル県に「ツァータン」とよばれるトナカイ遊牧民がいる。遊牧生活を続けるのは三〇家族ほどに過ぎない。しかし、そこはトナカイ遊牧の最南端、また山地タイガ帯の最南端、草原と接する地域であり、「トナカイ飼養が草原の牧畜に影響されて成立した」との説によれば、トナカイ飼養発祥の地である。またツァータンたちの生活は、タイガのトナカイ遊牧の形態をよく維持している。
筆者が最初にかの地を訪ねたのは一九九三年九月。モンゴル人地理学者とともに、ウランバートルからロシア製ジープを走らせ、北端のソム(郡)定住区まで四日かかった。国境警備隊の宿舎に泊めてもらい、翌朝、ウマを用意し国境警備兵の案内で出発した。森のなかを駆け、湿地を抜け、川を渡り、山道を上下し、休まず進んだが、途中で陽が落ちてしまった。進路をウマに委(ゆだ)ねてなおも進むと、イヌの吼え声が聞こえ、暗闇に天幕のシルエットが浮かんだ。なかに招き入れられると、ツェウェルさんというおばあさんと娘さんがトナカイ乳入りのお茶を出してくれた。それが美味しくて何杯もお代わりした。トナカイの毛皮の上に疲れた身を横たえると、円錐形天幕の頂点の隙間から雪が降り込んでいた。翌朝、天幕の外に白銀の世界が広がっていた。雪原の起伏の向こうからトナカイたちがあらわれた。トナカイに騎乗した息子さんが巧みに群れを追ってくる。心のなかでおもわず「これだっ」と叫んでいた。それから筆者は、ツェウェルさん一家を毎年のように訪問し、いつしか一〇回を数えた。
彼らは家族単位で天幕に住み、一年をとおして移動をする遊牧生活を続けてきた。夏は標高二三〇〇メートルほどの冷涼な高原(氷食谷)に比較的集まり、冬は標高一八〇〇メートルほどの森のなかに分散する。食糧確保のためクマ、シカの猟、また、現金をえるため毛皮獣のクロテン、リスの猟もしてきた。
悠久のときを過ごしてきたかに見えたツァータンたちは、じつは、激動の時代をからくも生きぬいてきたのだった。もともと、西に接するトゥバ共和国(現在ロシア連邦に属す)とモンゴルの国境地域で移動していた彼らは、一九四四年、トゥバがソ連に併合された後、夜陰に紛れて国境を越えてきた。コルホーズのための家畜共有化、対ドイツ戦のための家畜徴用、子どもたちの学校の寄宿舎での病気蔓延(まんえん)などがその理由だった。
ようやく定着したモンゴルでも一九五〇年代末、コルホーズに倣(なら)ったネグデル(農牧組合)が実施され、トナカイが共有化され、それを請け負って飼うようになった。給料が支給され、小麦粉などの食糧が安定的に供給され、狩猟への依存度が減り、トナカイ飼養数が増加して一〇〇〇頭を超えた。一方、林業や漁業が開発され、定住区に住む人も増えた。
適応の道を模索
一九九〇年、モンゴルは民主主義、市場経済に国家体制を転換した。トナカイが私有化されたが、給料はなくなり、医療、獣医、流通、情報などすべての生活支援システムが無くなった。生活に窮したツァータンのトナカイ個体数は数年で半数に減ってしまった。一方、森の民の小さな社会が突然、秘境中の秘境としての国際観光スポットになってしまった。幸い、観光は夏の短い期間に限られる。ツァータンのある者は観光客へのみやげ物を考案し、収入をえるようになった。また、ウシやヒツジを飼う草原の遊牧民と協力し合い、草原家畜を所有して乳製品や現金収入をえるなど、新たな適応の道を模索している。
ツェウェルおばあさんは数年前に亡くなったが、娘のハンダーさんが結婚して子どもができた。国際関係と国家体制の変革に翻弄(ほんろう)されながら、伝統を守ってきたツァータンたちは、これからも森を愛し、トナカイとともに生きる生活を続けてくれるだろうか。
モンゴル最北端フブスグル県に「ツァータン」とよばれるトナカイ遊牧民がいる。遊牧生活を続けるのは三〇家族ほどに過ぎない。しかし、そこはトナカイ遊牧の最南端、また山地タイガ帯の最南端、草原と接する地域であり、「トナカイ飼養が草原の牧畜に影響されて成立した」との説によれば、トナカイ飼養発祥の地である。またツァータンたちの生活は、タイガのトナカイ遊牧の形態をよく維持している。
筆者が最初にかの地を訪ねたのは一九九三年九月。モンゴル人地理学者とともに、ウランバートルからロシア製ジープを走らせ、北端のソム(郡)定住区まで四日かかった。国境警備隊の宿舎に泊めてもらい、翌朝、ウマを用意し国境警備兵の案内で出発した。森のなかを駆け、湿地を抜け、川を渡り、山道を上下し、休まず進んだが、途中で陽が落ちてしまった。進路をウマに委(ゆだ)ねてなおも進むと、イヌの吼え声が聞こえ、暗闇に天幕のシルエットが浮かんだ。なかに招き入れられると、ツェウェルさんというおばあさんと娘さんがトナカイ乳入りのお茶を出してくれた。それが美味しくて何杯もお代わりした。トナカイの毛皮の上に疲れた身を横たえると、円錐形天幕の頂点の隙間から雪が降り込んでいた。翌朝、天幕の外に白銀の世界が広がっていた。雪原の起伏の向こうからトナカイたちがあらわれた。トナカイに騎乗した息子さんが巧みに群れを追ってくる。心のなかでおもわず「これだっ」と叫んでいた。それから筆者は、ツェウェルさん一家を毎年のように訪問し、いつしか一〇回を数えた。
彼らは家族単位で天幕に住み、一年をとおして移動をする遊牧生活を続けてきた。夏は標高二三〇〇メートルほどの冷涼な高原(氷食谷)に比較的集まり、冬は標高一八〇〇メートルほどの森のなかに分散する。食糧確保のためクマ、シカの猟、また、現金をえるため毛皮獣のクロテン、リスの猟もしてきた。
悠久のときを過ごしてきたかに見えたツァータンたちは、じつは、激動の時代をからくも生きぬいてきたのだった。もともと、西に接するトゥバ共和国(現在ロシア連邦に属す)とモンゴルの国境地域で移動していた彼らは、一九四四年、トゥバがソ連に併合された後、夜陰に紛れて国境を越えてきた。コルホーズのための家畜共有化、対ドイツ戦のための家畜徴用、子どもたちの学校の寄宿舎での病気蔓延(まんえん)などがその理由だった。
ようやく定着したモンゴルでも一九五〇年代末、コルホーズに倣(なら)ったネグデル(農牧組合)が実施され、トナカイが共有化され、それを請け負って飼うようになった。給料が支給され、小麦粉などの食糧が安定的に供給され、狩猟への依存度が減り、トナカイ飼養数が増加して一〇〇〇頭を超えた。一方、林業や漁業が開発され、定住区に住む人も増えた。
適応の道を模索
一九九〇年、モンゴルは民主主義、市場経済に国家体制を転換した。トナカイが私有化されたが、給料はなくなり、医療、獣医、流通、情報などすべての生活支援システムが無くなった。生活に窮したツァータンのトナカイ個体数は数年で半数に減ってしまった。一方、森の民の小さな社会が突然、秘境中の秘境としての国際観光スポットになってしまった。幸い、観光は夏の短い期間に限られる。ツァータンのある者は観光客へのみやげ物を考案し、収入をえるようになった。また、ウシやヒツジを飼う草原の遊牧民と協力し合い、草原家畜を所有して乳製品や現金収入をえるなど、新たな適応の道を模索している。
ツェウェルおばあさんは数年前に亡くなったが、娘のハンダーさんが結婚して子どもができた。国際関係と国家体制の変革に翻弄(ほんろう)されながら、伝統を守ってきたツァータンたちは、これからも森を愛し、トナカイとともに生きる生活を続けてくれるだろうか。
トナカイ(学名:Rangifer tarandus)
スカンジナビア半島からシベリア、グリーンランド、北米のタイガ帯、ツンドラ帯、北極圏にかけて生息する。オス、メスともに角をもつ。角は春に生え始め、大きな枝分かれした袋角に生長する。袋角の表面には皮膚があり、そこから体温を放出する。大きな枝角は表面積を増やしており、夏に効率よく体温を放出する。秋から皮膚を落として骨角になり、冬に角が脱落する。また、寒さや雪に適応した厚い毛皮や横に広がる蹄(ひづめ)をもつ。夏は草や木の葉を食べ、冬は雪をかきわけてコケなどを食べる。
スカンジナビア半島からシベリア、グリーンランド、北米のタイガ帯、ツンドラ帯、北極圏にかけて生息する。オス、メスともに角をもつ。角は春に生え始め、大きな枝分かれした袋角に生長する。袋角の表面には皮膚があり、そこから体温を放出する。大きな枝角は表面積を増やしており、夏に効率よく体温を放出する。秋から皮膚を落として骨角になり、冬に角が脱落する。また、寒さや雪に適応した厚い毛皮や横に広がる蹄(ひづめ)をもつ。夏は草や木の葉を食べ、冬は雪をかきわけてコケなどを食べる。
今日もスダコの車窓から
高野 さやか(たかの さやか) 東京大学大学院総合文化研究科
庶民の足
インドネシア・スマトラ島のメダン市には、たくさんの「スダコ」が道路を走っている。
スダコとは、ここでは小型バスのことだ。正式なインドネシア語でないようだし、他の地域では通じない。何故そうよぶのか地元の人に聞いてみても、スダコの意味はよくわからない、というのが正直なところらしい。
道路に出れば、色、デザインさまざまなスダコが目に付く。外装は会社によって異なるが、運転席の内装や前後の窓は、運転手の好みで飾り付けてあり、日本の長距離トラックを思わせる。急発進・急停車は当たり前。しきりにクラクションを鳴らし、接触ぎりぎりのところをすり抜けていく。近年手ごろな価格の車が登場し、交通量が著しく増加しているメダン市で、乗用車やバイクのドライバーたちはスダコに気を使わないと運転できない。しょっちゅう起きる停電で信号が消えているときも、主導権を握るのはスダコたちだ。
公共交通機関の整備が不十分なので、庶民の足として大活躍している。乗客は道端で待っていて、外装と番号で目当てのスダコを見わけ、合図して止める。停留所や時刻表はない。後部座席は向かい合ったベンチ状で、ひざを突き合わせて座る。かなり揺れるので、読書や居眠りをしている人はまず見かけない。降りたいところで運転手に声をかけて知らせ、前にまわって料金を手渡す。市内なら、一人二五〇〇ルピア(約三五円)だ。
今日は何人乗せたかな?
スダコの運転手にとって最大の関心事は、いかに満員に近い状態で走るか、である。通りの反対側からでも、合図に気が付くと、ずっと待っている。乗っている車がいきなり止まるので、降りる人もいないのに、と不思議に思っていると、遠くからゆっくり歩いてくるお客さんがいることに気が付く。市場など人の集まるところでは、しばらく客待ち停車をする。どう見ても満員でも、いいから乗れ乗れ、と誘うので、乗車拒否をするのは乗客の方だ。
助手席に乗り込むと、スダコに何が必要で、何が必要でないか、はっきりと見てとることができる。運転席は改造が繰り返され、設備は最小限。速度計などの計器はどれも動いていない。内装は金属板がむきだしになっている。助手席の窓は、運賃の受け渡しのため常に開けておくので、ドアも外側からだけ開けばよい。
いいかげんなようだが、細かいところには独自の工夫がある。微妙なハンドルさばきがとても大事なので、ハンドルはひとまわり小さなものに取り替えられている。ウィンカーのレバーはクラクションにつながっていて、歩行者の注意を引く際などに反射的に使われる。乗客の足元にはスペアタイヤ。釣り銭はダッシュボードの上に並べ、赤信号のあいだに紙幣を整理してポケットにしまう。
乗客の数が、運転手の収入に直接結び付いている。会社には毎日決められた額を車の使用料として支払えばいいからだ。営業は運転手本位。乗客を乗せたまま、ガソリンスタンドにも行く。給油が終わるまで、みんな静かに待っている。慣れてくると、停留所と運行時間に拘束されている日本のバスが、つれなく思えることさえある。
一〇〇〇ルピア札を握りしめて
別れ際に「スダコで帰る」と言うと、「気を付けてね」と言われることがある。「スダコに乗ったことなんてないわ」と言う人も多い。用心のため、いつも乗る前には運賃をポケットに準備しておき、財布や携帯電話は出さないようにする。メダン市の若者にとっても、自分のバイクなり車なりを手に入れてスダコから卒業することは、ひとつの目標である。いつまでもスダコに乗っているのは、かっこ悪いことでもあり、不便でもある。
わたしも、ほかの交通手段を確保すべきだろうか、とも考えた。ぎゅうぎゅうに詰め込まれると、さすがに息苦しい。運転手付きの車は望むべくもないが、バイクタクシーを月極めで雇うという方法だってある。だが、スダコにはスダコのよさがあるのだ。二年間で運賃は二・五倍になったが、タクシーなどよりはずっと安い。そのつど料金交渉が必要なバイクタクシーに比べて、明朗会計だ。道も覚えられる。明るいうちなら、女性・子どもが多いから安心感があるし、もし不安を感じたら、とり外されているドアからすぐに降りることができる。
印象的な出来事に遭遇することもある。赤ちゃんを抱いたお母さんが、料金を払わずに歩き去ってしまったとき、運転手はあきらめ顔で見送っていた。車が止まる前に、わたしがつい立ち上がって降りようとすると、市場帰りのおばさんが「あんた座ってなさいよ」と笑いながら言う。「ここから何番のスダコに乗ればいい?」とたずねることが、会話の糸口になることも。空調の効いた車の窓ガラス越しに見るときとは、街の風景も別の場所のように生き生きと感じられるのだ。
というわけでわたしは今日も、一〇〇〇ルピア札を握りしめ、スダコに乗って出かけるのである。
インドネシア・スマトラ島のメダン市には、たくさんの「スダコ」が道路を走っている。
スダコとは、ここでは小型バスのことだ。正式なインドネシア語でないようだし、他の地域では通じない。何故そうよぶのか地元の人に聞いてみても、スダコの意味はよくわからない、というのが正直なところらしい。
道路に出れば、色、デザインさまざまなスダコが目に付く。外装は会社によって異なるが、運転席の内装や前後の窓は、運転手の好みで飾り付けてあり、日本の長距離トラックを思わせる。急発進・急停車は当たり前。しきりにクラクションを鳴らし、接触ぎりぎりのところをすり抜けていく。近年手ごろな価格の車が登場し、交通量が著しく増加しているメダン市で、乗用車やバイクのドライバーたちはスダコに気を使わないと運転できない。しょっちゅう起きる停電で信号が消えているときも、主導権を握るのはスダコたちだ。
公共交通機関の整備が不十分なので、庶民の足として大活躍している。乗客は道端で待っていて、外装と番号で目当てのスダコを見わけ、合図して止める。停留所や時刻表はない。後部座席は向かい合ったベンチ状で、ひざを突き合わせて座る。かなり揺れるので、読書や居眠りをしている人はまず見かけない。降りたいところで運転手に声をかけて知らせ、前にまわって料金を手渡す。市内なら、一人二五〇〇ルピア(約三五円)だ。
今日は何人乗せたかな?
スダコの運転手にとって最大の関心事は、いかに満員に近い状態で走るか、である。通りの反対側からでも、合図に気が付くと、ずっと待っている。乗っている車がいきなり止まるので、降りる人もいないのに、と不思議に思っていると、遠くからゆっくり歩いてくるお客さんがいることに気が付く。市場など人の集まるところでは、しばらく客待ち停車をする。どう見ても満員でも、いいから乗れ乗れ、と誘うので、乗車拒否をするのは乗客の方だ。
助手席に乗り込むと、スダコに何が必要で、何が必要でないか、はっきりと見てとることができる。運転席は改造が繰り返され、設備は最小限。速度計などの計器はどれも動いていない。内装は金属板がむきだしになっている。助手席の窓は、運賃の受け渡しのため常に開けておくので、ドアも外側からだけ開けばよい。
いいかげんなようだが、細かいところには独自の工夫がある。微妙なハンドルさばきがとても大事なので、ハンドルはひとまわり小さなものに取り替えられている。ウィンカーのレバーはクラクションにつながっていて、歩行者の注意を引く際などに反射的に使われる。乗客の足元にはスペアタイヤ。釣り銭はダッシュボードの上に並べ、赤信号のあいだに紙幣を整理してポケットにしまう。
乗客の数が、運転手の収入に直接結び付いている。会社には毎日決められた額を車の使用料として支払えばいいからだ。営業は運転手本位。乗客を乗せたまま、ガソリンスタンドにも行く。給油が終わるまで、みんな静かに待っている。慣れてくると、停留所と運行時間に拘束されている日本のバスが、つれなく思えることさえある。
一〇〇〇ルピア札を握りしめて
別れ際に「スダコで帰る」と言うと、「気を付けてね」と言われることがある。「スダコに乗ったことなんてないわ」と言う人も多い。用心のため、いつも乗る前には運賃をポケットに準備しておき、財布や携帯電話は出さないようにする。メダン市の若者にとっても、自分のバイクなり車なりを手に入れてスダコから卒業することは、ひとつの目標である。いつまでもスダコに乗っているのは、かっこ悪いことでもあり、不便でもある。
わたしも、ほかの交通手段を確保すべきだろうか、とも考えた。ぎゅうぎゅうに詰め込まれると、さすがに息苦しい。運転手付きの車は望むべくもないが、バイクタクシーを月極めで雇うという方法だってある。だが、スダコにはスダコのよさがあるのだ。二年間で運賃は二・五倍になったが、タクシーなどよりはずっと安い。そのつど料金交渉が必要なバイクタクシーに比べて、明朗会計だ。道も覚えられる。明るいうちなら、女性・子どもが多いから安心感があるし、もし不安を感じたら、とり外されているドアからすぐに降りることができる。
印象的な出来事に遭遇することもある。赤ちゃんを抱いたお母さんが、料金を払わずに歩き去ってしまったとき、運転手はあきらめ顔で見送っていた。車が止まる前に、わたしがつい立ち上がって降りようとすると、市場帰りのおばさんが「あんた座ってなさいよ」と笑いながら言う。「ここから何番のスダコに乗ればいい?」とたずねることが、会話の糸口になることも。空調の効いた車の窓ガラス越しに見るときとは、街の風景も別の場所のように生き生きと感じられるのだ。
というわけでわたしは今日も、一〇〇〇ルピア札を握りしめ、スダコに乗って出かけるのである。
編集後記
昨年の秋、韓国の航空会社を使って欧州から帰国の際に、仁川(インチョン)国際空港から日本人女性ばかりのツアー団体と同じ飛行機に乗ることになった。
皆、筒状に巻いたポスターを手荷物として大事そうに抱えている。「これ手垢付くのいややからまだなか見てへんけど、サインしてなかったらどーしよー。
あたし、泣くわ。あはははは」と、関西弁で賑やかに会話をしている。ポスターはどうも、韓流スターのご尊影らしい。
憧れのドラマの地に身をおき、幻想にどっぷりと浸かり、そしてその幻想のかけらを手に入れ満足そうに家路に着く女性たち。
この体験は、しばらくは彼女らの元気の源となるのであろう。
博物館もまた人びとが記憶、幻想、疑似体験を求めてやってくる「観光」の場である。 研究者が提示する「現実」は、ときには来館者の期待を裏切るということもありうる。 だが、あなたの幻想は間違っていますよ、とただ否定しただけでは、来館者に不快感を与えるばかりだ。 幻想の欲求を受け止めつつ、別の側面も教示する。そのバランスが大切なのだろう。 観光業界で進「幻想の復権」は、博物館のある方をも変えてゆくかもしれない。(山中由里子)
博物館もまた人びとが記憶、幻想、疑似体験を求めてやってくる「観光」の場である。 研究者が提示する「現実」は、ときには来館者の期待を裏切るということもありうる。 だが、あなたの幻想は間違っていますよ、とただ否定しただけでは、来館者に不快感を与えるばかりだ。 幻想の欲求を受け止めつつ、別の側面も教示する。そのバランスが大切なのだろう。 観光業界で進「幻想の復権」は、博物館のある方をも変えてゆくかもしれない。(山中由里子)
定期購読についてのお問い合わせは、ミュージアムショップまで。 本誌の内容についてのお問い合わせは、国立民族学博物館広報企画室企画連携係【TEL:06-6878-8210(平日9時~17時)】まで。