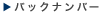月刊みんぱく 2008年8月号
2008年8月号
第32巻第8号通巻第371号
2008年8月1日発行
2008年8月1日発行
思いとかたち
柴崎 友香
大阪で暮らす若い女性がむかしの写真を集めて自分が住む街の過去を実感しようとする気持ちを『その街の今は』という小説に書いた。古い写真を使った絵はがきや戦後に写された空中写真などが小説のなかに出てくるが、それらの写真の大半は、大学で卒業論文を書くときに集めた資料がもとになっている。
わたしは大学で人文地理学を専攻していた。そう言うと、小説と関係ないのにどうして、意外ですね、なんて言われることが多いが、自分のなかではふたつのことはそんなに違わないというか、関心のありようという点では同じだ。卒業論文のテーマは「都市のイメージを写真によって分析する」ことで、『その街の今は』はその小説版だ、と自分では思っている。地理学だと階段を積み上げて着実にひとつひとつ上っていく感じ、小説ではときどきその段階を飛び越えるようなやり方ができるというふうに、あらわし方を変えてなんとか伝えようとしているのだと思う。
それからわたしの小説はいわゆる「大事件」が起こらなくて日常のできごとを題材にしていることが多い。それで、日常にこそドラマがあるんですね、と感想をいただくこともあるのだけれど、それも少し違う。電車で向かいに座る人を見ていても窓から外に広がる風景を見ていても、おもしろくてまったく飽きないのだが、その「おもしろい」というのは、特別変わったことを発見しているわけではない。
たとえるなら、昆虫や動物を見て「こっちのは羽根が長いけど、こっちには羽根が短いのがいる!」というような驚きに近いのではないかと思う。良いとか悪いとかではなく、違う、同じ、似てる、それだけでじゅうぶん驚異的だし、そこから考えることはいくらでもあって、好奇心は加速していく。
そういう性質なので当然、「みんぱく」は、寝袋を持ち込んで暮らしてもいいと思うほど好きな場所だ。最初に行ったのは何歳のときだったか覚えていないけれど、何度行っても、目が覚めるみたいに驚く。わたしにとってはテーマパークのアトラクションよりずっとわくわくするし、同時に、自分の家に帰ってきたように心が安らぐ。
それはきっと、みんぱくにあるものが、みんな人が作ったものだからだと思う。ひとつひとつ、誰か、それはわたしが会うことのない知らない人だけれど、その人の思考がその人の手によってかたちになってあらわれているからだろう。いつか、わたしが感じているこういう気持ちを小説のかたちにしたいと、長いあいだ考えている。
しばさき ともか/1973年大阪生まれ。小説家。2000年『きょうのできごと』(河出書房新社)でデビュー。2007年『その街の今は』(新潮社)で第57回芸術選奨文部科学大臣新人賞、第23回織田作之助賞受賞。著書に『青空感傷ツアー』『また会う日まで』(河出書房新社)『主題歌』(講談社)など多数。
わたしは大学で人文地理学を専攻していた。そう言うと、小説と関係ないのにどうして、意外ですね、なんて言われることが多いが、自分のなかではふたつのことはそんなに違わないというか、関心のありようという点では同じだ。卒業論文のテーマは「都市のイメージを写真によって分析する」ことで、『その街の今は』はその小説版だ、と自分では思っている。地理学だと階段を積み上げて着実にひとつひとつ上っていく感じ、小説ではときどきその段階を飛び越えるようなやり方ができるというふうに、あらわし方を変えてなんとか伝えようとしているのだと思う。
それからわたしの小説はいわゆる「大事件」が起こらなくて日常のできごとを題材にしていることが多い。それで、日常にこそドラマがあるんですね、と感想をいただくこともあるのだけれど、それも少し違う。電車で向かいに座る人を見ていても窓から外に広がる風景を見ていても、おもしろくてまったく飽きないのだが、その「おもしろい」というのは、特別変わったことを発見しているわけではない。
たとえるなら、昆虫や動物を見て「こっちのは羽根が長いけど、こっちには羽根が短いのがいる!」というような驚きに近いのではないかと思う。良いとか悪いとかではなく、違う、同じ、似てる、それだけでじゅうぶん驚異的だし、そこから考えることはいくらでもあって、好奇心は加速していく。
そういう性質なので当然、「みんぱく」は、寝袋を持ち込んで暮らしてもいいと思うほど好きな場所だ。最初に行ったのは何歳のときだったか覚えていないけれど、何度行っても、目が覚めるみたいに驚く。わたしにとってはテーマパークのアトラクションよりずっとわくわくするし、同時に、自分の家に帰ってきたように心が安らぐ。
それはきっと、みんぱくにあるものが、みんな人が作ったものだからだと思う。ひとつひとつ、誰か、それはわたしが会うことのない知らない人だけれど、その人の思考がその人の手によってかたちになってあらわれているからだろう。いつか、わたしが感じているこういう気持ちを小説のかたちにしたいと、長いあいだ考えている。
しばさき ともか/1973年大阪生まれ。小説家。2000年『きょうのできごと』(河出書房新社)でデビュー。2007年『その街の今は』(新潮社)で第57回芸術選奨文部科学大臣新人賞、第23回織田作之助賞受賞。著書に『青空感傷ツアー』『また会う日まで』(河出書房新社)『主題歌』(講談社)など多数。
景観をめぐるふたつのフィールド
―人間文化研究機構長、金田章裕氏に聞く―
―人間文化研究機構長、金田章裕氏に聞く―
二〇〇四年の国立大学等の法人化にともない、民博をはじめとした五つの大学共同利用機関がまとまり、「大学共同利用機関法人・人間文化研究機構」として再編されました。その第二代機構長として、今年四月に金田章裕先生が就任。
今号では、金田先生のこれまでの研究や、人間文化研究機構における民博への期待などについて編集長がうかがいました。
今号では、金田先生のこれまでの研究や、人間文化研究機構における民博への期待などについて編集長がうかがいました。
金田 章裕(きんだ あきひろ)
一九四六年富山県生まれ。地理学者。追手門学院大学、京都大学を経て、二〇〇八年四月から人間文化研究機構長、京都大学名誉教授。専門は歴史地理学。日本やオーストラリアの景観史研究に従事。文学博士。『オーストラリア景観史』(大明堂)、『古地図からみた古代日本』(中央公論新社)、『古代景観史の探究』(吉川弘文館)ほか著書多数。
一九四六年富山県生まれ。地理学者。追手門学院大学、京都大学を経て、二〇〇八年四月から人間文化研究機構長、京都大学名誉教授。専門は歴史地理学。日本やオーストラリアの景観史研究に従事。文学博士。『オーストラリア景観史』(大明堂)、『古地図からみた古代日本』(中央公論新社)、『古代景観史の探究』(吉川弘文館)ほか著書多数。
―最初に、先生の研究についてお聞かせください。ご専門は広く言えば人文地理学ですね。
自然地理学に対して人文地理学があるのですが、そのなかにも、地理学の頭に分野名をつけたさまざまな専門の分野があります。僕のメインは歴史地理学でしたので、歴博の共同研究に参加していました。さらにセカンド・フィールドはオーストラリアで、民博の小山修三、松山利夫先生がなさっていたオーストラリアに関する共同研究のメンバーでもありました。僕だけでなく、僕の出身である京大地理学教室のOBの多くの方が民博や歴博に関係しています。佐々木高明先生、端信行先生、田辺繁治先生、小長谷有紀先生、さらに大島襄二先生、岩田慶治先生、川喜田二郎先生なども活躍されています。松山利夫先生も大学は違いますが、もともと地理学出身です。地理学と文化人類学は深いつながりがあるんですよ。
と言うのも、文化人類学が日本で確立するのが遅かったので、いろいろな出自の人が文化人類学を始めた。ですから地理学のかなりの数の方が文化人類学の草創期を支えたことになります。
―歴史地理学とは、一言で言えばどんな学問ですか。
人が土地の上で生活をするためにさまざまな施策をおこなう、それがうまくいったり、やりすぎて失敗する、社会・経済条件の変化で変わっていく。そういう時間的な変化を、時間と空間の両方の視野で研究する、というのが基本的な姿勢です。ただし、さかのぼる時間幅は人間の生活の範囲だけで、僕がやるのは、自分のできる範囲に限ります。オーストラリアの場合には、わりあい時間幅の短い白人入植後に中心を置いて、アボリジニに関しても白人との接触の部分に注目しています。
―なぜオーストラリアに目をつけられたのですか?
僕は日本の歴史地理学を専攻していたけれど、これは地理学でも狭い分野なので地理学の相対的視点を身につけるためでした。あと、教育者として職をえるには海外にもフィールドをもって幅を広げねばならないと思って、大学院のときからどのフィールドにするべきか、いろいろ探していました。
もともと古代に関心があったので、最初、古代ローマに目をつけましたが、ラテン語が読めないのであきらめました。次に関心をもったのがインカ。博士課程のときにインカに関するレポートを書いたこともありますが、スペイン語がわからないのであきらめた。次に北アメリカかなと思ったのですが、あまりにポピュラーで留学した人も多く、自分に何ができるかわからなかったのであきらめました。
そうこうするうち、マイクル・ウィリアムズという人が書いたThe Making of the South Australian Landscapeをたまたま読む機会があって面白かった。ところが、鉱山をやっている人はいたが、そんな分野を研究している日本人の人文地理学者は歴史地理学では誰もいない。そこでオーストラリアを選んだわけです。
―最初のきっかけはランドスケープ(景観)だったんですね。
その本で言うところのランドスケープは、イギリスのW・G・ホスキンス流のランドスケープに近かったので、日本で言う景観と少しニュアンスが違います。もっとも当時はそこまで意識していなかった。こうしてふたつのフィールドをもつことになりましたが、その後、いろいろ迷ったすえに、オーストラリアの論文を書くために、日本をフィールドとする歴史地理学の論文をオーストラリアのと同じ本数以上書くことを決めて、日本については最低、一年にふたつ書きました。オースオラリアに流れすぎると日本がおろそかになることを避けるためです。オーストラリアの論文を書きたいために、日本の論文を書いたこともあるし、逆の場合もあります。僕の単著は九冊ありますが、オートラリアについては二冊しかないのは、そういうわけです。
―そのあたりはフィールドをふたつもっている人に共通する悩みですね。
オーストラリアを軽視したわけではないですが、一貫してセカンドでした。植民地を多くもっていたこともありますが、ドイツの地理学者も国内と海外のふたつのフィールドをもつことが一般的でした。そのことを知っていたというのもあります。人文地理学には、系統地理学の分野、つまり分析して法則を探すタイプと、地誌学というある特定地域の性格を明らかにするタイプのふたつがあります。大学に就職したいと思っていましたが、講義をするうえで、そのふたつをやるためには、フィールドをふたつもつことが必要です。そのためにふたつ目のフィールドを探したのです。
文化行政における景観
―国内調査も続けられ、文化庁の文化行政にもかかわってこられましたね。
出身が歴史地理学なので、最初は記念物課の史跡関連の委員になっていました。そのうち、ユネスコが世界遺産のひとつとしてカルチュラル・ランドスケープを対象に入れたのです。それに対応した法律作りをするために文化庁が作った検討委員会の委員にもなり、現在の法律の準備作業もしました。そのからみで、今度は、「重要文化的景観」というカテゴリーの文化財ができたので、その関係の委員長もやっています。
僕が、景観の歴史的変化を主要なテーマとして研究し始めたころは、景観そのものが行政の課題になるとは思いもしませんでした。そこに、ユネスコがヨーロッパ的なカルチュラル・ランドスケープという考え方をもち込んだものだから、景観のことをやっていた僕とか建築の樋口忠彦先生などの研究者が集められた。ちょうど、建築学や地理学、造園などに関心をもつ研究者が増えてきた時期です。
―重要文化的景観と世界遺産との関係はどうですか?
世界遺産は、ユネスコが条約を批准した各国からの提案について、価値を評価し、その国で保護できる状況になっているかどうかチェックして登録するものです。
日本の場合、世界遺産の文化遺産については、文化庁が作っている世界遺産特別委員会で、自治体からの提案を議論します。一方で、自然遺産については環境省がやっています。ユネスコがやるのはお墨付きを出すだけで、実際の調査や保護などは条約を批准した国がそれぞれの国内法で対処します。日本には、国内法で史跡・名勝・記念物などを保護する制度があり、そのひとつが重要文化的景観の選定です。
史跡は指定ですが、重要文化的景観は選定です。地元から申し出があったものを審査して選定するという枠組みになっています。これは二〇〇五年以降のことで、最近なんですね。国内で選定されたのはまだ九件で、岩手、滋賀各二件、北海道、愛媛、佐賀、大分、熊本各一件です
―文化的景観と言うのはどんな概念ですか?
地理学では、カルチュラル・ランドスケープはむかしから使っていたことばで、文化景観と訳していた。それを法律上の用語にするために、姑息な方法ですが、「的」という文字を入れました。法律は明確に規定しないといけないんですが、学問的な用語を明確に考えると限定されすぎて、研究の幅が狭くなってしまう。そこで、文化的景観としたのです。
―研究に広がりをもたせるための方法だったんですね。
そうです。だって、地理学で使っていたカルチュラル・ランドスケープとは、人間が手を加えたものすべてを指すんですよ、醜いモノであろうといいものであろうと。一方で、文化的景観という場合は、人間側の評価が入っている。
―人間にとってプラスの評価が入っている点は、ややいやらしいですね。
プラスと言えばそうなんだけども、人間生活のなかで、プラスという場合はそれを作ってきた人たちにとって、好ましいものなんですよ。好ましいものが歴史的に残り、好ましくないものは淘汰され消えていく。ですから、時間幅を長くとれば問題はない、短くとれば問題はたくさん出てくる。短い時間で見れば、好ましいもの、好ましくないものが併存するんですよ。
―それは興味深い考え方ですね。こうした景観の考え方はヨーロッパが起源ですか?
ヨーロッパの景観にもいろいろあって、ドイツ流のラントシャフトの系統と、英語圏のランドスケープとはまた違います。ドイツ語のラントは土地、州などの土地を領有する政治体制ですよね。ラントシャフトとは、そこの政治的なまとまりみたいなもののことです。日本語で言うと、そのことば自体が偏って使われているから不適切かも知れませんが、「一揆」と一緒ですよ。その地域に住んでいる人びとがまとまって何かをしようとすること。これが本来の意味で、それに近い。
―人間に重点をおく、ということですね。
そうなんです。ところが英語で対応するランドスケープということばは違う。僕がいつも言っていることですが、もしlandshipということばがあればそれに近いんだけれども英語にはない。英語の概念は、限りなく現在の日本人が思っている「景観」に近い。むしろそっちの方が今のカルチュラル・ランドスケープになっている。日本の地理学がラントシャフトという概念を受け入れた当初はドイツ流だったんですが、どんどん英語流のほうにシフトしてきました。
―遺産の保護と開発の問題はつねに出てきますね。
ええ、世界遺産に登録したためにかえって問題が生じるところもある。それまでは劣悪な経済条件で細々とやっていたところが、世界遺産に登録されたために有名になって観光客が押し寄せ、経済的には潤ったが遺産が崩壊していく。特に、アジアの場合は、石作りなどハードなものが少ないから問題が起きることが多い。
比較的うまくいっている例は、オーストラリアのカカドゥ国立公園です。ここでは、アボリジニの文化遺産である岩壁画、山から望んだ景観など象徴的な場所が保存されています。そこにあまり大量じゃない観光客が来るけれど、観光客の宿泊のための基地は別に設定されているのでうまくいっています。
―カカドゥはあれだけ広い国立公園ですし。
広いために破壊を免れているところがあります。もしあそこが人口過密なところだとすると、隔離ができないわけですね。その点、土地の狭い日本ではなかなか難しいですが、そのなかで一所懸命にシステムを作っておられるのが、屋久島や知床です。それでも訪れる人が増えているから問題が生じています。それに比べて、たとえば、日光、京都、奈良などは、むかしから観光客や参拝客が多いので、対応できるキャパシティがもともと大きいわけですよ。ところが、屋久島や知床をはじめ、熊野古道、白神山地などではなかなか難しいということです。
法人化の光と影
―二〇〇四年に発足した人間文化研究機構の二代目の機構長になられましたが、法人化という学術行政の流れについてどのように見ておられますか?
法人化の制度設計から実施にかけての時期が、僕自身、京都大学の副学長をやっていた時期に重なっていたので、流れは見てきました。表面だけ見れば、自主性があるという点で法人化は悪いことではない。でも、制度を新しくすることで、すべてを同じスタートラインに立たせ「ご破算で願いましては」とするのは問題です。人文学では、研究テーマが今、出てきたわけではないし、限定された時間内に結論が出るものでもない。人間社会にとって永遠の課題みたいなものを、こつこつ少しずつ何とかしようという学問です。そんな学問にとっては、新しい制度で、ご破算で再スタートと言われるのは大変困るのです。
―評価の時間幅が問題です。
時間幅どころか評価のシステム自体が問題です。僕が多少知っているイギリスに比べても、日本の評価システムは不必要に労働力を使いすぎるし、集団無責任体制です。つまり、評価する側が、何のためにどういう評価をするのかが定まっていないので、評価項目が何でもかんでも入っているから大変です。もうひとつは、評価をする側の人格が見えない匿名である点が問題です。イギリスの例ですと、評価項目が少ない。しかも、評価する人の個人名を出して全人格をあげて、この人の評価だったらこうなるだろうと納得してもらえるように評価する。受ける側も、この人だからこういう評価をした、と納得できます。
―評価する側もされる側も、お互いに真剣勝負ですね。
そうですよ。日本では評価委員が明確ではない。だからと言って、日本でイギリスのようにしようとすると問題がある。何でもかんでも同じ画一的な評価をしようとするからです。人間文化研究機構にしても、大学共同利用機関法人なのに、国立大学法人と基本的に同じ評価システムである点が問題です。
―各機関の独自性を評価のポイントにしてもいいですよね。
ところが今は、国立大学法人に共通する部分を軸にして評価項目ができあがっていて、そこに独自性を付け加えることになっている。その分どれかの項目を落とす、ということになっていない。結局、評価項目が膨大な量になり、膨大な力を浪費することになる。
―実際、評価用レポートなどの書類作りが増えています。
それが法人化のひとつのマイナス面です。法人予算の本来の趣旨は、大きな袋で予算を渡すのでその使い方は各法人で決めなさい、というものでしたが、実態は違う。予算の基準を今のような評価システムとくっつけたりするから、問題がより複雑になり、多大な労力を使っているだけで、それが本当に各法人の独自性に結びつくのだろうか、という話になります。
戦後の新制大学制度ができて時間の経つなかで、問題はいくつかあったけど、それぞれが制度のなかで独自性を出す努力をしてきた。それをみんな無くしちゃった。由々しい問題ですよ、特に人文学にとっては。理系と同じようにプロジェクト型でやる、それにお金を付けるというスタイルに人文学が慣れてしまうと、むかし予算の少ないころにこつこつとやって醸し出されてきた重要な部分が軽視されることになる。
―特に個人でやる研究の多い人文学ではね。
最終的に人文学は個人ベースに戻るんです。何でもかんでもプロジェクトという方式にはなじまないし、運用しにくい。国が貧するのは無駄使いばっかりのせいですが、そのしわ寄せが学術の方に来ている。イギリスなどではむしろ今は文教予算を増やしているのに、日本では財務省が削っていくなんてことを言い始めている。政策的にちゃんと考えるべきだと思います。
民博の次の一手を
―今後の民博について期待されることはありますか。
民博について言えば、文化人類学が分野として定着していなかったころに創設され、大きな研究組織として積極的な研究活動と啓蒙活動を展開してきました。それが成功したからこそ、どの大学にも文化人類学という分野が定着して専攻ができた。かつては、地理学、歴史学、社会学、考古学、自然人類学からも文化人類学に参入した時代から、今では文化人類学専攻出身者がその分野を担うようになってきた。それは結構なんですが、下手をすると文化人類学を研究する他の大学と変わらなくなってしまう。
さあ、民博はこれから何をするのか、大学共同利用機関として位置づけられているなかで、次の一手は何かを考えないといけない。ただし、外圧では無理な押しつけになるので、民博ならではの得意分野に基づいた内発的な次の一手が必要ですね。内発的に出てこないと外圧が出てくる危機はつねにある。むしろ外圧が追っかけてくるぐらいの状態にもっていかないとだめですよ。
―どの分野でも研究領域として確立すると深く、狭くなっていく傾向がありますね。
地理学でもそうでした。帝大の文学部ができた当時は、論壇の主要なものを含め、社会的な関心の七、八割は集めたと思います。だけどその後たくさんできた文学部は、どんどん専門性が高まりあるいは硬直化が進んで、社会的な関心の半分以下しか今では集めていないと思います。その一部をもぎとったのが、かつての民博です。でも成功の代償として、現在の民博があることを認識する必要がある。守りになってはだめで、常に前衛として次の一手を考える。だから、民博が総力をあげて考える時期に来ているし、周りの皆さんの期待も大きいと思います。
民博の設立当初、露出展示という理念は当時の日本では画期的だった。でも今やいろいろなところに広まって当たり前になった。では次は何なのか、が問われている。我々の使命はそれが枯渇したら終わりなのです。
かつて梅棹先生などがコンセプトを作られたけど、今や、何十人の研究者が総力を挙げて考えるべきだと思います。いまだに広い意味で同じ分野の研究者が五〇人以上も集まっている機関は他にないんですから。もったいないです。
独立行政法人法の改正案が国会で議論されていて、それが今後は共同利用機関法人に波及してくる可能性がある。そこで何が課題になるかというと、国立大学法人とは異なる共同利用性をより強く求められるのは間違いない。それが社会的ニーズである、と理解しておいた方が良い。でもこれからは、各大学に附置されている多くの研究所も共同利用性をより強めると思いますので、そのなかに埋没してしまわない方策を考えないといけない。
―大学ではできない共同利用性を探さないといけませんね。共同研究、モノや資料の共同利用、場の共同利用などが考えられますが。
僕の機構長としての任期は四年で、そのあいだに第一期六年間の評価が入る。第二期は今回の延長でいけるでしょうが、第三期はまったくわからない、揺り戻しがあるかも知れない。評価されるうえで、認知度を明確にしておかないとつらいですよ。
最近よく言われるように、ニーズを決めるのは一般社会です。大学は一般社会に直結している学部教育をもっていますが、それをもたない民博・歴博は、代わりに社会に直結する博物館の機能をもっています。それを表に出して有効活用しない手はない。それを使ってどうしたら社会へのアピールを効果的に強化できるか、がひとつのポイントでしょう
―博物館活動においても、この分野をリードするような次の一手を考えないといけませんね。
一般社会では、民博と国立博物館機構などとの違いがわからない。国立博物館機構には東京文化財研究所や奈良文化財研究所も加わって研究を盛んにやっています。ですから、民博はそれらとの違いをいかに出すか、ですよ。そういうところも含めた戦略をぜひ考えていただきたいですね。
―民博へのアドバイスもいただき、本日はありがとうございました。
聞き手・久保正敏(本誌編集長)
自然地理学に対して人文地理学があるのですが、そのなかにも、地理学の頭に分野名をつけたさまざまな専門の分野があります。僕のメインは歴史地理学でしたので、歴博の共同研究に参加していました。さらにセカンド・フィールドはオーストラリアで、民博の小山修三、松山利夫先生がなさっていたオーストラリアに関する共同研究のメンバーでもありました。僕だけでなく、僕の出身である京大地理学教室のOBの多くの方が民博や歴博に関係しています。佐々木高明先生、端信行先生、田辺繁治先生、小長谷有紀先生、さらに大島襄二先生、岩田慶治先生、川喜田二郎先生なども活躍されています。松山利夫先生も大学は違いますが、もともと地理学出身です。地理学と文化人類学は深いつながりがあるんですよ。
と言うのも、文化人類学が日本で確立するのが遅かったので、いろいろな出自の人が文化人類学を始めた。ですから地理学のかなりの数の方が文化人類学の草創期を支えたことになります。
―歴史地理学とは、一言で言えばどんな学問ですか。
人が土地の上で生活をするためにさまざまな施策をおこなう、それがうまくいったり、やりすぎて失敗する、社会・経済条件の変化で変わっていく。そういう時間的な変化を、時間と空間の両方の視野で研究する、というのが基本的な姿勢です。ただし、さかのぼる時間幅は人間の生活の範囲だけで、僕がやるのは、自分のできる範囲に限ります。オーストラリアの場合には、わりあい時間幅の短い白人入植後に中心を置いて、アボリジニに関しても白人との接触の部分に注目しています。
―なぜオーストラリアに目をつけられたのですか?
僕は日本の歴史地理学を専攻していたけれど、これは地理学でも狭い分野なので地理学の相対的視点を身につけるためでした。あと、教育者として職をえるには海外にもフィールドをもって幅を広げねばならないと思って、大学院のときからどのフィールドにするべきか、いろいろ探していました。
もともと古代に関心があったので、最初、古代ローマに目をつけましたが、ラテン語が読めないのであきらめました。次に関心をもったのがインカ。博士課程のときにインカに関するレポートを書いたこともありますが、スペイン語がわからないのであきらめた。次に北アメリカかなと思ったのですが、あまりにポピュラーで留学した人も多く、自分に何ができるかわからなかったのであきらめました。
そうこうするうち、マイクル・ウィリアムズという人が書いたThe Making of the South Australian Landscapeをたまたま読む機会があって面白かった。ところが、鉱山をやっている人はいたが、そんな分野を研究している日本人の人文地理学者は歴史地理学では誰もいない。そこでオーストラリアを選んだわけです。
―最初のきっかけはランドスケープ(景観)だったんですね。
その本で言うところのランドスケープは、イギリスのW・G・ホスキンス流のランドスケープに近かったので、日本で言う景観と少しニュアンスが違います。もっとも当時はそこまで意識していなかった。こうしてふたつのフィールドをもつことになりましたが、その後、いろいろ迷ったすえに、オーストラリアの論文を書くために、日本をフィールドとする歴史地理学の論文をオーストラリアのと同じ本数以上書くことを決めて、日本については最低、一年にふたつ書きました。オースオラリアに流れすぎると日本がおろそかになることを避けるためです。オーストラリアの論文を書きたいために、日本の論文を書いたこともあるし、逆の場合もあります。僕の単著は九冊ありますが、オートラリアについては二冊しかないのは、そういうわけです。
―そのあたりはフィールドをふたつもっている人に共通する悩みですね。
オーストラリアを軽視したわけではないですが、一貫してセカンドでした。植民地を多くもっていたこともありますが、ドイツの地理学者も国内と海外のふたつのフィールドをもつことが一般的でした。そのことを知っていたというのもあります。人文地理学には、系統地理学の分野、つまり分析して法則を探すタイプと、地誌学というある特定地域の性格を明らかにするタイプのふたつがあります。大学に就職したいと思っていましたが、講義をするうえで、そのふたつをやるためには、フィールドをふたつもつことが必要です。そのためにふたつ目のフィールドを探したのです。
文化行政における景観
―国内調査も続けられ、文化庁の文化行政にもかかわってこられましたね。
出身が歴史地理学なので、最初は記念物課の史跡関連の委員になっていました。そのうち、ユネスコが世界遺産のひとつとしてカルチュラル・ランドスケープを対象に入れたのです。それに対応した法律作りをするために文化庁が作った検討委員会の委員にもなり、現在の法律の準備作業もしました。そのからみで、今度は、「重要文化的景観」というカテゴリーの文化財ができたので、その関係の委員長もやっています。
僕が、景観の歴史的変化を主要なテーマとして研究し始めたころは、景観そのものが行政の課題になるとは思いもしませんでした。そこに、ユネスコがヨーロッパ的なカルチュラル・ランドスケープという考え方をもち込んだものだから、景観のことをやっていた僕とか建築の樋口忠彦先生などの研究者が集められた。ちょうど、建築学や地理学、造園などに関心をもつ研究者が増えてきた時期です。
―重要文化的景観と世界遺産との関係はどうですか?
世界遺産は、ユネスコが条約を批准した各国からの提案について、価値を評価し、その国で保護できる状況になっているかどうかチェックして登録するものです。
日本の場合、世界遺産の文化遺産については、文化庁が作っている世界遺産特別委員会で、自治体からの提案を議論します。一方で、自然遺産については環境省がやっています。ユネスコがやるのはお墨付きを出すだけで、実際の調査や保護などは条約を批准した国がそれぞれの国内法で対処します。日本には、国内法で史跡・名勝・記念物などを保護する制度があり、そのひとつが重要文化的景観の選定です。
史跡は指定ですが、重要文化的景観は選定です。地元から申し出があったものを審査して選定するという枠組みになっています。これは二〇〇五年以降のことで、最近なんですね。国内で選定されたのはまだ九件で、岩手、滋賀各二件、北海道、愛媛、佐賀、大分、熊本各一件です
―文化的景観と言うのはどんな概念ですか?
地理学では、カルチュラル・ランドスケープはむかしから使っていたことばで、文化景観と訳していた。それを法律上の用語にするために、姑息な方法ですが、「的」という文字を入れました。法律は明確に規定しないといけないんですが、学問的な用語を明確に考えると限定されすぎて、研究の幅が狭くなってしまう。そこで、文化的景観としたのです。
―研究に広がりをもたせるための方法だったんですね。
そうです。だって、地理学で使っていたカルチュラル・ランドスケープとは、人間が手を加えたものすべてを指すんですよ、醜いモノであろうといいものであろうと。一方で、文化的景観という場合は、人間側の評価が入っている。
―人間にとってプラスの評価が入っている点は、ややいやらしいですね。
プラスと言えばそうなんだけども、人間生活のなかで、プラスという場合はそれを作ってきた人たちにとって、好ましいものなんですよ。好ましいものが歴史的に残り、好ましくないものは淘汰され消えていく。ですから、時間幅を長くとれば問題はない、短くとれば問題はたくさん出てくる。短い時間で見れば、好ましいもの、好ましくないものが併存するんですよ。
―それは興味深い考え方ですね。こうした景観の考え方はヨーロッパが起源ですか?
ヨーロッパの景観にもいろいろあって、ドイツ流のラントシャフトの系統と、英語圏のランドスケープとはまた違います。ドイツ語のラントは土地、州などの土地を領有する政治体制ですよね。ラントシャフトとは、そこの政治的なまとまりみたいなもののことです。日本語で言うと、そのことば自体が偏って使われているから不適切かも知れませんが、「一揆」と一緒ですよ。その地域に住んでいる人びとがまとまって何かをしようとすること。これが本来の意味で、それに近い。
―人間に重点をおく、ということですね。
そうなんです。ところが英語で対応するランドスケープということばは違う。僕がいつも言っていることですが、もしlandshipということばがあればそれに近いんだけれども英語にはない。英語の概念は、限りなく現在の日本人が思っている「景観」に近い。むしろそっちの方が今のカルチュラル・ランドスケープになっている。日本の地理学がラントシャフトという概念を受け入れた当初はドイツ流だったんですが、どんどん英語流のほうにシフトしてきました。
―遺産の保護と開発の問題はつねに出てきますね。
ええ、世界遺産に登録したためにかえって問題が生じるところもある。それまでは劣悪な経済条件で細々とやっていたところが、世界遺産に登録されたために有名になって観光客が押し寄せ、経済的には潤ったが遺産が崩壊していく。特に、アジアの場合は、石作りなどハードなものが少ないから問題が起きることが多い。
比較的うまくいっている例は、オーストラリアのカカドゥ国立公園です。ここでは、アボリジニの文化遺産である岩壁画、山から望んだ景観など象徴的な場所が保存されています。そこにあまり大量じゃない観光客が来るけれど、観光客の宿泊のための基地は別に設定されているのでうまくいっています。
―カカドゥはあれだけ広い国立公園ですし。
広いために破壊を免れているところがあります。もしあそこが人口過密なところだとすると、隔離ができないわけですね。その点、土地の狭い日本ではなかなか難しいですが、そのなかで一所懸命にシステムを作っておられるのが、屋久島や知床です。それでも訪れる人が増えているから問題が生じています。それに比べて、たとえば、日光、京都、奈良などは、むかしから観光客や参拝客が多いので、対応できるキャパシティがもともと大きいわけですよ。ところが、屋久島や知床をはじめ、熊野古道、白神山地などではなかなか難しいということです。
法人化の光と影
―二〇〇四年に発足した人間文化研究機構の二代目の機構長になられましたが、法人化という学術行政の流れについてどのように見ておられますか?
法人化の制度設計から実施にかけての時期が、僕自身、京都大学の副学長をやっていた時期に重なっていたので、流れは見てきました。表面だけ見れば、自主性があるという点で法人化は悪いことではない。でも、制度を新しくすることで、すべてを同じスタートラインに立たせ「ご破算で願いましては」とするのは問題です。人文学では、研究テーマが今、出てきたわけではないし、限定された時間内に結論が出るものでもない。人間社会にとって永遠の課題みたいなものを、こつこつ少しずつ何とかしようという学問です。そんな学問にとっては、新しい制度で、ご破算で再スタートと言われるのは大変困るのです。
―評価の時間幅が問題です。
時間幅どころか評価のシステム自体が問題です。僕が多少知っているイギリスに比べても、日本の評価システムは不必要に労働力を使いすぎるし、集団無責任体制です。つまり、評価する側が、何のためにどういう評価をするのかが定まっていないので、評価項目が何でもかんでも入っているから大変です。もうひとつは、評価をする側の人格が見えない匿名である点が問題です。イギリスの例ですと、評価項目が少ない。しかも、評価する人の個人名を出して全人格をあげて、この人の評価だったらこうなるだろうと納得してもらえるように評価する。受ける側も、この人だからこういう評価をした、と納得できます。
―評価する側もされる側も、お互いに真剣勝負ですね。
そうですよ。日本では評価委員が明確ではない。だからと言って、日本でイギリスのようにしようとすると問題がある。何でもかんでも同じ画一的な評価をしようとするからです。人間文化研究機構にしても、大学共同利用機関法人なのに、国立大学法人と基本的に同じ評価システムである点が問題です。
―各機関の独自性を評価のポイントにしてもいいですよね。
ところが今は、国立大学法人に共通する部分を軸にして評価項目ができあがっていて、そこに独自性を付け加えることになっている。その分どれかの項目を落とす、ということになっていない。結局、評価項目が膨大な量になり、膨大な力を浪費することになる。
―実際、評価用レポートなどの書類作りが増えています。
それが法人化のひとつのマイナス面です。法人予算の本来の趣旨は、大きな袋で予算を渡すのでその使い方は各法人で決めなさい、というものでしたが、実態は違う。予算の基準を今のような評価システムとくっつけたりするから、問題がより複雑になり、多大な労力を使っているだけで、それが本当に各法人の独自性に結びつくのだろうか、という話になります。
戦後の新制大学制度ができて時間の経つなかで、問題はいくつかあったけど、それぞれが制度のなかで独自性を出す努力をしてきた。それをみんな無くしちゃった。由々しい問題ですよ、特に人文学にとっては。理系と同じようにプロジェクト型でやる、それにお金を付けるというスタイルに人文学が慣れてしまうと、むかし予算の少ないころにこつこつとやって醸し出されてきた重要な部分が軽視されることになる。
―特に個人でやる研究の多い人文学ではね。
最終的に人文学は個人ベースに戻るんです。何でもかんでもプロジェクトという方式にはなじまないし、運用しにくい。国が貧するのは無駄使いばっかりのせいですが、そのしわ寄せが学術の方に来ている。イギリスなどではむしろ今は文教予算を増やしているのに、日本では財務省が削っていくなんてことを言い始めている。政策的にちゃんと考えるべきだと思います。
民博の次の一手を
―今後の民博について期待されることはありますか。
民博について言えば、文化人類学が分野として定着していなかったころに創設され、大きな研究組織として積極的な研究活動と啓蒙活動を展開してきました。それが成功したからこそ、どの大学にも文化人類学という分野が定着して専攻ができた。かつては、地理学、歴史学、社会学、考古学、自然人類学からも文化人類学に参入した時代から、今では文化人類学専攻出身者がその分野を担うようになってきた。それは結構なんですが、下手をすると文化人類学を研究する他の大学と変わらなくなってしまう。
さあ、民博はこれから何をするのか、大学共同利用機関として位置づけられているなかで、次の一手は何かを考えないといけない。ただし、外圧では無理な押しつけになるので、民博ならではの得意分野に基づいた内発的な次の一手が必要ですね。内発的に出てこないと外圧が出てくる危機はつねにある。むしろ外圧が追っかけてくるぐらいの状態にもっていかないとだめですよ。
―どの分野でも研究領域として確立すると深く、狭くなっていく傾向がありますね。
地理学でもそうでした。帝大の文学部ができた当時は、論壇の主要なものを含め、社会的な関心の七、八割は集めたと思います。だけどその後たくさんできた文学部は、どんどん専門性が高まりあるいは硬直化が進んで、社会的な関心の半分以下しか今では集めていないと思います。その一部をもぎとったのが、かつての民博です。でも成功の代償として、現在の民博があることを認識する必要がある。守りになってはだめで、常に前衛として次の一手を考える。だから、民博が総力をあげて考える時期に来ているし、周りの皆さんの期待も大きいと思います。
民博の設立当初、露出展示という理念は当時の日本では画期的だった。でも今やいろいろなところに広まって当たり前になった。では次は何なのか、が問われている。我々の使命はそれが枯渇したら終わりなのです。
かつて梅棹先生などがコンセプトを作られたけど、今や、何十人の研究者が総力を挙げて考えるべきだと思います。いまだに広い意味で同じ分野の研究者が五〇人以上も集まっている機関は他にないんですから。もったいないです。
独立行政法人法の改正案が国会で議論されていて、それが今後は共同利用機関法人に波及してくる可能性がある。そこで何が課題になるかというと、国立大学法人とは異なる共同利用性をより強く求められるのは間違いない。それが社会的ニーズである、と理解しておいた方が良い。でもこれからは、各大学に附置されている多くの研究所も共同利用性をより強めると思いますので、そのなかに埋没してしまわない方策を考えないといけない。
―大学ではできない共同利用性を探さないといけませんね。共同研究、モノや資料の共同利用、場の共同利用などが考えられますが。
僕の機構長としての任期は四年で、そのあいだに第一期六年間の評価が入る。第二期は今回の延長でいけるでしょうが、第三期はまったくわからない、揺り戻しがあるかも知れない。評価されるうえで、認知度を明確にしておかないとつらいですよ。
最近よく言われるように、ニーズを決めるのは一般社会です。大学は一般社会に直結している学部教育をもっていますが、それをもたない民博・歴博は、代わりに社会に直結する博物館の機能をもっています。それを表に出して有効活用しない手はない。それを使ってどうしたら社会へのアピールを効果的に強化できるか、がひとつのポイントでしょう
―博物館活動においても、この分野をリードするような次の一手を考えないといけませんね。
一般社会では、民博と国立博物館機構などとの違いがわからない。国立博物館機構には東京文化財研究所や奈良文化財研究所も加わって研究を盛んにやっています。ですから、民博はそれらとの違いをいかに出すか、ですよ。そういうところも含めた戦略をぜひ考えていただきたいですね。
―民博へのアドバイスもいただき、本日はありがとうございました。
聞き手・久保正敏(本誌編集長)
ムシロやゴザを織る道具
ムシロやゴザを織るには、絹や麻や木綿や羊毛などをはじめとする一般的な繊維素材をタテ糸やヨコ糸として織物を織る場合とは、まったく違った道具が使われてきた。その道具とは、織機を構成する部品のうちに見出される開口具(かいこうぐ)や緯打具(よこうちぐ)である。このうち開口具は、専門的には綜絖(そうこう)の名で知られているもので、奇数列や偶数列といった二種類に分割されたタテ糸の相対的な位置関係を交互に変化させて、ヨコ糸をとおすためのタテ糸の開口や逆開口を繰り返しおこなう道具である。一方、緯打具はタテ糸のあいだにとおしたヨコ糸を打ち込むための道具である。ムシロやゴザを織るために使われてきた開口具のうちには、緯打具としての機能をも兼ね備えている例が見出されるが、開口具が備わっていない場合のムシロやゴザを織るための道具としては、緯打具が織りの道具として主要な役割を果たしている。
ムシロやゴザを織るために使われてきた開口具としては、開孔棒綜絖、開孔板綜絖、複合式開孔板綜絖、箱型開孔板綜絖の存在がこれまでにあきらかになっている。また、緯打具としては、形状の異なる二種類の板状の道具が知られている。以下は、わたしがこれまで世界各地で調査した結果に基づいて、そうした開口具と緯打具の概要を示そう。
開口具1(開孔棒綜絖)―開孔棒綜絖は、ムシロやゴザ、あるいはゴザ状の織物を織るための専用の開口具として知られている。もともと東アジアのみに分布していたと見られるが、最近ではタイやラオスにおいても広く使われている。これは一本の棒に幅の狭いジョウゴ型の孔が、交互に向きを変えて連続してあけられており、棒の角度を変えることによって、孔にとおされているタテ糸が開口と逆開口を繰り返す。開孔棒綜絖はそうした開口具としての機能とともに緯打具としての機能も有しており、タテ糸のあいだにとおされたヨコ糸の打ち込みも開孔棒綜絖によっておこなわれる。(写真1)
なお、開孔棒綜絖のうちには、例外的に竹筒を使用したものがあり、そうした例は、これまでに中国の貴州省に住む漢族とラオス北部に住むタイ・プアン人のもとで確認している。それらはいずれも竹筒の両側から細長い孔と円い孔が交互に向き合うように連続してあけられている。その構造は開孔棒綜絖とは異なるものの、開口具、および緯打具としての機能はまったく共通している。
開口具2(開孔板綜絖)―開孔板綜絖は細幅織物を織るための開口具として世界の広範な地域で使われてきたが、広幅のムシロを織るために使われている例が西シベリアのタタール人のもとに見出される。開孔板綜絖は一枚の板に、細長い孔と円い孔が交互に連続してあけられており、板を上下させることによって、孔にとおされているタテ糸が開口と逆開口を繰り返す。なお、タテ糸の開口部や逆開口部にとおされたヨコ糸の打ち込みには、刀状の緯打具が使用されている。(写真2)
開口具3(複合式開孔板綜絖)―複合式開孔板綜絖は、東南アジア大陸部のベトナム、カンボジア、ラオス、タイでゴザを織るために使用されている。これは開孔板綜絖を二枚あわせにした構造の開口具である。ただし、機能的には開孔棒綜絖と共通しており、角度を変えることによって孔にとおされているタテ糸が開口と逆開口を繰り返し、開口具としての機能とともに緯打具としての機能も有している。(写真3)
開口具4(箱型開孔板綜絖)―箱型開孔板綜絖は、これまでのところ日本においてのみ存在が確認されている開口具である。北海道常呂町の栄浦第二遺跡から出土した一〇世紀後半から一一世紀ごろのものと見られる考古資料と、明治時代に新潟県と岩手県で使われていた二点の民俗資料が知られている。これは開孔板綜絖の類品として位置づけられるもので、ゴザ状織物を織るための開口具であるとともに、緯打具としての機能を兼ね備えた道具として使われていたと考えられるものである。(写真4)
緯打具1―板の片側が波状を呈した緯打具。これは、タイやラオスで二〇世紀後半に開孔棒綜絖や複合式開孔板綜絖が普及し始めるまで広く使われていたと見られるもので、V字形の切れ込み部分にタテ糸をはめ込むようにして、ヨコ糸の打ち込みがおこなわれる。(写真5)
緯打具2―板に円い孔が連続してあけられており、タテ糸が孔にとおされている。このような緯打具は、これまでにコーカサス、イラン、トルコ、エジプトにおいて確認している。(写真6)
ムシロやゴザを織るために使われてきた開口具としては、開孔棒綜絖、開孔板綜絖、複合式開孔板綜絖、箱型開孔板綜絖の存在がこれまでにあきらかになっている。また、緯打具としては、形状の異なる二種類の板状の道具が知られている。以下は、わたしがこれまで世界各地で調査した結果に基づいて、そうした開口具と緯打具の概要を示そう。
開口具1(開孔棒綜絖)―開孔棒綜絖は、ムシロやゴザ、あるいはゴザ状の織物を織るための専用の開口具として知られている。もともと東アジアのみに分布していたと見られるが、最近ではタイやラオスにおいても広く使われている。これは一本の棒に幅の狭いジョウゴ型の孔が、交互に向きを変えて連続してあけられており、棒の角度を変えることによって、孔にとおされているタテ糸が開口と逆開口を繰り返す。開孔棒綜絖はそうした開口具としての機能とともに緯打具としての機能も有しており、タテ糸のあいだにとおされたヨコ糸の打ち込みも開孔棒綜絖によっておこなわれる。(写真1)
なお、開孔棒綜絖のうちには、例外的に竹筒を使用したものがあり、そうした例は、これまでに中国の貴州省に住む漢族とラオス北部に住むタイ・プアン人のもとで確認している。それらはいずれも竹筒の両側から細長い孔と円い孔が交互に向き合うように連続してあけられている。その構造は開孔棒綜絖とは異なるものの、開口具、および緯打具としての機能はまったく共通している。
開口具2(開孔板綜絖)―開孔板綜絖は細幅織物を織るための開口具として世界の広範な地域で使われてきたが、広幅のムシロを織るために使われている例が西シベリアのタタール人のもとに見出される。開孔板綜絖は一枚の板に、細長い孔と円い孔が交互に連続してあけられており、板を上下させることによって、孔にとおされているタテ糸が開口と逆開口を繰り返す。なお、タテ糸の開口部や逆開口部にとおされたヨコ糸の打ち込みには、刀状の緯打具が使用されている。(写真2)
開口具3(複合式開孔板綜絖)―複合式開孔板綜絖は、東南アジア大陸部のベトナム、カンボジア、ラオス、タイでゴザを織るために使用されている。これは開孔板綜絖を二枚あわせにした構造の開口具である。ただし、機能的には開孔棒綜絖と共通しており、角度を変えることによって孔にとおされているタテ糸が開口と逆開口を繰り返し、開口具としての機能とともに緯打具としての機能も有している。(写真3)
開口具4(箱型開孔板綜絖)―箱型開孔板綜絖は、これまでのところ日本においてのみ存在が確認されている開口具である。北海道常呂町の栄浦第二遺跡から出土した一〇世紀後半から一一世紀ごろのものと見られる考古資料と、明治時代に新潟県と岩手県で使われていた二点の民俗資料が知られている。これは開孔板綜絖の類品として位置づけられるもので、ゴザ状織物を織るための開口具であるとともに、緯打具としての機能を兼ね備えた道具として使われていたと考えられるものである。(写真4)
緯打具1―板の片側が波状を呈した緯打具。これは、タイやラオスで二〇世紀後半に開孔棒綜絖や複合式開孔板綜絖が普及し始めるまで広く使われていたと見られるもので、V字形の切れ込み部分にタテ糸をはめ込むようにして、ヨコ糸の打ち込みがおこなわれる。(写真5)
緯打具2―板に円い孔が連続してあけられており、タテ糸が孔にとおされている。このような緯打具は、これまでにコーカサス、イラン、トルコ、エジプトにおいて確認している。(写真6)
砂漠のなかのグローバル楽器博物館
アメリカ合衆国の南西部にあるアリゾナ州に大規模な楽器の博物館を建てる計画が進められている。その名もずばり「楽器博物館」Musical Instrument Museum(略称MIM)。二〇一〇年に開館の予定である。楽器コレクションといえばパリの音楽博物館やブリュッセルの楽器博物館などが有名であるが、収蔵品には地域的な偏りがある。スミソニアンやメトロポリタン博物館にも数多くの楽器があるが巨大なコレクションの一部でしかない。MIMは、「世界初のグローバル楽器博物館」という壮大で野心的なキャッチフレーズのもと、世界中の楽器を網羅的に展示することを目指している。
館長のビル・デワルトさんは音楽や楽器の専門家ではなく、ラテンアメリカを研究する文化人類学者である。長年ピッツバーグ大学で教鞭をとったが、二〇〇二年にカーネギー自然史博物館の館長に就任。そこでの運営の手腕が評価されて、昨年MIMの館長に抜擢された。自分の仕事は「資金集め」と笑うが、すでに三人の民族音楽学者をスタッフに雇い入れ、開館に向けての体制作りを着々と進めている。
MIMは開館までに五〇〇〇点の楽器収集を目指しており、その調達が目下のところいちばんの課題である。すでに一二〇〇点におよぶ大型コレクションを一括購入しているが、ゼロからの出発であるから先は長い。そのため世界各地の博物館とネットワークを作り、資料の貸借を容易にすることも展示活動を続けていくうえで重要である。今年の五月中旬にデワルトさん夫妻が来日したのは、日本の博物館や楽器製作会社などとの協力関係を作るためだった。
MIMの展示の特徴は、楽器をモノとしてのみでなく、むしろ文化として紹介しようとする姿勢にある。展示されている楽器の音を聴けるようにするだけでなく、楽器のもち方や演奏法、演奏される場などを写真や映像を使って紹介する計画だ。また、地域別にわけられた展示場のほかに、ライブ用のホールや録音スタジオ、楽器体験コーナーから楽器作りを見学できる工房にいたるまで、音楽と楽器について多角的に楽しみながら学ぶことができる仕掛けがそろっている。ちなみに、「文化としての楽器」というコンセプトは、いま民博で準備を進めている新しい音楽展示にも共通している。今後このコンセプトをいかに実際の展示として実現していくかについて議論し合うことは双方にとって有益であろう。
MIMはフェニックス市の外れの砂漠に建設が予定されている。この博物館が音楽への渇きを潤すオアシスに成長していくことを期待したい。
館長のビル・デワルトさんは音楽や楽器の専門家ではなく、ラテンアメリカを研究する文化人類学者である。長年ピッツバーグ大学で教鞭をとったが、二〇〇二年にカーネギー自然史博物館の館長に就任。そこでの運営の手腕が評価されて、昨年MIMの館長に抜擢された。自分の仕事は「資金集め」と笑うが、すでに三人の民族音楽学者をスタッフに雇い入れ、開館に向けての体制作りを着々と進めている。
MIMは開館までに五〇〇〇点の楽器収集を目指しており、その調達が目下のところいちばんの課題である。すでに一二〇〇点におよぶ大型コレクションを一括購入しているが、ゼロからの出発であるから先は長い。そのため世界各地の博物館とネットワークを作り、資料の貸借を容易にすることも展示活動を続けていくうえで重要である。今年の五月中旬にデワルトさん夫妻が来日したのは、日本の博物館や楽器製作会社などとの協力関係を作るためだった。
MIMの展示の特徴は、楽器をモノとしてのみでなく、むしろ文化として紹介しようとする姿勢にある。展示されている楽器の音を聴けるようにするだけでなく、楽器のもち方や演奏法、演奏される場などを写真や映像を使って紹介する計画だ。また、地域別にわけられた展示場のほかに、ライブ用のホールや録音スタジオ、楽器体験コーナーから楽器作りを見学できる工房にいたるまで、音楽と楽器について多角的に楽しみながら学ぶことができる仕掛けがそろっている。ちなみに、「文化としての楽器」というコンセプトは、いま民博で準備を進めている新しい音楽展示にも共通している。今後このコンセプトをいかに実際の展示として実現していくかについて議論し合うことは双方にとって有益であろう。
MIMはフェニックス市の外れの砂漠に建設が予定されている。この博物館が音楽への渇きを潤すオアシスに成長していくことを期待したい。
北西海岸のシルクスクリーン版画
シルクスクリーン(蚊の起源)(標本番号H144824、高さ/77cm 幅/57cm)
シルクスクリーン(蚊の起源)(標本番号H144824、高さ/77cm 幅/57cm)
一九六〇年代にカナダの北西海岸先住民のあいだでは、販売用のアート作品として版画がさかんに制作されはじめた。版画自体は伝統的なものではなかったが、そのなかに表現された図像は伝統的なものであった。みんぱくにはカナダ国立博物館の協力のもとに収集されたカナダ北西海岸先住民の版画が約六七〇点、所蔵されている。
北西海岸先住民の版画は、彼らの祖先と関係の深い動物や昆虫、神話のなかの怪物、精霊、太陽や星などが、色鮮やかに、幾何学的な形式で描き出されている。意外と、人間の様子や姿を描いた図像は少ない。一方、おどろくほど多種多様な生物が版画のなかに描き出されている。たとえば、クマやクジラ、ラッコ、ビーバー、シャチ、サケ、タコ、ウナギ、ハマグリなど多種の海生動物、ワタリガラス、ワシ、タカなど多数の鳥、蚊やチョウのような昆虫、双頭のヘビやサンダーバードなどの想像上の動物が、独特の形態に変形され表現されている。
ここで紹介したのは、夏に大量に発生する蚊の版画である。北西海岸にすむ多くの人びとにとって、蚊は彼らを刺し、血をすうので、害虫のひとつであると考えられている。しかし、クワクワカワクゥ社会やツィムシアン社会では重要な儀礼で踊るときに蚊の仮面を着用する家族がいる。この一族の祖先と蚊とのあいだには何らかの関係があると考えられており、蚊は、代々、一族の紋章のひとつとして受け継がれている。彼らにとって蚊は祖先と彼らをつなぐ重要かつ象徴的な媒介物であるとともに、共生すべき大事な自然界の一部なのである。
現代の北西海岸先住民のアーティストは、多数の昆虫のなかから蚊を選び、注意深く観察し、独特な形態で描き出している。
北西海岸先住民の版画は、彼らの祖先と関係の深い動物や昆虫、神話のなかの怪物、精霊、太陽や星などが、色鮮やかに、幾何学的な形式で描き出されている。意外と、人間の様子や姿を描いた図像は少ない。一方、おどろくほど多種多様な生物が版画のなかに描き出されている。たとえば、クマやクジラ、ラッコ、ビーバー、シャチ、サケ、タコ、ウナギ、ハマグリなど多種の海生動物、ワタリガラス、ワシ、タカなど多数の鳥、蚊やチョウのような昆虫、双頭のヘビやサンダーバードなどの想像上の動物が、独特の形態に変形され表現されている。
ここで紹介したのは、夏に大量に発生する蚊の版画である。北西海岸にすむ多くの人びとにとって、蚊は彼らを刺し、血をすうので、害虫のひとつであると考えられている。しかし、クワクワカワクゥ社会やツィムシアン社会では重要な儀礼で踊るときに蚊の仮面を着用する家族がいる。この一族の祖先と蚊とのあいだには何らかの関係があると考えられており、蚊は、代々、一族の紋章のひとつとして受け継がれている。彼らにとって蚊は祖先と彼らをつなぐ重要かつ象徴的な媒介物であるとともに、共生すべき大事な自然界の一部なのである。
現代の北西海岸先住民のアーティストは、多数の昆虫のなかから蚊を選び、注意深く観察し、独特な形態で描き出している。
お犬様とEU加盟
人命を脅かす動物愛護
ルーマニアに住む友人が野犬に襲われた。狂犬病の注射を受けるため、パニックのなか奔走したらしい。狂犬病とは、イヌ、コウモリなどを介して起こる伝染病で、感染してから二四時間以内にワクチンを注射しなければ死亡率が高い。わたしが直接に知るだけでも野犬にかまれた人はこれで四人目である。二〇〇六年一月には邦人男性がブカレストで野犬にかまれ、失血死する事件も起きている。ルーマニアで野放しにされたイヌは全国で推定二〇〇万匹、そのうち首都ブカレストでは約一〇万匹の野犬がいるという。
二〇〇五年には同国内で二万人以上がイヌに襲われ、当局は駆除に乗り出そうとした。しかし、対策は進んでいない。その原因は「ヨーロッパ」からの動物愛護要求のためだ。急先鋒は、フランスの元有名女優。二〇〇六年一月、動物愛護活動家でもあるこの女優は駆除計画に抗議して声明を出し、ルーマニア当局を非難した。個人の声明に過ぎないが、背後にはヨーロッパの動物愛護の大きな勢力がある。むろん、年間五〇万に近いイヌやネコが保健所で「処分」される日本も大きな顔はできない。身勝手なペットブームは、生きとし生けるものへの冒涜(ぼうとく)である。だが、市民が恐怖におののきながら暮らす動物愛護もいかがなものか。
「文明」による野蛮
他方、イタリアではルーマニア人が襲われている。イヌに、ではない。移民を排斥しようとする人間に、である。イタリアでは、二〇〇七年一月のEU加盟後、ルーマニアからの移民が急増している。言語と文化の親近性から、イタリアはルーマニア人の出稼ぎ先としてもっとも好まれる国のひとつ。公式資料によるとイタリアで働くルーマニア人の数は五〇万人に達する。
入国したルーマニア人による犯罪も多発しているらしい。さらに二〇〇七年一〇月、イタリア人女性に対するルーマニア人による強盗レイプ殺人事件が世論に火をつけた。ルーマニア人襲撃もその影響である。他方、イタリア政府は市民の安全を脅かすと思われるEU市民の追放を認める法令を一一月一日に定めた。その結果、法令制定後三日間でイタリアの七都市から三九人のルーマニア人が追放処分となった。EU加盟国の国民は域内の自由な移動が認められるのが建前である。しかし、ルーマニア人は例外のようだ。
EU加盟によってルーマニアは、ヨーロッパへと「回帰」した。「野蛮」な社会主義から解放されたというなら、喜ばしいことである。しかし、「文明」による野蛮は、ヨーロッパのそこかしこに散在している。植民地主義、人種主義、反ユダヤ主義、移民排斥。EU加盟で、その矛先はルーマニアにも向けられた。もとよりルーマニアにも差別はある。ロマ(かつてジプシーとよばれた)の人びとへの蔑視も否定できない。ルーマニア当局は、イタリアにおけるルーマニア人移民と犯罪者の区別を強調する。これは犯罪者をロマと関連づけて、誠実で勤勉な「本当の」ルーマニア人と区別しようというものだ。そこには差別のいれこ構造ともいうべき、人間社会の本性がある。
ルーマニアに住む友人が野犬に襲われた。狂犬病の注射を受けるため、パニックのなか奔走したらしい。狂犬病とは、イヌ、コウモリなどを介して起こる伝染病で、感染してから二四時間以内にワクチンを注射しなければ死亡率が高い。わたしが直接に知るだけでも野犬にかまれた人はこれで四人目である。二〇〇六年一月には邦人男性がブカレストで野犬にかまれ、失血死する事件も起きている。ルーマニアで野放しにされたイヌは全国で推定二〇〇万匹、そのうち首都ブカレストでは約一〇万匹の野犬がいるという。
二〇〇五年には同国内で二万人以上がイヌに襲われ、当局は駆除に乗り出そうとした。しかし、対策は進んでいない。その原因は「ヨーロッパ」からの動物愛護要求のためだ。急先鋒は、フランスの元有名女優。二〇〇六年一月、動物愛護活動家でもあるこの女優は駆除計画に抗議して声明を出し、ルーマニア当局を非難した。個人の声明に過ぎないが、背後にはヨーロッパの動物愛護の大きな勢力がある。むろん、年間五〇万に近いイヌやネコが保健所で「処分」される日本も大きな顔はできない。身勝手なペットブームは、生きとし生けるものへの冒涜(ぼうとく)である。だが、市民が恐怖におののきながら暮らす動物愛護もいかがなものか。
「文明」による野蛮
他方、イタリアではルーマニア人が襲われている。イヌに、ではない。移民を排斥しようとする人間に、である。イタリアでは、二〇〇七年一月のEU加盟後、ルーマニアからの移民が急増している。言語と文化の親近性から、イタリアはルーマニア人の出稼ぎ先としてもっとも好まれる国のひとつ。公式資料によるとイタリアで働くルーマニア人の数は五〇万人に達する。
入国したルーマニア人による犯罪も多発しているらしい。さらに二〇〇七年一〇月、イタリア人女性に対するルーマニア人による強盗レイプ殺人事件が世論に火をつけた。ルーマニア人襲撃もその影響である。他方、イタリア政府は市民の安全を脅かすと思われるEU市民の追放を認める法令を一一月一日に定めた。その結果、法令制定後三日間でイタリアの七都市から三九人のルーマニア人が追放処分となった。EU加盟国の国民は域内の自由な移動が認められるのが建前である。しかし、ルーマニア人は例外のようだ。
EU加盟によってルーマニアは、ヨーロッパへと「回帰」した。「野蛮」な社会主義から解放されたというなら、喜ばしいことである。しかし、「文明」による野蛮は、ヨーロッパのそこかしこに散在している。植民地主義、人種主義、反ユダヤ主義、移民排斥。EU加盟で、その矛先はルーマニアにも向けられた。もとよりルーマニアにも差別はある。ロマ(かつてジプシーとよばれた)の人びとへの蔑視も否定できない。ルーマニア当局は、イタリアにおけるルーマニア人移民と犯罪者の区別を強調する。これは犯罪者をロマと関連づけて、誠実で勤勉な「本当の」ルーマニア人と区別しようというものだ。そこには差別のいれこ構造ともいうべき、人間社会の本性がある。
ラテンアメリカの古写真を求めて
民博ではいま、企画展「ラテンアメリカを踏査する――写真で辿る黎明期の考古学・民族学調査」が開催されている(九月二三日まで)。この展示では、一九世紀末から二〇世紀初めにかけてラテンアメリカを踏査した四人の欧米の考古学者と民族学者の写真を紹介している。発掘当時の古代遺跡の状態や、近代化の波にもまれる以前の先住民の暮らしを鮮明に記録したそれらの写真は、研究資料として第一級の価値をもっている。写真はまた、当時の研究者の関心のありかや価値観、写す側と写される側の関係についても多くを語ってくれる。
被写体だけでなく撮影者も
わたしは企画展のプロジェクト・リーダー(および唯一のメンバー)として、二〇〇四年からその準備にたずさわってきた。計画当初からわたしは、被写体だけでなく撮影者についても学べるような写真展を実施したいと考えていた。ラテンアメリカの遺跡や先住民についてはもちろん、彼らを調査した人びとの期待や思惑、感動や苦難についても理解を深めることができる展示を目指していた。それゆえ、写真の選定基準として、特定の学術調査の際に作成されたまとまったコレクションであることが最重視された。
もっとも、そのようなコレクションを探しだし、原板の所在を突き止めるのは、容易ではなかった。同僚からの情報や、本やインターネットで拾った情報を出発点とせざるをえず、その真偽を確かめるには、これはと思われる機関や個人に直接アプローチするしかなかった。運良く返事が来て、コレクションの存在が確かめられると、次にすべきことは、現地を訪れて写真を実見することである。こうしてわたしは、イギリス、ドイツ、アメリカの博物館や文書館、大学や研究所を渡り歩き、膨大な量の写真に目をとおした。最終的に、マヤ地域、アンデス地域、アマゾン川流域、フエゴ諸島を踏査した四人の研究者に焦点を絞った。
圧倒的な歴史の証言
写真展の企画者としては情けない話だが、じつはわたしは写真を撮るのが苦手である。大学院時代、ボリビア・アマゾンで生活したときも、あまり写真を撮らなかった。撮影が下手というだけではない。人びとにレンズを向けることが、他人の家に土足で踏み込むようなぶしつけな行為に思われて、ためらわれたのである。これでは調査者失格である。実際、再訪するたびに変貌している先住民の暮らしを目にすると、なぜあのときもっと写真を撮っておかなかったのか、と悔やまれることがある。きっと彼らにとっても、貴重な記録となっていただろうに。
企画展で取り上げた四人の研究者の著作を読むと、厳しい環境下、簡便とはいえない撮影機材と格闘し、被写体を説き伏せてなかば強引に撮影を敢行する彼らの姿が浮かび上がる。やらせもまれではなかった。もっとも、彼らの振る舞いを植民地主義的といって非難するのは、おそらく的外れだろう。彼らが撮影した写真は、約百年後の今日、歴史的証言として圧倒的な存在感を獲得しているのだから。その重みの一部を、今回の展示を通じて伝えることができれば、企画者として望外の幸せである。
被写体だけでなく撮影者も
わたしは企画展のプロジェクト・リーダー(および唯一のメンバー)として、二〇〇四年からその準備にたずさわってきた。計画当初からわたしは、被写体だけでなく撮影者についても学べるような写真展を実施したいと考えていた。ラテンアメリカの遺跡や先住民についてはもちろん、彼らを調査した人びとの期待や思惑、感動や苦難についても理解を深めることができる展示を目指していた。それゆえ、写真の選定基準として、特定の学術調査の際に作成されたまとまったコレクションであることが最重視された。
もっとも、そのようなコレクションを探しだし、原板の所在を突き止めるのは、容易ではなかった。同僚からの情報や、本やインターネットで拾った情報を出発点とせざるをえず、その真偽を確かめるには、これはと思われる機関や個人に直接アプローチするしかなかった。運良く返事が来て、コレクションの存在が確かめられると、次にすべきことは、現地を訪れて写真を実見することである。こうしてわたしは、イギリス、ドイツ、アメリカの博物館や文書館、大学や研究所を渡り歩き、膨大な量の写真に目をとおした。最終的に、マヤ地域、アンデス地域、アマゾン川流域、フエゴ諸島を踏査した四人の研究者に焦点を絞った。
圧倒的な歴史の証言
写真展の企画者としては情けない話だが、じつはわたしは写真を撮るのが苦手である。大学院時代、ボリビア・アマゾンで生活したときも、あまり写真を撮らなかった。撮影が下手というだけではない。人びとにレンズを向けることが、他人の家に土足で踏み込むようなぶしつけな行為に思われて、ためらわれたのである。これでは調査者失格である。実際、再訪するたびに変貌している先住民の暮らしを目にすると、なぜあのときもっと写真を撮っておかなかったのか、と悔やまれることがある。きっと彼らにとっても、貴重な記録となっていただろうに。
企画展で取り上げた四人の研究者の著作を読むと、厳しい環境下、簡便とはいえない撮影機材と格闘し、被写体を説き伏せてなかば強引に撮影を敢行する彼らの姿が浮かび上がる。やらせもまれではなかった。もっとも、彼らの振る舞いを植民地主義的といって非難するのは、おそらく的外れだろう。彼らが撮影した写真は、約百年後の今日、歴史的証言として圧倒的な存在感を獲得しているのだから。その重みの一部を、今回の展示を通じて伝えることができれば、企画者として望外の幸せである。
インドとのつながりを胸に
窪田 暁(くぼた さとる) 総合研究大学院大学文化科学研究科博士課程
二軍戦
二〇〇八年六月初旬のある日、北海道日本ハムファイターズ二軍の本拠地・鎌ヶ谷球場を訪れた。「プレスルーム」にあらわれた長身の選手の名はダース・ローマシュ匡(たすく)。彫りの深い顔立ちと、すらりと伸びた手足はプロ野球選手というよりはちょっとモデルを連想させる。空いている席を見つけると、目の前の試合を食い入るように見つめ出した。「やば!スライダー、めちゃ曲がってるやん」、発せられることばは、いまどきの若者そのものだ。二軍の試合では、調整目的で一軍クラスの投手がマウンドにあがることも多く、若手選手たちにとってはプロの技術を勉強できる格好の場となっている。ことばとは裏腹に、真剣なまなざしがマウンド上の先輩投手に注がれていた。
野球ファンにはダースとよばれ親しまれている彼は、岡山県の野球強豪校・関西高校から二〇〇七年にドラフト四巡目で北海道日本ハムに入団して二年目の投手である。高校野球甲子園での敗北に、倒れ込まんばかりに泣いて悔しがった姿は多くの人の記憶に残る。一九〇センチメートルの長身とその出自から「ダルビッシュ二世」といわれることも多い。マー君こと田中将大投手(東北楽天)や斉藤佑樹投手(早稲田大学)は、甲子園を沸かせた同期にあたる。
「プロ野球選球になる」
一九八八年、奈良県生駒市でインド人の父・シェンカーさんと日本人の母・記久子さんとのあいだにうまれた。小さいころからスポーツセンスは抜群だったが、野球は大嫌いだった。父親がテレビの野球中継ばかり見るので、大好きなアニメを見ることができなかったからだ。そんな彼が野球をはじめたのは小学二年の冬。小学校でいちばんの親友から地元の少年野球チームに誘われたのがきっかけだった。野球のルールも知らず、興味もなかった彼にとって、親友と遊べなくなるのがいちばん嫌だったという。
野球チームに入団はしたが、好きではじめたわけではなく、一向に上達しない。練習にいってもつまらない。コーチからは「いつでも辞めていいぞ」と言われる始末。そんな彼を励ましたのが、母親の「うまくなればいいやん。ずっとやってれば楽しいことだってある」ということばだった。負けず嫌いで目立ちたがり屋の性格に火がついた。それからは絵に描いたような野球人生を歩みはじめる。小学六年のときに「ちびっこ甲子園」に出場、中学でもシニアチームのエースとして全国大会出場をはたす。このときには五試合を投げて計六〇奪三振の大会記録を作り、一気に注目される存在になっていく。当然のように甲子園常連校から声がかかり、高校時代には、春夏あわせて四回の甲子園出場をはたすことになる。
ダース投手には、ずっと「絶対にプロ野球選手になる」という信念があった。自分がベンチ入りできなかった高校一年の夏の地方大会、スタンドで応援しながらも、気持ちは複雑だった。自分がマウンドにいなければチームが勝っても意味がないと思ったからだ。父親のシェンカーさんは「運と縁」のある人がプロ野球選手になれるという。しかし、高校時代、友だちと夜の一〇時まで遊んだあと、こっそり下宿を抜け出し、明け方近くまで縄跳びやランニングをしたという彼自身が、「運と縁」をたぐりよせようとしていたことは確かである。
インドとの出合い
父親のシェンカーさんはヒンドゥー教徒のため、今でも風呂上りのお祈りを欠かさない。ダース投手も小学二年のころまでは、父親の真似をして一緒にお祈りをしていた。しかし、子どものころ、父親から何かを強いられたという記憶はない。お祈りをしなくなったときも何もいわれなかったし、ヒンディー語を覚えなさいと強要されたということもない。こういった環境で育ったせいであろうか、自分のなかに流れるインドの血をとりたてて意識するようなことはなかったという。
子どものときから明るい性格で、いつもたくさんの友だちに囲まれてきた。そのため、出自や容姿などが理由で特別嫌な思いをしたということはない。それでも、カタカナの名前をからかわれたり、「顔濃いな」などと言われたことは何度かあった。そのたびに「なんで僕だけこうなんやろ」と思ったりもした。しかし、中学生になり全国大会で訪れた北海道での経験が彼を変える。地元チームの子どもたちから「ダースや」と声をかけられたときに、そんな思いも吹き飛んだという。「自分て得や!名前すぐに覚えてもらえるし、チャンスやん」。
これがきっかけとなったのか、最近、自分はみんなにないものをもっていると、自身のルーツを積極的に受け入れられるようになってきた。昨年の一二月のことである。プロ一年目のシーズンを終えて迎えた初めてのシーズンオフ、久しぶりに実家に帰るといつものように祈りを捧げる父親の姿があった。そのときふと思った。「俺もやったほうがいいのかな」。こうしてプロ野球選手になれたのも、日本人にはない体つきにうまれた結果だと今なら思えるからだ。
順風満帆に見えるダース投手の野球人生も、プロの壁にぶつかっている。これまでは、速い球さえ投げていれば打たれることはなかった。ところがプロ相手では、一五〇キロ近い速球でも簡単に打ちかえされてしまう。現在はコーチの指導をうけながら、プロでも通用するようなキレのあるボールを手にいれようともがいている。インドの血をひく投手が、日本のプロ野球で初勝利を記録する日はそう遠くはなさそうである。
今年の六月六日、母親の記久子さん五一才の誕生日、彼女の携帯に一通のメールが届いた。「俺は野球頑張って、今よりはるかにでかい家住ましたるから待っといて」。
二〇〇八年六月初旬のある日、北海道日本ハムファイターズ二軍の本拠地・鎌ヶ谷球場を訪れた。「プレスルーム」にあらわれた長身の選手の名はダース・ローマシュ匡(たすく)。彫りの深い顔立ちと、すらりと伸びた手足はプロ野球選手というよりはちょっとモデルを連想させる。空いている席を見つけると、目の前の試合を食い入るように見つめ出した。「やば!スライダー、めちゃ曲がってるやん」、発せられることばは、いまどきの若者そのものだ。二軍の試合では、調整目的で一軍クラスの投手がマウンドにあがることも多く、若手選手たちにとってはプロの技術を勉強できる格好の場となっている。ことばとは裏腹に、真剣なまなざしがマウンド上の先輩投手に注がれていた。
野球ファンにはダースとよばれ親しまれている彼は、岡山県の野球強豪校・関西高校から二〇〇七年にドラフト四巡目で北海道日本ハムに入団して二年目の投手である。高校野球甲子園での敗北に、倒れ込まんばかりに泣いて悔しがった姿は多くの人の記憶に残る。一九〇センチメートルの長身とその出自から「ダルビッシュ二世」といわれることも多い。マー君こと田中将大投手(東北楽天)や斉藤佑樹投手(早稲田大学)は、甲子園を沸かせた同期にあたる。
「プロ野球選球になる」
一九八八年、奈良県生駒市でインド人の父・シェンカーさんと日本人の母・記久子さんとのあいだにうまれた。小さいころからスポーツセンスは抜群だったが、野球は大嫌いだった。父親がテレビの野球中継ばかり見るので、大好きなアニメを見ることができなかったからだ。そんな彼が野球をはじめたのは小学二年の冬。小学校でいちばんの親友から地元の少年野球チームに誘われたのがきっかけだった。野球のルールも知らず、興味もなかった彼にとって、親友と遊べなくなるのがいちばん嫌だったという。
野球チームに入団はしたが、好きではじめたわけではなく、一向に上達しない。練習にいってもつまらない。コーチからは「いつでも辞めていいぞ」と言われる始末。そんな彼を励ましたのが、母親の「うまくなればいいやん。ずっとやってれば楽しいことだってある」ということばだった。負けず嫌いで目立ちたがり屋の性格に火がついた。それからは絵に描いたような野球人生を歩みはじめる。小学六年のときに「ちびっこ甲子園」に出場、中学でもシニアチームのエースとして全国大会出場をはたす。このときには五試合を投げて計六〇奪三振の大会記録を作り、一気に注目される存在になっていく。当然のように甲子園常連校から声がかかり、高校時代には、春夏あわせて四回の甲子園出場をはたすことになる。
ダース投手には、ずっと「絶対にプロ野球選手になる」という信念があった。自分がベンチ入りできなかった高校一年の夏の地方大会、スタンドで応援しながらも、気持ちは複雑だった。自分がマウンドにいなければチームが勝っても意味がないと思ったからだ。父親のシェンカーさんは「運と縁」のある人がプロ野球選手になれるという。しかし、高校時代、友だちと夜の一〇時まで遊んだあと、こっそり下宿を抜け出し、明け方近くまで縄跳びやランニングをしたという彼自身が、「運と縁」をたぐりよせようとしていたことは確かである。
インドとの出合い
父親のシェンカーさんはヒンドゥー教徒のため、今でも風呂上りのお祈りを欠かさない。ダース投手も小学二年のころまでは、父親の真似をして一緒にお祈りをしていた。しかし、子どものころ、父親から何かを強いられたという記憶はない。お祈りをしなくなったときも何もいわれなかったし、ヒンディー語を覚えなさいと強要されたということもない。こういった環境で育ったせいであろうか、自分のなかに流れるインドの血をとりたてて意識するようなことはなかったという。
子どものときから明るい性格で、いつもたくさんの友だちに囲まれてきた。そのため、出自や容姿などが理由で特別嫌な思いをしたということはない。それでも、カタカナの名前をからかわれたり、「顔濃いな」などと言われたことは何度かあった。そのたびに「なんで僕だけこうなんやろ」と思ったりもした。しかし、中学生になり全国大会で訪れた北海道での経験が彼を変える。地元チームの子どもたちから「ダースや」と声をかけられたときに、そんな思いも吹き飛んだという。「自分て得や!名前すぐに覚えてもらえるし、チャンスやん」。
これがきっかけとなったのか、最近、自分はみんなにないものをもっていると、自身のルーツを積極的に受け入れられるようになってきた。昨年の一二月のことである。プロ一年目のシーズンを終えて迎えた初めてのシーズンオフ、久しぶりに実家に帰るといつものように祈りを捧げる父親の姿があった。そのときふと思った。「俺もやったほうがいいのかな」。こうしてプロ野球選手になれたのも、日本人にはない体つきにうまれた結果だと今なら思えるからだ。
順風満帆に見えるダース投手の野球人生も、プロの壁にぶつかっている。これまでは、速い球さえ投げていれば打たれることはなかった。ところがプロ相手では、一五〇キロ近い速球でも簡単に打ちかえされてしまう。現在はコーチの指導をうけながら、プロでも通用するようなキレのあるボールを手にいれようともがいている。インドの血をひく投手が、日本のプロ野球で初勝利を記録する日はそう遠くはなさそうである。
今年の六月六日、母親の記久子さん五一才の誕生日、彼女の携帯に一通のメールが届いた。「俺は野球頑張って、今よりはるかにでかい家住ましたるから待っといて」。
イヌイットの夏の生活
季節ごとに移動を繰り返していた極北の狩猟民イヌイットは、一九六〇年ごろにカナダ政府の政策で定住生活をはじめた。彼らは住宅や病院、店舗などがある村を生活の拠点とし、そこから狩猟やキャンプに行き、また、そこに戻ってくるようになった。
現代のイヌイットは、クリスマスのようなキリスト教の行事や狩猟活動の季節的な変化をおもな節目として日常生活を営んでいるが、彼らにとって夏にキャンプに行くことは、生活習慣のひとつである。
夏が来れば思い出す
夏は、村から離れ、親しい仲間だけとともにすごすことができる季節だ。夏が近づくとイヌイットは、昨年のキャンプを思い出し、今年はどこに誰とキャンプに行こうかと考えはじめる。
地上にまだ雪が残る六月ごろからキャンプに出かけはじめるが、短い人で一週間、長い人で三ヵ月間ぐらいをキャンプ地ですごすことが多い。キャンプ地は、村から約三〇キロメートル以内の海岸線に集中している。
キャンプの一日
わたしが一九八四年に同行したキャンプ地は、村から船外機付きボートで一時間ほどのところにあるケープスミス島にあった。そのキャンプは、世帯主がイトコ同士である二家族から構成されていた。ある日のキャンプ生活を紹介しよう。
夏至をすぎたばかりの季節は、太陽がほとんど沈まない。朝起きると、まず、老夫婦とその息子、小さな孫娘、わたしは、今日一日を無事にすごせ、獲物にめぐまれますようにと神様にお祈りをした。それから乾パンと紅茶で簡単な朝食を終えると、となりの家族五人とともに二隻の船外機付きボートに分乗して、キャンプ地の近くに仕掛けてある漁網をチェックしてからアザラシ猟に出た。
島の沿岸にそってゆっくりとボートを走らせながら、アザラシが呼吸のために海面に頭部を出すのを探した。アザラシを発見するとその方向に、次はどこに浮上するだろうかと予測しながら全力で近づき、再び、呼吸のために浮上するのを待った。アザラシを次に見つけた人は「あそこだ、あそこだ」とその方向を指し示しながら大声でハンターに知らせる。このようにしながらアザラシに接近し、ライフルでしとめた。
アザラシを捕獲すると近くの海岸に上陸した。すぐさまハンターはお茶を沸かし、砂糖を大量に入れた紅茶を数杯、時間をかけて楽しんでから、アザラシの解体作業をはじめた。二人のハンターは満面の笑みをうかべながら作業を進め、ときどき、脂肪や肝臓の一部を口にする。解体が終わると二人のハンターは肉と脂肪を折半にした。
それから二家族がいっしょに、今朝とったホッキョクイワナの昼食をゆっくりと楽しんでから次の活動に移った。ブルーベリーなどの野イチゴの採集である。全員が各自、バケツをもち、野イチゴをつむ。一時間もするとかなりの分量を集めることができた。
朝からすでに一二時間以上が経過しているが、活動はまだまだ続く。今度は、生まれたばかりの渡り鳥の雛(ひな)の捕獲だ。雛は飛ぶことができないので、それを全力で走って追っかけ捕獲する。体力がいるが、子どもでも参加でき、楽しい活動だ。
午後一〇時すぎにキャンプ地に帰ったときには、体はくたくただった。待ちに待った夕食は、一方のテントに一〇名全員が集まり、神に祈りをささげた後、いろいろな話に花を咲かせながらとってきた鳥の肉を食べた。
真夜中でも外は明るく、食事が終わると子どもたちは外で遊ぶが、大人たちは無線通信でほかのキャンプ地の人たちと楽しそうに情報交換をする。就寝前には家族が集まり、無事であったことを神に感謝する祈りでその一日を締めくくった。
このような日々が、天気のよい日には毎日、繰り返された。これはイヌイットが望む生き方であった。
変化する夏のキャンプ
現代のイヌイットは生活に必要な物品を購入し、家賃や電話代を払うためには、賃金労働に励まなければならない。また、村には多数の人間が集住しているため、人間関係が多岐にわたり、複雑になった。このように村は、彼らにとってストレスにみちた場所である。
現在も夏になると多くのイヌイットがキャンプに出かけるが、むかしと比べるとキャンプ地が村の近くになり、そこですごす期間が短くなった。この背景には、多くの人が仕事をもっており、長期間、村から離れられなくなったことや経費がかさむためにキャンプに行くことが困難になってきたことなどがあげられる。さらに、村で生まれ、村のなかで育った若者たちが、キャンプに行くよりも、村のなかでテレビを観ることやスポーツを楽しむことを好みだしたことも一因である。
さらに裕福なイヌイットのなかには、キャンプ地にキャビンを建て、自家発電の装置まで設置して、毎週末をすごすような人びとも出てきた。彼らがキャンプ地で過ごすのは、村の喧騒とストレスから逃れるためであり、必ずしもイヌイットの生き方を貫くためではない。グローバル化のもとイヌイットの生活は急速に変貌を遂げつつある。
現代のイヌイットは、クリスマスのようなキリスト教の行事や狩猟活動の季節的な変化をおもな節目として日常生活を営んでいるが、彼らにとって夏にキャンプに行くことは、生活習慣のひとつである。
夏が来れば思い出す
夏は、村から離れ、親しい仲間だけとともにすごすことができる季節だ。夏が近づくとイヌイットは、昨年のキャンプを思い出し、今年はどこに誰とキャンプに行こうかと考えはじめる。
地上にまだ雪が残る六月ごろからキャンプに出かけはじめるが、短い人で一週間、長い人で三ヵ月間ぐらいをキャンプ地ですごすことが多い。キャンプ地は、村から約三〇キロメートル以内の海岸線に集中している。
キャンプの一日
わたしが一九八四年に同行したキャンプ地は、村から船外機付きボートで一時間ほどのところにあるケープスミス島にあった。そのキャンプは、世帯主がイトコ同士である二家族から構成されていた。ある日のキャンプ生活を紹介しよう。
夏至をすぎたばかりの季節は、太陽がほとんど沈まない。朝起きると、まず、老夫婦とその息子、小さな孫娘、わたしは、今日一日を無事にすごせ、獲物にめぐまれますようにと神様にお祈りをした。それから乾パンと紅茶で簡単な朝食を終えると、となりの家族五人とともに二隻の船外機付きボートに分乗して、キャンプ地の近くに仕掛けてある漁網をチェックしてからアザラシ猟に出た。
島の沿岸にそってゆっくりとボートを走らせながら、アザラシが呼吸のために海面に頭部を出すのを探した。アザラシを発見するとその方向に、次はどこに浮上するだろうかと予測しながら全力で近づき、再び、呼吸のために浮上するのを待った。アザラシを次に見つけた人は「あそこだ、あそこだ」とその方向を指し示しながら大声でハンターに知らせる。このようにしながらアザラシに接近し、ライフルでしとめた。
アザラシを捕獲すると近くの海岸に上陸した。すぐさまハンターはお茶を沸かし、砂糖を大量に入れた紅茶を数杯、時間をかけて楽しんでから、アザラシの解体作業をはじめた。二人のハンターは満面の笑みをうかべながら作業を進め、ときどき、脂肪や肝臓の一部を口にする。解体が終わると二人のハンターは肉と脂肪を折半にした。
それから二家族がいっしょに、今朝とったホッキョクイワナの昼食をゆっくりと楽しんでから次の活動に移った。ブルーベリーなどの野イチゴの採集である。全員が各自、バケツをもち、野イチゴをつむ。一時間もするとかなりの分量を集めることができた。
朝からすでに一二時間以上が経過しているが、活動はまだまだ続く。今度は、生まれたばかりの渡り鳥の雛(ひな)の捕獲だ。雛は飛ぶことができないので、それを全力で走って追っかけ捕獲する。体力がいるが、子どもでも参加でき、楽しい活動だ。
午後一〇時すぎにキャンプ地に帰ったときには、体はくたくただった。待ちに待った夕食は、一方のテントに一〇名全員が集まり、神に祈りをささげた後、いろいろな話に花を咲かせながらとってきた鳥の肉を食べた。
真夜中でも外は明るく、食事が終わると子どもたちは外で遊ぶが、大人たちは無線通信でほかのキャンプ地の人たちと楽しそうに情報交換をする。就寝前には家族が集まり、無事であったことを神に感謝する祈りでその一日を締めくくった。
このような日々が、天気のよい日には毎日、繰り返された。これはイヌイットが望む生き方であった。
変化する夏のキャンプ
現代のイヌイットは生活に必要な物品を購入し、家賃や電話代を払うためには、賃金労働に励まなければならない。また、村には多数の人間が集住しているため、人間関係が多岐にわたり、複雑になった。このように村は、彼らにとってストレスにみちた場所である。
現在も夏になると多くのイヌイットがキャンプに出かけるが、むかしと比べるとキャンプ地が村の近くになり、そこですごす期間が短くなった。この背景には、多くの人が仕事をもっており、長期間、村から離れられなくなったことや経費がかさむためにキャンプに行くことが困難になってきたことなどがあげられる。さらに、村で生まれ、村のなかで育った若者たちが、キャンプに行くよりも、村のなかでテレビを観ることやスポーツを楽しむことを好みだしたことも一因である。
さらに裕福なイヌイットのなかには、キャンプ地にキャビンを建て、自家発電の装置まで設置して、毎週末をすごすような人びとも出てきた。彼らがキャンプ地で過ごすのは、村の喧騒とストレスから逃れるためであり、必ずしもイヌイットの生き方を貫くためではない。グローバル化のもとイヌイットの生活は急速に変貌を遂げつつある。
博物館のいたずら虫たち(2)
和髙 智美(わだか ともみ) 本館プロジェクト研究員
大型はフン害も
ハエ目には、ハエ、アブ、カ、ガガンボなどが含まれ、世界各地に分布し、日本には五〇〇〇種以上が生息している。わたしたちが日常的に見かける身近な昆虫のグループといえるだろう。いわゆるハエには、イエバエやニクバエなどの大型のハエや小型のショウジョウバエがあり、衛生害虫や不快害虫として一般的にはいいイメージがもたれていない。博物館においてハエ目は、資料に穴を開けて卵を生みつけたり、幼虫が資料を食害したりするような、直接、資料に害を与える害虫ではないが、イエバエやニクバエのような大型のハエは、フンなどで資料を汚す恐れのある虫として認識されている。
ハエ目は、収蔵庫のように人の出入りが制限されている場所にはほとんどいないが、事務室や作業場などの人の出入りが多いところに集中して見られる。人がドアを開けるときや、ドアやシャッターの下にあるちょっとした隙間が、虫にとっては大きな通り道になっているのである。
網戸取り替え前とその後
民博で、特にハエ目が多くみられるのは、資料を出し入れする搬入口周辺である。民博の搬入口は、大型のシャッター一枚で外と内を隔てているだけである。そのため、シャッターを開けることによって簡単に虫が建物内に侵入できる状況となってしまうことから、かねてから搬入口に網戸を取り付ける防虫対策をおこなってきた。しかし、当時取り付けた網戸は、木枠に網を貼り付けた簡単な網戸であったため(写真1)、時間とともに木枠がひずみ、大きな隙間ができていた。また、網戸の建てつけが悪いことから、作業者の防虫に対する意識が弱まり、結果的に網戸が開放されていることが多かった。つまり、防虫のために取り付けた網戸が役割を果たしていなかった。そこで、二〇〇七年二月に網戸の取り替え工事がおこなわれ、現在の金属製のものに交換した(写真2)。
その効果は、生物生息調査の結果に顕著にあらわれている。生物生息調査は、補虫トラップ(写真3)を館内のいろいろなところに一五日間設置して、そこに捕まった虫を調べることによって、どこに、どんな虫が生息しているのかを調査するものである。網戸を取り替えた後の二〇〇七年春の調査結果と、取り替え工事前の同じ季節(二〇〇六年春)の調査結果を比べてみると(図)、搬入口付近でのハエ目の捕獲数が、六七匹から二七匹に減少しており、網戸を取り替えた効果があったことがわかる。これは、網戸が新しくなったことによって、大きな隙間がなくなり、虫が侵入しにくくなったことと、網戸をあつかいやすくなったことから作業者が網戸をこまめに開閉して開放している時間が短かくなったことなどが考えられる。
虫の侵入を完全に防ぐことは難しい。民博は、緑豊かな万博記念公園に囲まれた素晴らしい環境にある一方で、建物内に虫が侵入する危険性も高い立地条件といえる。だからこそ、生物生息調査の結果から虫の動向を確認し、その結果を参考に、施設的な改良とともに日常作業の見直しをおこない、ハエ目だけでなく、そのほかの害虫の侵入を未然に防ぐ努力をおこなっているのである。
ハエ目(学名:Diptera) イエバエ類 (学名:Muscidae)
ハエ目(Diptera)の成虫は、1対の翅をもつが、これは前翅で、後ろの翅は飛翔中の安定を保つための平均棍(こん)に変化している。イエバエ類は、日本で約250種が確認されており、ハエ目のなかでもっともよく知られている種類である。幼虫は畜舎やゴミ処理場などで発生し、成虫は体長が4~8mmある大型のハエで、家屋内に侵入する性質がある。一般には、病原菌を媒介する衛生害虫として注意されている虫である。
ハエ目には、ハエ、アブ、カ、ガガンボなどが含まれ、世界各地に分布し、日本には五〇〇〇種以上が生息している。わたしたちが日常的に見かける身近な昆虫のグループといえるだろう。いわゆるハエには、イエバエやニクバエなどの大型のハエや小型のショウジョウバエがあり、衛生害虫や不快害虫として一般的にはいいイメージがもたれていない。博物館においてハエ目は、資料に穴を開けて卵を生みつけたり、幼虫が資料を食害したりするような、直接、資料に害を与える害虫ではないが、イエバエやニクバエのような大型のハエは、フンなどで資料を汚す恐れのある虫として認識されている。
ハエ目は、収蔵庫のように人の出入りが制限されている場所にはほとんどいないが、事務室や作業場などの人の出入りが多いところに集中して見られる。人がドアを開けるときや、ドアやシャッターの下にあるちょっとした隙間が、虫にとっては大きな通り道になっているのである。
網戸取り替え前とその後
民博で、特にハエ目が多くみられるのは、資料を出し入れする搬入口周辺である。民博の搬入口は、大型のシャッター一枚で外と内を隔てているだけである。そのため、シャッターを開けることによって簡単に虫が建物内に侵入できる状況となってしまうことから、かねてから搬入口に網戸を取り付ける防虫対策をおこなってきた。しかし、当時取り付けた網戸は、木枠に網を貼り付けた簡単な網戸であったため(写真1)、時間とともに木枠がひずみ、大きな隙間ができていた。また、網戸の建てつけが悪いことから、作業者の防虫に対する意識が弱まり、結果的に網戸が開放されていることが多かった。つまり、防虫のために取り付けた網戸が役割を果たしていなかった。そこで、二〇〇七年二月に網戸の取り替え工事がおこなわれ、現在の金属製のものに交換した(写真2)。
その効果は、生物生息調査の結果に顕著にあらわれている。生物生息調査は、補虫トラップ(写真3)を館内のいろいろなところに一五日間設置して、そこに捕まった虫を調べることによって、どこに、どんな虫が生息しているのかを調査するものである。網戸を取り替えた後の二〇〇七年春の調査結果と、取り替え工事前の同じ季節(二〇〇六年春)の調査結果を比べてみると(図)、搬入口付近でのハエ目の捕獲数が、六七匹から二七匹に減少しており、網戸を取り替えた効果があったことがわかる。これは、網戸が新しくなったことによって、大きな隙間がなくなり、虫が侵入しにくくなったことと、網戸をあつかいやすくなったことから作業者が網戸をこまめに開閉して開放している時間が短かくなったことなどが考えられる。
虫の侵入を完全に防ぐことは難しい。民博は、緑豊かな万博記念公園に囲まれた素晴らしい環境にある一方で、建物内に虫が侵入する危険性も高い立地条件といえる。だからこそ、生物生息調査の結果から虫の動向を確認し、その結果を参考に、施設的な改良とともに日常作業の見直しをおこない、ハエ目だけでなく、そのほかの害虫の侵入を未然に防ぐ努力をおこなっているのである。
ハエ目(学名:Diptera) イエバエ類 (学名:Muscidae)
ハエ目(Diptera)の成虫は、1対の翅をもつが、これは前翅で、後ろの翅は飛翔中の安定を保つための平均棍(こん)に変化している。イエバエ類は、日本で約250種が確認されており、ハエ目のなかでもっともよく知られている種類である。幼虫は畜舎やゴミ処理場などで発生し、成虫は体長が4~8mmある大型のハエで、家屋内に侵入する性質がある。一般には、病原菌を媒介する衛生害虫として注意されている虫である。
「水上人」の幻影
長沼 さやか(ながぬま さやか) 本館外来研究員
イメージと違う現実の生活
「言霊」とは、発したことを現実にすることばの力であるという。その文字や響きは、どこか神秘的で超自然的なイメージをたたえている。しかし、実態のあやふやなものが名前をつけられ、まことしやかに語られることならば、わたしたちの身近でも頻繁に起こりうる。わたしがフィールドワークをしていた中国広東省珠江(しゅこう)デルタでも、研究対象である「水上人(ソイソンヤン)」とよばれる人びとをめぐり、しばしばそのような状況を目にした。
中国には多くの民族が暮らしているが、その全人口の約九五パーセントは多数派である漢族で占められている。しかし、一口に漢族といっても方言、風俗習慣などはさまざまである。たとえば、首都北京から南へ二〇〇〇キロメートル以上離れた広東省では、標準中国語とは発音・語法ともに異なる広東語が話されている。しかし、彼らもまた漢族だ。さらに、広東の中心部である珠江デルタでは、同じ広東語の話者でも、住む場所によって風俗習慣が異なっている。やや海抜の高い地域に住む人たちは「陸上人(ロクソンヤン)」、海抜の低い「沙田(サーティン)」とよばれる地域に住む人たちは「水上人」とよばれ、ときに隔たりをもちながら生活してきた。
水上人はかつて「蛋家(ダンガ)」ともよばれ、その多くは船を家にしたり、川の中州などに簡素な小屋をつくったりして、流動的な生活を送っていた。レンガで建てた立派な家に住む陸上人からすれば、こうした人びとは住所不定の不審者であった。そのため、水上人はしばしば陸上人から差別されたり、非漢族とみなされたりした。やがて中華人民共和国成立後、こうした人びとも政策の影響を受け定住した。
文献などには、水上人は「先祖代々船に住み漁業をしてきた人びと」であり、「古代越族が漢族化したもの」と書かれている。船上生活は、広東の先住民族・越族の特徴だからという論拠らしい。しかし、父の世代まで船に住み漁業をしていたというわたしの知人は、決してそんなふうに思っていなかった。そもそも彼らは、自分たちを水上人と思っていない。ただ、漢族であると考えている。それに、水上人はかならずしも先祖代々船で暮らしていたわけではない。ある老人は言う。「わたしの家は、もとは陸で米屋をしていたが、祖父の代に破産し、家を売り払い、船で暮らすようになったんだ」。また、船上生活をしたことのない人もいる。生業も、漁業や水運業のような船を必要とするものに限らない。むしろ、陸上で賃金労働をしていた人のほうが多かった。つまり、文献を記した学者たちの決めつけをよそに、水上人は陸上に近い生活を送っていたのだ。
無形文化遺産の咸水歌
そんな水上人が、わたしが訪れている珠江デルタ南部の広東省中山市で、近ごろちょっとしたブームとなっている。水上人の民謡と言われる「咸水歌(ハムソイゴー)」が、民間芸術として脚光を浴び始めたのである。近年、中国では近代化とともに失われつつある「伝統文化」を保護し、観光資源として利用する動きが高まっている。そんな折りに、注目されたのが水上人の咸水歌だった。感情を即興で表現する咸水歌は、「テレビもインターネットもなかった時代の素朴な娯楽」とされた。こうした口上は、都市に生きる現代人のノスタルジーを巧みにくすぐった。
以後、中山市では、水上人の暮らしてきた沙田を「水郷(すいごう)」とよび、そこに住む人びとの風俗習慣を「水郷文化」と名づけ、観光資源として活用し始めた。二〇〇〇年には市内に、水郷文化の参観・体験を趣旨としたテーマパークが建設された。また、咸水歌の名手が、アマチュア歌手として政府に起用され、市内のみならず広東省内外に公演に出かけるようになった。著名な歌手を多く輩出した鎮(市に属する行政区)では、咸水歌の資料館がつくられた。さらに二〇〇六年には、その鎮の咸水歌が国の無形文化遺産に選ばれた。これらを経て、水郷文化をめぐる観光開発はさらに加速している。
意志を生みだすか
しかし、ブームに沸き立つ政府に対して、沙田の人たちの反応は薄い。そもそも、咸水歌は沙田の人びとの民謡なのかといえば、じつはそうでもないのである。咸水歌など歌ったこともない、咸水歌がどんなものか知らないという人もいる。自分たちはそう思っていないのに、他から水上人と言われるのと同様で、咸水歌という「伝統」もよそからもち寄られたものらしい。とすれば、いったい何が水上人という存在や、咸水歌という「伝統」を今日まで保持してきたのだろう。それは、「水上人」や「咸水歌」といった「名」であるように思える。それらはまるで言霊のように、書物や人びとの口に上るたび、水上人の幻影をまことしやかに描き出してきたのだろう。
そうしてみると、異なる方言や風俗習慣をもつ人びとを、一口に「漢族」とよび合わせることも、ある意味でことばの力と言えるのではないだろうか。ただ、水上人をめぐる状況と異なるのは、その幻影を受け入れようとする意志が、人びとに共有されているという点である。ことばに宿る力は、いつかその意志までも生みだすことができるだろうか。そんなことを考えながら、フィールドと日常のはざまを行き来している。
今年度から『月刊みんぱく』にインタビューのコーナーが戻ってきた。「みんぱくインタビュー」である。復活第1弾は6月号のヨーゼフ・クライナーさんで、8月号は人間文化研究機構の2代目機構長になられた金田章裕さんである。
このインタビューは『月刊みんぱく』が創刊されたときには「館長対談」という名前で、初代梅棹館長が、いろいろな分野の第一線で活躍する人と対談するものだった。対談に出演したのは学術分野だけでなく、芸術、スポーツ、政財界などじつにさまざまな分野で活躍していた人びとで、当時の民博に関心をよせる人びとの裾野の広さを物語っていた。さらに梅棹館長の軽妙でときに鋭く核心を突く質問と、それに対する対談者の対応が絶妙の緊張感をただよわせて、読む人を飽きさせなかった。最終回が182回(1993年3月号)であることから、梅棹館長は一人で182人を相手にしたのである。
梅棹館長退任後は「みんぱく・いんたびゅー」という名前で、おもに編集長が聞き手となって続けられたが、2004年4月号から編集方針が変わったこともあり、このコーナーは廃止され、特集が組まれることになった。それが今年になって復活したわけである。今のところ特集の合間に企画されているために、毎号登場するわけではないが、このインタビューコーナーも大切に育てていきたいと考えている。 (佐々木史郎)
このインタビューは『月刊みんぱく』が創刊されたときには「館長対談」という名前で、初代梅棹館長が、いろいろな分野の第一線で活躍する人と対談するものだった。対談に出演したのは学術分野だけでなく、芸術、スポーツ、政財界などじつにさまざまな分野で活躍していた人びとで、当時の民博に関心をよせる人びとの裾野の広さを物語っていた。さらに梅棹館長の軽妙でときに鋭く核心を突く質問と、それに対する対談者の対応が絶妙の緊張感をただよわせて、読む人を飽きさせなかった。最終回が182回(1993年3月号)であることから、梅棹館長は一人で182人を相手にしたのである。
梅棹館長退任後は「みんぱく・いんたびゅー」という名前で、おもに編集長が聞き手となって続けられたが、2004年4月号から編集方針が変わったこともあり、このコーナーは廃止され、特集が組まれることになった。それが今年になって復活したわけである。今のところ特集の合間に企画されているために、毎号登場するわけではないが、このインタビューコーナーも大切に育てていきたいと考えている。 (佐々木史郎)
定期購読についてのお問い合わせは、ミュージアムショップまで。 内容についてのお問い合わせは、国立民族学博物館広報企画室企画連携係【TEL:06-6878-8210(平日9時~17時)】まで。