ファシズム期の人類学―インテリジェンス、プロパガンダ、エージェント ★
館外での出版物
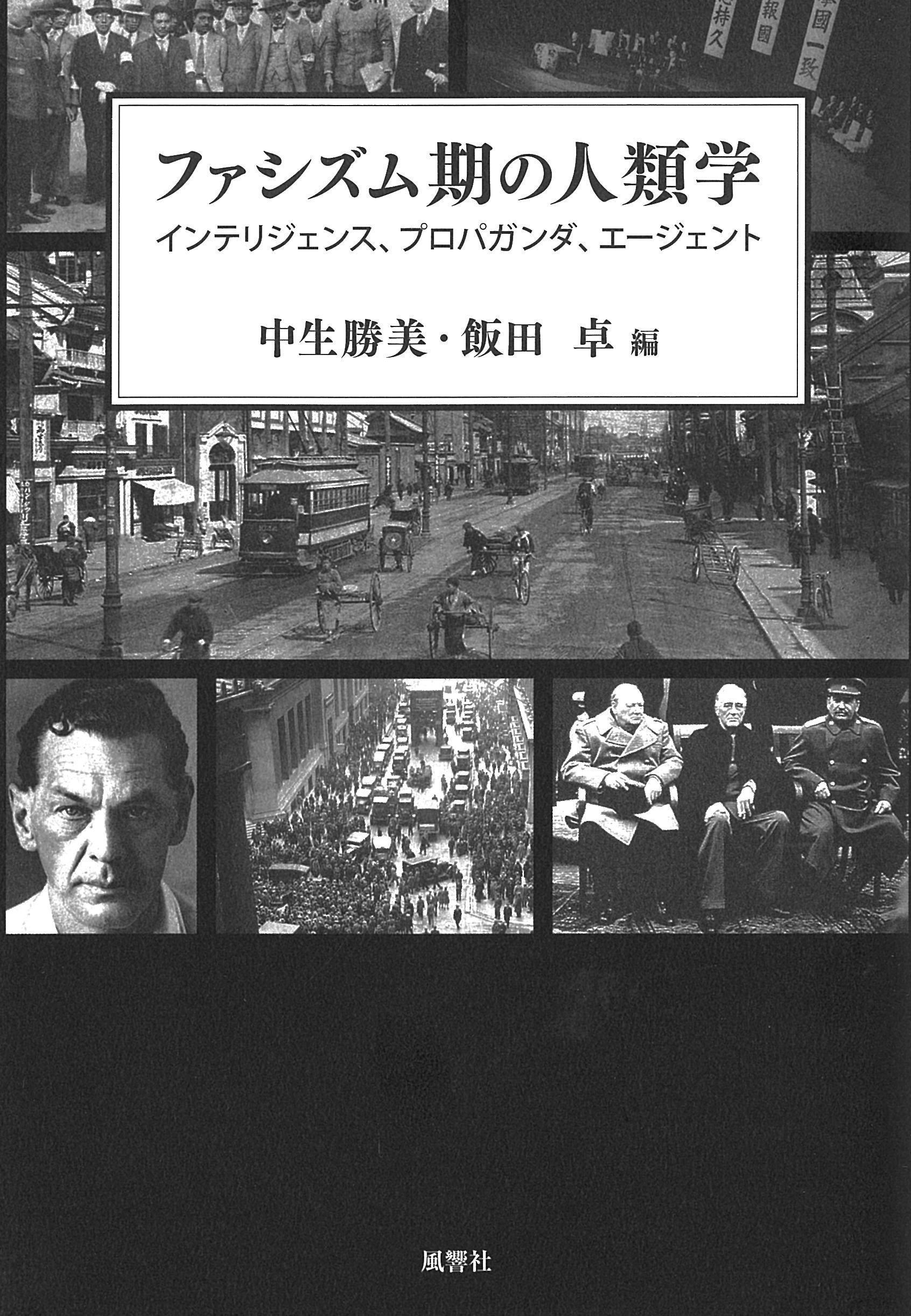
| 書名 | ファシズム期の人類学―インテリジェンス、プロパガンダ、エージェント |
| 著者名 | 中生勝美・飯田卓編 |
| 出版社 | 風響社 |
| 発行年月日 | 2025年5月30日 |
| 判型・体裁 | A5版 |
| 頁数 | 304頁 |
| ISBN | 9784894890480 |
| 定価 | 3,300円(税込) |
| 研究成果 |
共同研究成果: 人類学/民俗学の学知と国民国家の関係――20世紀前半のナショナリズムとインテリジェンス(2017.10-2023.3) |
主題・内容
科学の発展の道筋は、社会状況を反映してさまざまなかたちをとる。本書は、ファシズム期に各国が展開した科学政策に関連して、民族学(人類学、民俗学)分野でどのような変化が生じたかを広く深く論じたものである。
おすすめのポイント、読者へのメッセージ
学問は時として暴走します。だからこそ、時間が経ってから「脱植民地化」の動きが生じます。そのとき、なにが迷惑でなにが迷惑でなかったかを選別していく作業が不可欠。学問の社会性を学問自体が維持していくため、こうした科学史のアプローチは、分野を越えて重要になると思います。
目次
まえがき(中生勝美)
序論 人類学史の検証と自省のための方法論(中生勝美)
一 人類学的学知の自省
二 本書の鳥瞰図
第I部 エージェントとプロパガンダの人類学
第1章 戦前の内蒙古におけるドイツと日本の特務機関─モンゴル学者ハイシッヒと岡正雄(中生勝美)
はじめに
一 ハイシッヒと岡正雄
二 北京時代のハイシッヒ
三 内蒙古の日本特務機関
四 戦後のハイシッヒ
おわりに
第2章 ナチスドイツ時代における人種衛生学の位相(池田光穂)
はじめに
一 一九三三〜三九年─人種衛生学に基づく断種政策
二 一九三九〜四一年─T4計画
三 一九四二〜四五年─民族絶滅計画とその派生
おわりに
第3章 文化人類学、戦争、植民地統治─一九三〇~一九四〇年代のフューラー=ハイメンドルフとリーチの人生をめぐって(田中雅一)
はじめに
一 国境地帯のフィールドワーク
二 文化人類学と植民地統治
三 民族分布と歴史
四 敵性外国人、クリストフ・フォン・フューラー=ハイメンドルフ
五 陸軍少佐、エドマンド・リーチ
六 植民地統治との関係
おわりに
第4章 民族学者ペッタッツォーニ─ファシスト政権下のイタリア民族学(江川純一)
はじめに
一 ペッタッツォーニにおける宗教史学と民族学
二 民族学講座開講講演(一九三七年)
三 人種法の施行と第八回ヴォルタ学会(一九三八年)
おわりに
第5章 ベイトソンの戦時研究
─NARA、UCSCおよびLOC資料の分析から(飯嶋秀治)
はじめに
一 グレゴリー・ベイトソンと国民国家の関係
二 ミルトン・エリクソン
三 OSS
四 プロパガンダ
五 ベイトソンの象徴操作
六 軍事、セラピー、デザイン
第II部 インテリジェンスの学知展開
第6章 農村社会研究がインテリジェンスになるとき─学説史のなかの『須恵村』、社会史のなかのエンブリー(泉水英計)
はじめに
一 問題の所在
二 人類学の学説史のなかの『須恵村』
三 米国社会史のなかのエンブリー
おわりに
第7章 両大戦間期の日本民族学─フランスとの関係を中心に(飯田卓)
はじめに
一 国際連盟─国際文化交流の始まり
二 フランス国立極東学院─美術史と考古学を中心とした活動
三 松本信廣─考古学に関心を広げた東洋学者
四 エミール・ガスパルドヌ─フランスの日本学(一)
五 アンドレ・ルロワ=グーラン─フランスの日本学(二)
おわりに
第III部 ナショナリズムの周辺
第8章 鳥居龍蔵の西南中国調査にみる二つの民族観と中国への影響─中国民族学界からの評価に着目して(佐藤若菜)
はじめに
一 鳥居龍蔵と日清戦争─繰り返す調査と昇進、西南中国での手厚い援助
二 二つの民族観─『苗族調査報告』と『人類学上より見たる西南支那』の比較から
三 中国の民族学界による評価─苗族カテゴリーの確立
おわりに
第9章 ミンゾク学と宗教者─近代仏教者を例として(角南聡一郎)
はじめに
一 学僧の定義と歴史
二 僧侶とミンゾク学
三 今村完道の植民地経験と平和
四 近代仏教者とミンゾク学
おわりに
結論 学知のデコロナイゼーション(飯田卓)
あとがき(飯田 卓)
索引
