みんぱく公開講演会「流動化する家族のかたち――少子高齢社会を文化人類学から考える」

| 日時 | 2021年11月12日(金) 18:30 – 20:40(開場17:30) |
|---|---|
| 講演会場 | 日経ホール 東京都千代田区大手町1-3-7日経ビル3F |
| 主催 | 国立民族学博物館、日本経済新聞社 |
| 定員 | 300名(要事前申込み/先着順) ※ 申込受付は終了いたしました。 |
| 参加費 | 無料 |
☆ 手話通訳あり
☆ インターネットでのライブ中継も実施いたします。(要事前申込み)
☆ 新型コロナウイルス感染症の流行状況によっては開催の中止、形式の変更等となる場合もあります。ご了承ください。
趣旨
家族はもっとも身近なあつまりですが、その輪郭は決して固定的なものではありません。結婚、離婚、未婚によって家族のかたちは変化しますし、シェアハウスやペットへの関心の高まりは、新しい家族を求める姿ともいえます。安定しているようにみえる家族も、さまざまな制度やテクノロジーを駆使し、それに支えられています。
この講演会では、ヨーロッパと南アジアで、少子化や高齢化と向き合っている現代家族の輪郭が変動的であることに注目し、家族のかたちが流動化しつつあることについて考えます。産み・育て・食べさせ・世話し・介護する、生存の空間としての家族の、現代世界におけるあり方について考えていきます。同じ観点から、感染症や震災に対面した家族に起こっていることについて討論します。
プログラム
| 17:30 – 18:30 | 受付 | |
|---|---|---|
| 18:30 – 18:35 (5分) |
開会 | 津川悟(日本経済新聞社・大阪本社編集局長) |
| 18:35 – 18:40 (5分) |
挨拶 | 吉田憲司(国立民族学博物館長) |
| 18:40 – 19:10 (30分) |
講演 1 | 「自宅介護はどのように作動したか――EUオーストリアの山地農家」 森明子(国立民族学博物館教授) |
| 19:10 – 19:40 (30分) |
講演 2 | 「ケア空間としての家族の境界――インドの都市中間層」 松尾瑞穂(国立民族学博物館准教授) |
| 19:40 – 19:55 (15分) |
休憩 | |
| 19:55 – 20:40 (45分) |
コメント | 「保育に映し出された地域と家族――東日本大震災をめぐって」 大門正克(早稲田大学特任教授) |
| パネルディスカッション | 「災害・感染症とケアと家族」 森明子× 松尾瑞穂 × 大門正克 |
講師紹介

森明子(国立民族学博物館教授)
専門は文化人類学。オーストリア南東の村や、ドイツのベルリンで、人びとが変容する現代世界をどのように生きているか追っている。著書に『土地を読みかえる家族――オーストリア・ケルンテンの歴史民族誌』(1999年、新曜社)、編著に『ケアが生まれる場――他者とともに生きる社会のために』(2019年、ナカニシヤ出版)などがある。

松尾瑞穂(国立民族学博物館准教授)
インドをフィールドに、出産や不妊といった生殖にまつわる実践とジェンダーや家族とのかかわりについて研究している。著書に『ジェンダーとリプロダクションの人類学―インド農村社会における不妊を生きる女性たち』(2013年、昭和堂)、『代理出産の文化論―出産の商品化のゆくえ』(2013年、風響社)がある。
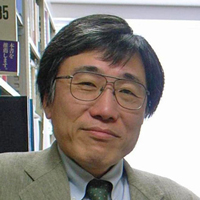
大門正克(早稲田大学教育・総合科学学術院特任教授)
日本近現代の民衆史について、歴史学の視点から調査研究を進めている。いまを生きる人に過去の経験を尋ね、地域の歴史を探り、歴史と現在を往還するなかで研究に取り組んでいる。著書に『語る歴史、聞く歴史―オーラル・ヒストリーの現場から』(2017年、岩波新書)、共著に『「生存」の歴史と復興の現在―3・11 分断をつなぎ直す』(2019年、大月書店)などがある。
地図
講演会場:日経ホール(東京都千代田区大手町1-3-7日経ビル3階)

交通機関
東京メトロ
- 千代田線「大手町駅」神田橋方面改札より徒歩約2分
- 丸ノ内線「大手町駅」サンケイ前交差点方面改札より徒歩約5分
- 半蔵門線「大手町駅」皇居方面改札より徒歩約5分
- 東西線「大手町駅」中央改札より徒歩約9分/「竹橋駅」4番出口より徒歩約2分
都営地下鉄
- 三田線「大手町駅」大手町方面改札より徒歩約6分
地下鉄「大手町駅」下車C2b出口直結
申込方法
※ 申込受付は終了いたしました。
お問い合わせ先
- 国立民族学博物館 研究協力課
- TEL 06-6878-8209
- メールアドレス koenkai★minpaku.ac.jp
※★印を@に変更して送信ください。
