みんぱく創設50周年記念特別展「民具のミカタ博覧会―見つけて、みつめて、知恵の素」関連シンポジウム「Doing TSUNEICHI 『忘れられた日本人』を読み直す」
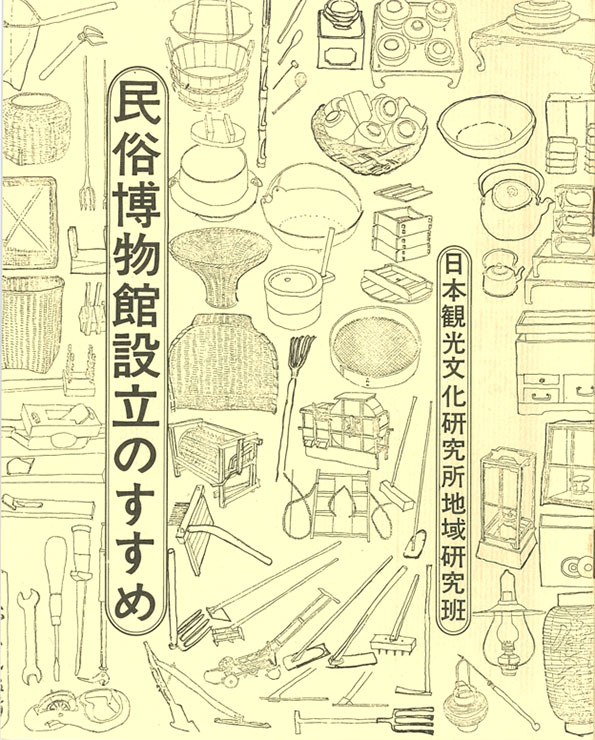
| 日 程 | 2025年4月13日(日)13:20~16:25(12:30開場) |
|---|---|
| 場 所 | 国立民族学博物館 第5セミナー室(本館2F) |
| 定 員 | 【会場参加】50名(要事前申込み/先着順) ※受付終了 【オンライン配信】450名(要事前申込み/先着順) |
| 参加費 | 無料 |
| 主 催 | 国立民族学博物館 |
| 共 催 | 国立歴史民俗博物館「フィールドサイエンスの再統合と地域文化の創発」、現代民俗学会 |
趣旨
近年、宮本常一の『忘れられた日本人』が再び読まれている。民衆の持ち伝えた歴史への真摯なまなざしに立脚し、人間が人間らしく生きる最前線として「生活」を位置付け、フィールドで出会う人々との関わりから問いを起こすのが宮本民俗学である。それが存分に発揮された『忘れられた日本人』が名著とされる背景にあるのは、現代における地域のありようをもう一度足元から見つめ直そうとする機運や、宮本の社会実践的な学問の態度に学ぼうとする、再評価の視点である。
『忘れられた日本人』は、確かに読むたびに何かを得るような名著である。しかし、一方でそれが出版された一九六〇年前後、そしてこの本が読まれていった一九六〇年代、一九七〇年代の同時代において、本書は実際どのようにとらえられていたのだろうか。それを読み解くことは、今回の特別展「民具のミカタ博覧会」で紹介する、EEMコレクションとムサビ・コレクションが収集された時代を考える重要なヒントとなろう。
本シンポジウムは、武蔵野美術大学市ヶ谷キャンパスを拠点に断続的に進められてきた『忘れられた日本人』の読書会「Doing TSUNEICHI」の議論をベースに企画する。本読書会は、『忘れられた日本人』を基点とし、身近な歴史や地域文化をみずからの課題として協働的に歴史叙述・文化実践を進める、パブリック・ヒストリー、パブリック・フォークロアの問題を議論する緩やかな研究会である。
名著として神話化するのではなく、より時代の中にもう一度埋め込んで再考し、現代の人文学の公共性の議論と、ミュージアムのコレクションの意義について考える材料としたい。
プログラム
| 13:20-13:25 |
開会あいさつおよび趣旨説明 加藤幸治(武蔵野美術大学教授) |
|---|---|
| 13:25-13:55 |
宮本常一が若者たちに求めたDoingの現代性(仮) 加藤幸治(武蔵野美術大学教授) |
| 13:55-14:25 |
同時代の批判から再考する『忘れられた日本人』(仮) 北條勝貴(上智大学教授) |
| 14:25-14:55 |
民話採訪の実践性と『忘れられた日本人』成立の背景(仮) 山川志典(武蔵野美術大学非常勤講師) |
| 14:55-15:10 | 休憩 |
| 15:10-15:20 |
コメント 小谷竜介(文化財防災センター統括リーダー) |
| 15:20-16:20 |
パネルディスカッション「Doing TSUNEICHI 宮本常一から歴史実践を問い直す」 コーディネーター 加藤幸治 パネラー 日髙真吾、北條勝貴、山川志典, 小谷竜介 |
| 16:20-16:25 |
閉会挨拶 日髙真吾(国立民族学博物館教授) |
申込方法
以下事項を記入し、E-mail:bunkazai★minpaku.ac.jp 宛にお申し込みください。
(★を@に変換して送信ください。)
※会場参加は受付終了
- 申込期間:2025年3月13日(木)~4月11日(金)
- 件名に「Doing TSUNEICHI 『忘れられた日本人』を読み直す」と記入してください。
- 本文に氏名及び連絡用メールアドレスをと記入してください。
- 参加形態としてオンラインか会場参加を記入してください。
お問い合わせ先
みんぱく創設50周年記念特別展
「民具のミカタ博覧会―見つけて、みつめて、知恵の素」
関連シンポジウム「Doing TSUNEICHI 『忘れられた日本人』を読み直す」事務局
E-mail:bunkazai★minpaku.ac.jp (★を@に変換して送信ください。)
