2019年11月15日(金)みんぱく公開講演会「アニメ『聖地』巡礼――サブカルチャー遺産の現在」
東京都千代田区大手町1-3-7日経ビル3F

| 日 時 | 2019年11月15日(金) 18:30~20:40(開場17:30) |
|---|---|
| 講演会場 | 日経ホール 東京都千代田区大手町1-3-7日経ビル3F ※事前申込が必要です。 |
| 定 員 | 600名(先着順) |
| 参加費 | 無料(要事前申込) ☆手話通訳あり |
| 申込方法 | ※申込フォームまたは往復はがきによる事前申込制 ※往復はがきは11月8日(金)締切(当日消印有効) ★ 申込受付は終了いたしました。 |
| 主 催 | 国立民族学博物館、日本経済新聞社 |
趣旨
人文社会科学に先んじて、地域振興を進める内閣府や経済産業省、地方自治体が注目してきたクール・ジャパン。日本では、地域と強く結びついたアニメを観光資源に用いる「聖地巡礼」も、クール・ジャパンの潮流のなかで始まりました。しかし、日本から離れて海外の事例に目を向けたとき、同様の現象はどのような意味を帯びているのでしょうか。また、アニメをはじめとするポピュラー・カルチャーの流行サイクルの速さと、息長く持続させるべき観光振興は、はたして相性がよいといえるのでしょうか。文化や文化遺産の問題を地域の問題として考えてきた人類学者・民俗学者が、聖地観光の意味を考えます。
プログラム
司会飯田卓(国立民族学博物館教授)
| 17:30 – 18:30 | 受付 | |
|---|---|---|
| 18:30 – 18:35 (5分) |
開会 | 藤井達郎(日本経済新聞社常務執行役員・大阪本社代表) |
| 18:35 – 18:40 (5分) |
挨拶 | 吉田憲司(国立民族学博物館長) |
| 18:40 – 19:00 (25分) |
概要説明 | 「遺産観光におけるバーチャリティ」 飯田卓(国立民族学博物館教授) |
| 19:00 – 19:25 (25分) |
講演1 | 「聖地巡礼のラビリンス――現代日本における旅・キャラクター・物語」 川村清志(国立歴史民俗博物館准教授) |
| 19:25 – 19:50 (25分) |
講演2 | 「アニメのある景観――中国地域の客家文化継承をめぐって」 河合洋尚(国立民族学博物館准教授) |
| 19:50 – 20:05 (15分) |
休憩 | |
| 20:05 – 20:40 (35分) |
パネルディスカッション | 川村清志×河合洋尚 司会:飯田卓 |
講演内容

概要説明「遺産観光におけるバーチャリティ」
飯田卓(国立民族学博物館教授)
専門は文化人類学、ヨーロッパの民族誌研究。1986年以来、オーストリア国境の村とドイツのベルリンで、社会変容のなかの家族について調査研究を行う。主な著作として、『ケアが生まれる場―他者とともに生きる社会のために』(2019年、ナカニシヤ出版)、『ヨーロッパ人類学の視座―ソシアルなるものを問い直す』(2014年、世界思想社)、『土地を読みかえる家族―オーストリア・ケルンテンの歴史民族誌』(1999年、新曜社)などがある。
<講師紹介>
有形のものを修復によって保存するという従来の文化遺産学をのり越え、人びとの実践の反復によって有形無形の文化を次世代にひき継ぐという「文化遺産の人類学」を提唱している。著書に『海を生きる技術と知識の民族誌――マダガスカル漁撈社会の生態人類学』(世界思想、2008)、編著に『文明史のなかの文化遺産』(臨川書店、2017)などがある。

講演1「聖地巡礼のラビリンス――現代日本における旅・キャラクター・物語」
川村清志(国立歴史民俗博物館准教授)
アニメや漫画の舞台となった場所を巡る「聖地巡礼」は、2000年代以後に大きく展開します。聖地の中には、地方の自治体や企業を巻き込み、国際的な観光地に成長する一方で、ファンと地域社会が物語を超えた新たな関係性を築くケースもみられます。地域社会の実情に対応した関係性の深化に注目しながら、聖地の現在を考えていきます。
<講師紹介>
学術博士。日本の祭礼や民俗芸能を中心に、フィールドワークに基づく研究を続けてきた。メディアによる文化表象への関心から映像文化の批評やドキュメンタリー制作も行う。主な作品に『明日に向かって曳けー石川県輪島市皆月山王祭の現在』(DVD監督、2016)、『石川県輪島市山王祭フォトエスノグラフィー準備編』(川村清志・倉本啓之編、2018)などがある。
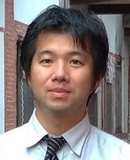
講演2「アニメのある景観――中国地域の客家文化継承をめぐって」
河合洋尚(国立民族学博物館准教授)
最近、台湾や中国本土では、景観デザインにアニメ・キャラクターをとりいれるという、新たな動きがみられます。この動きは、民族の文化遺産が失われるという危機と深くかかわっています。中華圏ではアニメはどのようにとらえられているのか。アニメを景観デザインとして使うことでどのような効果が期待されているのか。客家と呼ばれる人々を事例として、この問いに答えていきます。
<講師紹介>
中国南部における文化的景観の創出について、人類学の視点から調査研究を行っている。近年は環太平洋の漢族、なかでも客家と呼ばれる集団を調査の対象としている。著書に『景観人類学の課題――中国広州における都市環境の表象と再生』(風響社、2013)、『客家――歴史・文化・イメージ』(現代書館、2019)などがある。
地図
講演会場:日経ホール&カンファレンスルーム(東京都千代田区大手町1-3-7 日経ビル3階)
詳しくはこちら(日経ホール&カンファレンスルームホームページ)

交通機関
[地下鉄]東京メトロ
- 千代田線
「大手町駅」神田橋方面改札より徒歩約2分 - 丸ノ内線
「大手町駅」サンケイ前交差点方面改札より徒歩約5分 - 半蔵門線
「大手町駅」皇居方面改札より徒歩約5分 - 東西線
「大手町駅」中央改札より徒歩約9分
「竹橋駅」4番出口より徒歩約2分
都営地下鉄
- 三田線
「大手町駅」大手町方面改札より徒歩約6分
地下鉄「大手町駅」下車C2b出口直結
申込方法
※申込受付は終了いたしました。
お問い合わせ先
国立民族学博物館 研究協力課
TEL 06-6878-8209
メールアドレス koenkai★minpaku.ac.jp ※★印を@に変更して送信ください。
