みんぱく創設50周年記念特別展「民具のミカタ博覧会―見つけて、みつめて、知恵の素」ご挨拶
皆さんこんにちは。
本日はようこそ、国立民族学博物館創設50周年記念特別展「民具のミカタ博覧会―見つけて、みつめて、知恵の素」の開会式におあつまりいただきまして、誠にありがとうございます。
みんぱく館長の吉田憲司です。と、申し上げてご挨拶するのも、あと2週間ほどのことになりました。
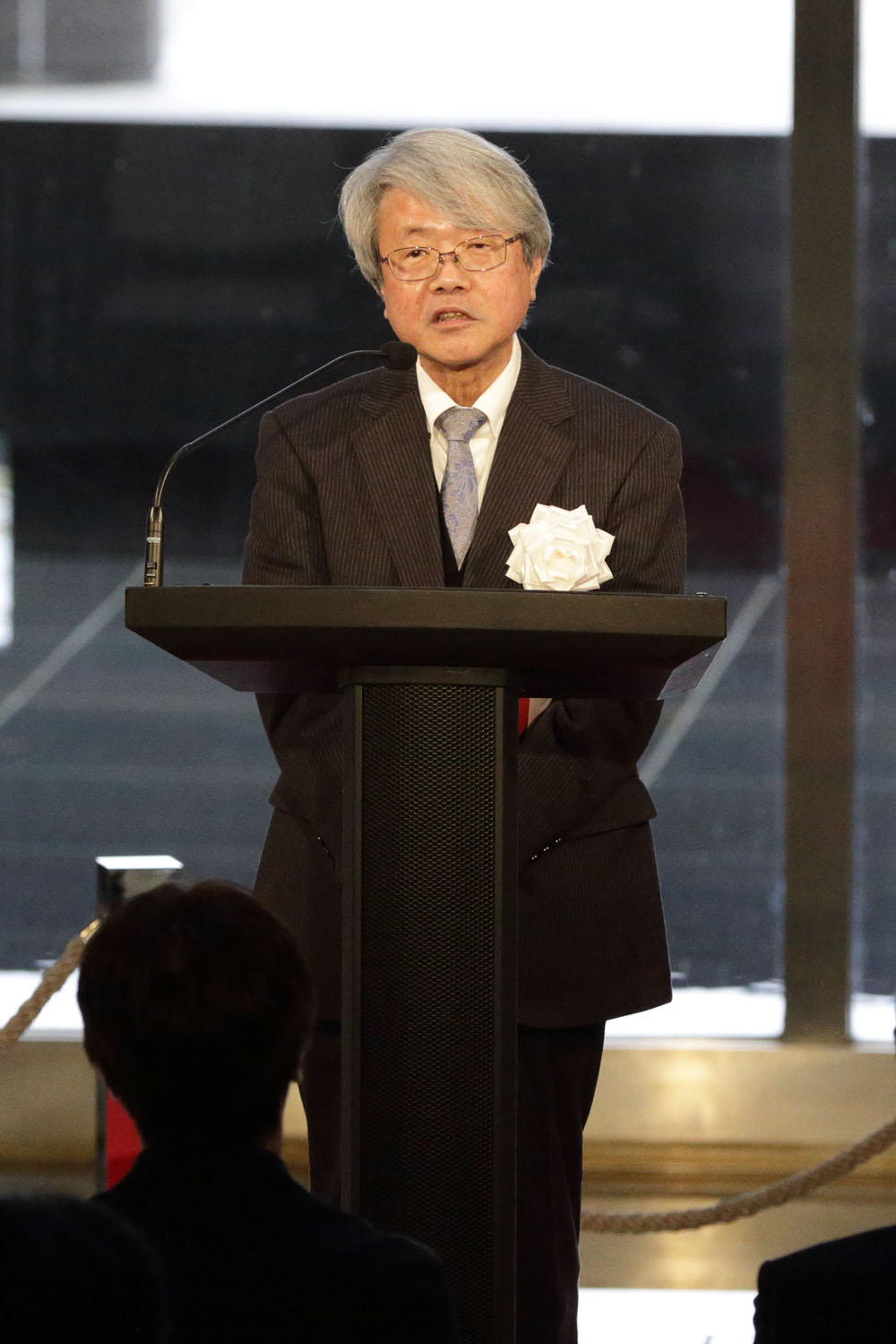
私は、この3月末日で、国立民族学博物館長の3期8年の任期が満了となり、民博を離れます。館長としての最後の仕事のひとつとして、今日ここで御挨拶をさせていただきます。
国立民族学博物館(みんぱく)は、博物館機能をもつ文化人類学・民族学とその関連分野の大学共同利用機関として1974年に創設され、1977年にこちら大阪・万博記念公園内に開館しました。昨年、2024年6月に創設50周年を迎えました。周年期間の終りの時期は、2024年度末、つまり今年の3月末としておりますため、この特別展が、創設50周年記念事業の最後。「大トリ」の事業ということになります。
民具という言葉は、私たちが日常、人びとの用いる生活用具の総称としてごく一般的に用いる言葉になっていますが、もともと日本語の語彙にはなかったものです。渋沢栄一の孫で、日銀総裁や大蔵大臣を務めた渋沢敬三が、アチックミューゼアムの活動を主宰する中で昭和10(1935)年に初めて用いた言葉とされています。その渋沢の薫陶を受け、日本各地を旅して民俗学の研究と民具の収集に没頭し、自ら巨大な民具のコレクションを形成して「旅する巨人」とよばれたのが、宮本常一でした。
このようなアチックミューゼアムの活動や宮本常一の調査行を通じて、日本の民具については、悉皆的なコレクションが形成されました。宮本常一が中心となって築いた民具コレクションは、現在、武蔵野美術大学に所蔵されていますが、その総点数は9万点を数えます。
一方、日本の歴史の中で、初めて形成された世界全域を対象とした生活用具のコレクションが、1970年に大阪・千里で開催された日本万国博覧会を機に組織された「日本万国博覧会世界民族資料調査収集団(Expo’70 Ethnological Mission: EEM)によるコレクションです。
この70年大阪万博でテーマ館のプロデューサーとなった岡本太郎は、テーマ館の一部である太陽の塔の地下に、人類の根源を示すものとして世界の民族資料を展示しようというプランを立て、泉靖一・梅棹忠夫の指揮の下で若手の民族学や人類学研究者を中心とする総勢20人からなる収集団が組織されました。その収集団が世界各地から集めた資料約2600点は万博での展示の後、民博の創設とともに、民博に収められ、民博開館時の収蔵品のひとつの核となります。
民具という言葉は、その成立の経緯から、主として日本の民衆が作り出し、使用してきた生活用具の呼称といえ、世界各地の生活用具を民具と呼ぶことは とくに民族学や文化人類学の世界では一般的ではありません。ただ、今回の特別展では、武蔵野美術大学の収集品と、EEMによる収集品をあえて「民具」とひとしなみにしてよび、その両者を同じ地平において突き合わせることで、日本人が生活の中で生み出したモノと、世界の人々が生み出したモノの異同を検証しようとしています。その作業を通じて、どちらか一方だけを見ていたのでは気づかない、素材や用途に応じた形の共通性と多様性、造形と身体の関わり、特定の形状に注がれたまなざしのありようが浮かび上がってくることと思います。
折りしもこの特別展の会期中に、大阪で2度目の万国博覧会、2025大阪・関西万博(会期:2025年4月13日~10月13日)が開幕します。今度の万博のテーマ館である8つのシグネチャー・パビリオンのなかには、70年万博の、とくに太陽の塔のレガシーを受け継ぎ、その新たな展開として企画を練り上げたパビリオンも含まれています。本特別展には、2025年日本国際博覧会協会からのご後援もいただいております。70年万博のレガシーを受け継ぐ、もうひとつの「博覧会」として、特別展「民具のミカタ博覧会―見つけて、みつめて、知恵の素」をお楽しみいただければと思います。
今回の特別展は、武蔵野美術大学と国立民族学博物館の共同企画といってよいものですが、その展示の実現には、武蔵野美術大学の皆さんをはじめ、数多くの機関、多くの方々からご協力、ご後援をいただきました。
実行委員を務めていただいた皆さんを始め、ご支援をいただいた皆さまにこの場をお借りしまして、厚く御礼を申し上げます。
では、この後、「民具のミカタ博覧会」をご堪能ください。
本日はお越しいただき、まことにありがとうございました。

